|
|
|
|
| 浮羽の船越 |
|
迂闊にも筑後川流域に「船越」地名があることに気付いたのは、ほんの五~六年前のことでした(久留米市田主丸町船越)。
一部の例外はあるものの、この「船越」という地名は、ほとんど海岸部に位置する地名であり、その分布は沖縄の先島から青森の八戸まで及んでいます。
このことは、その存在を以って海岸の痕跡と考えることも、ある程度までは許されるかも知れません。ただし“海岸部に位置する地名”という表現には現在の海岸線ばかりではなく、その地名が成立した時代の海岸線という意味も同時に持たせているつもりです。
さて、田主丸の船越地名についても古代には有明海が相当奥まで湾入していたことが想定されています(『久留米市史』ほか)。また、その時代には現在、最大で上下六メートルと言われる有明海の潮汐の幅も、なお、大きく凌駕していたとも考えられており、この付近までが満潮時の臨海部であったとすることは当然許されるでしょう。
大潮にはさらに上がりますし、台風などの高潮までも考えれば、僅かでも潮を被る土地のラインは想像を越えかなりの内陸まで入る可能性さえもあります。
もちろん、この地の船越の場合には高い半島とか切立った岬が船の進路を遮っていた訳ではなく、ただただ平坦な芦原や氾濫原野が広がっていたに過ぎません。後でもふれますが、海の「船越」が岬や半島、さらには島一つをもショート・カットするものがあったことを考えると、この浮羽の「船越」はどのように考えるべきでしょうか?
もちろん、日本列島の全域に分布する船越地名から考えれば、この浮羽の「船越」も海洋民族が住み着いた地名と考えることは十分に許されるでしょう。
ただ、私にはそれだけでは済まない、もっと深刻な意味を持った地名であるように思えてなりません。
前置きが多少長くなり過ぎましたが、田主丸の「船越」の話に入りましょう。
一つのモデルに過ぎませんが、私には浮羽の山に端を発する筑後川の支流巨瀬川(佐賀市にも巨勢川があります)との関係で考えるべきもののように思えてなりません。
仮に浮羽や田主丸辺りから、当時は遥かに北に振れていたと言われる筑後川本流左岸の中ほどに木材を集積させることを考えてみましょう。
一旦は下流の大川風浪宮辺りまで流し(実際にはそこまで流す必要はないのかもしれませんが)、再び上げ潮を利用して搬送するよりは、点在する三日月湖や沼地なども利用できたはずであり、並走する複数の小河川を渡り、ほとんど障害物のない平坦地を田主丸の「船越」辺りで直接横切った方が時間も含めてはるかに経済的であったはずであり、筑後の平坦地を流れる何本もの小河川を実際に横切る「船越」が行なわれていた痕跡地名と考えたいのです。
なお、筏流しについては、『筑後川を道として』語り渡辺音吉・聞き書き竹島真理(不知火書房)が参考になります。
筏流しという今や例外的に思えるものを持ち出しましたが、田主丸の船越地名が成立した時代、最大の搬送物資とは材木や木材(船も含みますが)に石材でしかなく、筑後川を跨いで、人や食料が移動する場合にも、一旦、下流まで降り、上げ潮を待って筑後川(もちろん当時は筑後川とは呼ばれていませんが)を遡上するよりは、当然にも船で横断したはずであり、その際に一部区間については船を曳いたと考えれば分かり易いかも知れません。
ただ、この仮説に留まることなく、話をもう少し展開させてみましょう。 |
|
古代において大規模な木造建築物が太宰府一帯に大量に造られた事は皆さんにも異論はないでしょう。では、その木材はいったいどこから調達され、どのように運ばれたのか?と、考えてください。
もちろん、建設予定地に大木を調達できる森(できれば平坦地が理想です)があれば、その地を伐り開き、近世の用語に従えば普請から作事へと進むだけで良いのですが、凡そ、トラックやクレーンなどといった便利なものが一切存在しなかった時代においては、船と筏と人力に依存せざるを得なかったことは明らかでしょう(釣瓶の井戸があったのですから木製の長大クレーン程度は間違いなくあったでしょうが)。
してみると、目を九州最大級の大河である筑後川と太宰府に近接する宝満川に向けることは至極当然なことと言えるでしょう。
いきおい、日田、浮羽方面で調達された大木は筏船として筑後川を下り、再度、有明海の巨大な潮汐を利用し、宝満川から支流の山口川を持ち上げられたと考えることは十分に許されるでしょう。
そもそも、博多湾に木材が持ち込まれたとしても、御笠川は利用できるものの、水量には乏しく、かなり早い段階から陸上を曳かねばならなかったはずであり、一般的には針葉樹を調達し難い玄海灘側よりは、筑後川流域から調達されたと考えるのが自然でしょう。
恐らく、正規のルートは筑紫野市を北流する高尾川に限りなく近接する西鉄朝倉街道駅、JR天拝山駅の東に位置する筑紫野市の針摺から紫付近のはずで、ここまでは川を利用して曳き上げたはずです。そして、その時代からその搬送を支える人々が組織的に、常時、配置されていたと考えています。
一番大きな初夏の大潮の満潮を利用し、筏や分解された木材を単独で運べる限界点まで運び、後は堰を造り、閘門などによって川を曳けば、かなりのところまでは搬送できたと考えるのですがどうでしょうか?
そして、非常に面白い事に、現在は消えましたが、この筑紫野市紫には塩浸(今でもマンションなどの名前に拾えます)という地名まであったのです。
一方、針摺(これについてはアイヌ語地名説があることは承知していますが)という地名まで揃っています。
まず、大工の棟梁という言葉は棟(屋根最上部の横木)と梁(柱に対する横木)を組上げる技術者を意味します。ここで「針摺」という地名を考える時、恐らく“梁摺”のことであり、梁を摺って木材を運んだ地名に思えるのです。これが的を得ているか否かは、旧字名などを詳しく洗い、現地を調べるなど将来に待ちたいと思います。
今のところは田主丸の「船越」についてミクロ的な話をしただけですが、「船越」や「針摺」など、現地の伝承や古文書を拾うなど、今後とも調査を進めたいと思います。
さて、「船越」地名が全国的にどのように分布しているかに目を向けて見ましょう。 |
|
| 船越という地名 |
|
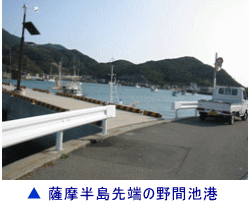 船越という地名があります。 船越という地名があります。
"フナコシ"とも"フナゴエ"とも呼ばれています。
決して珍しいものではなく、海岸部を中心に漁撈民が住み着いたと思える地域に分布しているようです。 |
|
 |
|
遠くは八郎潟干拓で有名な秋田県男鹿半島の船越(南秋田郡天王町天王船越)、岩手県陸中海岸船越半島の船越(岩手県下閉伊郡山田町船越)、岩手船越という駅もあります。また、伊勢志摩の大王崎に近い英虞湾の船越(三重県志摩市大王町船越)、さらに日本海は隠岐の島の船越(島根県隠岐郡西ノ島町大字美田)、四国の宿毛湾に臨む愛南町の船越(愛媛県南宇和郡愛南町船越)、……など。
インターネットで検索したところ、北から青森、岩手、宮城、秋田、福島、栃木、埼玉、千葉、神奈川、新潟、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、鳥取、広島、山口、愛媛、福岡、長崎、沖縄の各県に単、複数あり、県単位ではほぼ半数の二三県に存在が確認できました(マピオン)。もちろんこれは極めて荒い現行の字単位の検索であり、木目細かく調べれば、まだまだ多くの船越地名を拾うことができるでしょう。
それほど目だった傾向は見出せませんが、九州に関しては、鹿児島(奄美大島にはありますが)、宮崎、熊本、佐賀、大分にはなく、一応、"南九州には存在しないのではないか"とまでは言えそうです。なお、沖縄のさらに南、先島諸島の石垣島の北半部に船越(フナクヤ、フナグヤ)あることを紹介しておきます。
勝手な思い込みながら、海人(士)族の移動を示しているのではないかと考えています。
この点から考えると、大分県南部や熊本県の八代あたりにあってもよさそうなのですが、ちょっと残念な思いがします。大分にはたしか海士(海人)部があったはずですし(現在も南、北海士郡があります)、かつては海賊の拠点でもあったのですから。もちろん地名の意味は半島の付け根で、廻送距離を大幅に軽減するために船を担いだり曳いたり、古くはコロによって、後には台車などに乗せて陸上を移動していたことを今にとどめる痕跡地名であり、踏み込んで言えば普通名詞に近いものとも言えそうです。
ここで、一応お断りしておきます。"佐賀にはない"としましたが、日本三大稲荷と言われる鹿島市の祐徳稲荷神社南側の尾根筋に「鮒越」(フナゴエ)という地名があります。地形から考えてこれはここで言う船越を行なった地名ではないと思います。また、表記が「船越」であっても鳥取県西伯郡伯耆町の船越のように本当の山奥にあるものもありますので、ここで"船越"が行なわれたわけではありません。あくまでも全国の船越という地名の中には"船越"が行なわれていたものがかなりあるのではないかというほどの意味であることをご理解下さい。また、山奥にあっても、海岸部の船越地名が移住などによって持ち込まれたものがありますので、地名の考察とは非常に難しいものです。 |
|
| 九州の船越 |
この船越地名が九州西岸を中心にかなり分布しています。近いところでは佐世保市の俵ヶ浦半島の付け根に上船越、下船越という二つの集落があり、実際に船を運んだという話も残っています(長崎県佐世保市船越町)。
「佐世保から目的地の鹿子前(かしまえ)や相浦(あいのうら)の方に向かう途中に俵ヶ浦半島があり、遠回りしなければなりません。遠回りすれば風向きが変ったり、天候が急変することもあります。そこで半島の付け根の平坦な地形のところで、船を陸にあげ、小さな船はかつぐなり、大きな船は引っ張るなりして陸地を越えました。荷物はひとつひとつ運び、乗客や乗組員は歩き、最後に船を丸太を並べたコロの上を引っ張りました。」(「ふるさと昔ばなし」佐世保市教育委員会・佐世保市図書館)
他にもありますのでいくつか例をあげてみましょう。十年ほど前まで良く釣りに行っていた魚釣り(メジナ、キス)の好ポイントです。長崎県の平戸島の南端に位置する志々伎崎ですが、ここに小田と野子の二つの船越(長崎県平戸市大志々伎町)があります。特に小田の船越は誰が考えても船を曳いた方が断然楽と思えそうな地形をしています。
また、福岡市の西に糸島半島がありますが、この西の端、船越湾と引津湾に挟まれた小さな岬の付け根にも船越地名があります(福岡県糸島郡志摩町大字久家)。
引津湾と船越湾というニつの小湾(唐津湾の一部)の間に岬が飛び出していますが、その根っ子のところが、字船越です。縄文時代や弥生時代の舟は底が浅かったし、ずうたいも小さい。一本造りの丸木舟や筏。
こういうものなら、岬をずっーと回るより、根っこの部分を"押して"越えた方が早いはずです。五十メートルや百メートルくらい、うしろから押す、前から綱で引っ張る。その方がずっと手っ取り早いのです。時間とエネルギーの節約なのです。というわけで、日本列島各地にこの地名が分布しています。 |
|
| 対馬 小船越 と阿麻氏*留神社 |
|
| もうひとつ例をあげましょう。この船越は"フナゴエ"と呼ばれています。対馬の二つの船越です。今の対馬は大きく二つの島に分かれていますが、昔は一島を成していました。対馬の中央にある浅茅湾は複雑な溺谷が幾つもあるリアス式海岸ですが、ここには非常に幅の狭い地峡がいくつもあります。対馬の東海岸から西海岸に船で移動するためには七〇キロあまりも航走することが必要になりますので、昔から"船越"が行なわれてきましたが、ここに運河が造られます。まず、大船越瀬戸が寛文一二年(一六七一年)宗義真(宗家第二一代)によって開削されます(「…昔から船を引いてこの丘を越え、また荷を積み替えて往き来きした。船越の地名はここに由来すると言われる。…」=現地大船越の掲示板)。その後、明治三三年(一九〇〇年、結局、日露戦争では使用されなかったようですが)には艦隊決戦を想定した運河=万関瀬戸(マンゼキセト)が帝国海軍によって掘られます(ダイナマイトを大量に使う難工事だったようです)。 |
|
 |
|
| 当然にも、大船越(長崎県対馬市美津島町大船越)があれば小船越(〃美津島町久須保)があります。小船越には知る人ぞ知る阿麻氏*留神社(アマテルジンジャ)がありますが、この小船越にも「東西から入江が入り込み地峡部を船を曳いて越えた。ここは小舟が越えたので小船越。大きい船は大船越で越えた」(史跡船越の表示板)という伝承があります。北に位置する小船越には水道はありませんが、この小船越と対馬空港に近い南の大船越の間にあるのが万関瀬戸になります。 |
|
| 『肥前国風土記』、『延喜式』に見る高来郡駅と船越 |
|
| 実は、この船越地名が有明海沿岸にもあります。諫早の船越(長崎県諌早市船越町)と小船越(〃小船越町)です。また同地には貝津船越名(〃大字貝津小船越名/長崎県内には末尾に"名"が付く地名が非常に多い)という地名もあります。ここの船越地名が古いものであることは確かです。肥前国風土記や平安時代に編纂された「延喜式」(*)に、この"船越駅"(駅=ウマヤ)のことが出てきます。「延喜式」に駅馬五疋が置かれていたと書かれていることから考えると、烽火(トブヒ)の存在とともにこの諫早という土地が政治、軍事の重要な拠点であったことが容易に想像できます。 |
|
| * 延喜式:①弘仁式・貞観式の後を承けて編纂された律令の施行細則。平安書初期の禁中の年中儀式や制度などの事を漢文で記す。50巻。…(広辞苑) |
|
|
|
|
 |
|
諫早は千々石湾(橘湾)、有明海(諫早湾)、大村湾の三つの海に囲まれた地峡ですが、それゆえか、古代の官道(?)が通っていました。当時、長崎は取るも足らない場所であり、陸路を考えれば、重要なのは大宰府から西に進み、佐賀県の塩田(塩田町)を通り吉田(嬉野町吉田)あたりから山越えして長崎県の大村(大村市)に下り、諫早を通って島原付近(野鳥?)から海路、肥後(熊本)に向かうものでした(ただし、延喜式の時代にはこの海路は廃止されたと言われます)。
「肥前風土記」(肥前国風土記)は、一応、七一三(和銅六年)年の詔により奈良時代中期に成立したとされていますが(もちろん異論は存在します)、古代史家を中心に良く読まれているようですので、ここでは原文を省略します。
ただし、「肥前国風土記」には船越駅の記述は直接的には出てきません。このことについて、日野尚志 佐賀大学名誉教授が書かれた「肥前国の条里と古道」(「風土記の考古学⑤」肥前国風土記の巻 小田富士夫編 同成社)から引用させて頂きます。
律令時代になると駅伝制が整備された。肥前国における初期の駅制は明確ではない。『肥前国風土記』によれば、肥前国の駅路は小路で、養父郡を除く一〇郡に一八の駅家が置かれていた。そのうち具体的な駅名が判明するのは松浦郡の逢鹿・登望ニ駅にすぎない。『延喜式』によれば肥前国に一五駅あって『肥前国風土記』の総数と比較して三駅減少している。この三駅の減少は単に駅の廃止だけではなく、駅路の変更に伴う駅の減少である可能性が強く、奈良時代と『延喜式』時代では駅路が必ずしも同一でない可能性が強いことに留意すべきであろう。
対して、九二七年撰進、九六七年施行の「延喜式」(巻二十八 兵部省)には、ほんのわずかながら、他の駅と並んで、肥前國驛馬として「船越 傳馬五疋」の記述が出てきます(「延喜式」吉川弘文館)。 |
|
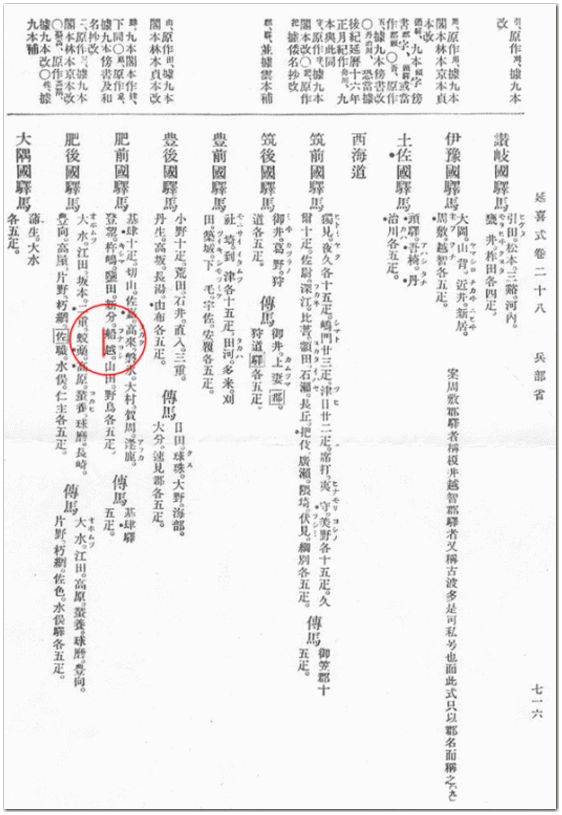 |
| 「延喜式」新訂増補国史体系第二部 10 ㈱吉川弘文館 |
|
| ただ、船越の場合は駅路変更の余地がない場所だけに、「肥前国風土記」が成立したと言われている時期に先行する七世紀、もしかしたら、五~六世紀にも一定の政治権力によって烽火や駅が整備されていたのではないかと考えています。 |
|
| 諫早の船越、小船越 |
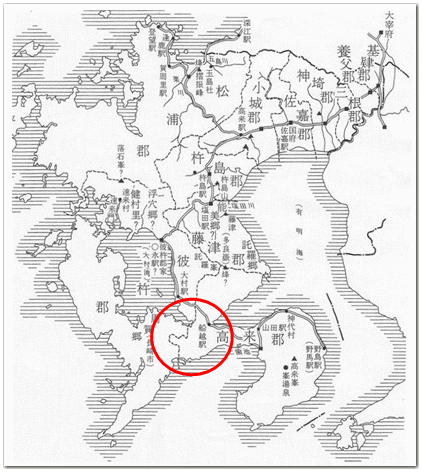 |
| 「風土記の考古学⑤肥前国風土記の巻」小田富士雄編の巻頭地図です。 |
|
|
地図を見ていただければ直ぐに分かるのですが、船による移動が重要であった古代において、もしも、諫早の"船越"が事実であれば、大宰府から南に宝満川を下り有明海に出て、西に進み、さらに、諫早湾から船越を経由して大村湾から西に出て(大村湾には西海橋が架かる急潮の針尾瀬戸と小さく緩やかな早岐瀬戸の二箇所の海峡があります)対馬海流に乗れば、労することなく自然に朝鮮半島にたどり着くことができるのです。
最近、古代史界の一部では、朝鮮半島へのルートとして、下手すればロシアのウラジオストック方面に流されかねない博多や唐津(唐津の唐は遣唐使の唐ではなく、任那=加羅、金官伽耶、高霊伽耶なのでしょうが)よりも、むしろ有明海ルートの方が合理的ではなかったかということが言われ始めているようです。
仮に、有明海湾奥部から北に向かうとしても、島原半島を大迂回するよりは、諫早の船越経由による大村湾コースが極めて有利であることは言うまでもないでしょう。
博多湾、唐津湾から朝鮮半島に向かうとしても、一旦は西に向かい対馬海流に乗ったと言われていますので、荒れる玄界灘を直行したり、弱風で西に進むよりは、有明海、大村湾を西に進む方が遥かに安全だったはずなのです。
これまでにも繰り返し述べてきたことですが、今でも、有明海は非常に大きな潮汐を見せる海です。ギロチンが行なわれるまでは、上下で六メートルと言われていましたので、干拓が行なわれていなかった古代においては、浅い海が広がり、多くの島や半島が入り組んだ複雑な地形をしていたはずですので、潮汐は今よりももっともっと大きかったはずなのです(奥行が深く海が浅いほど振幅は増大するとされています)。
現在でも諫早は低い平地ですが、実際に"船越"が行なわれていた時代には、その距離は今の地形から想像する以上に短かったのではないかと思います。
諫早地峡の東側には本明川と半造川が諫早湾に向かって流れています。また、西側には東大川が大村湾に向かって流れています。この間が約一キロですから、ここさえ"船越"すれば良いことになるのです。記述にもあるとおり駅に馬が置いてあったのですから、この外にも馬はいたはずですし(島原半島の口之津、早崎半島に"牧"があったと言われています)、馬に曳かせるなどして、船を運ぶことは思うほど大変なことではないでしょう。小さい船であれば数人で曳けたでしょうし、大きな船でも極力、川を利用し、時としてパナマ地峡のように川を堰き止め水位を上げるなどしてその牽引距離をさらに縮めたはずなのです。
逆に言えば、そのような重要な場所であったからこそ、古代の駅が置かれていたのです。
いずれにせよ、ほとんど遮るものがなかった古代において、船を曳くということは普通に行なわれていたと考えられ、もしかしたら、ある程度組織化されていたのではないかとまで考えています。
また、民俗学の世界には"西船東馬"という言葉があります。これは中国の軍団の移動や物資輸送が"南船北馬"と表現されたことにヒントを得たものでしょうが、確かに西は船による輸送が主力でした。また、"東の神輿、西の山車"という言葉もあります。これは、それほど明瞭ではないのですが、東には比較的神輿が多く、西には山車が多いというほどの意味です。
非常に大雑把な話をすれば、全国の船越地名の分布と、祭りで山車(ダンジリ、ヤマ)を使う地域がかなり重なることから、もしかしたら、祭りの山車は、車の付いた台車で"船越"を行なっていた時代からの伝承ではないかとまで想像の冒険をしてしまいます。
直接には長崎(長崎市)に船越地名は見出せませんが、ここの"精霊流し"もそのなごりのように思えてくるのです(長崎の精霊船は舟形の山車であり底に車が付いており道路を曳き回しますね)。
少なくとも、諫早の船越地名は非常に古く、潮汐は今よりも大きかったはずですから、太古、大村湾と諫早湾の間において船で"陸行していた"という推定は十分に可能ではないかと思うのです。
さらに、地質学的な調査、例えば海成粘土の分布といった資料があるのならば、"船越"のルートを特定し、地峡の幅、従って"船越"が行なわれた距離(延長)もある程度推定することができますので、今後の課題にしたいと思います。 |
|
| 大王の石棺実験航海と諫早の船越 |
|
一方、読売がプロデュースしてひところ話題になった「大王の石棺実験航海」においても、諫早の「船越」(延喜式に登場する「船越」の駅=ウマヤ経由の一部陸路利用)が利用され運ばれたのではないかと考えています。この有明海~諫早=船越~大村湾というルートがリアリティーを持つのは、海が安定する夏場でも、南、西風が卓越する長崎南、西岸は通りたくない上に、当時の島原から長崎、長崎から佐世保にかけての長崎南、西海岸には人口の集積がなく寄港地としての兵站が全く望めないからです。さらに言えば、搬送は王権の示威を兼ねていたと考えられ、数艘の随行船を従えて国家的事業として取り組まれたはずであり、当時の人口集積地である諫早から大村湾に抜け、彼杵付近を中継して平戸の瀬戸を目指したと考えるのです。長崎県は現在でも長崎市と佐世保市に人口が集積しています。その理由は江戸以来の外国貿易の独占と明治以来の三菱長崎造船所と佐世保の海軍工廠の存在によるものでしかないのであり、小なりと言えども、長崎における弥生以来の稲作の集積は諫早から佐世保に抜ける大村、川棚の一帯に認められるからです。
筑後の「船越」という話がいつしか大風呂敷に広がり、有明海と大村湾との往来、さらには、有明海湾奥部から畿内、朝鮮半島、大陸へと延びる話にまで発展しましたが、最後に山車でもある博多山笠にも振っておきます。恐らく、これも古代の船越のなごりではないかと考えています。これは、太宰府がその権勢を失い、観世音寺を含む多くの建物が解体され筏として組まれ畿内に運ばれたとする『法隆寺は移設された』米田良三氏ほかの仮説の物質的基盤を船越の延長としての山車に求めたいのです。
一方、石垣島の船越(フナグヤ)と奄美大島宇検村の船越(未踏査)の存在を考える時、船越地名が北上したのかそれとも南下したのかという問題にも行き当ります。以前は、柳田国男の『海上の道』の影響からか「船越」北上説に魅力を感じていましたが、呼称の問題からやはり、揚子江下流から五島列島経由で入ってきた海人族の南下と北上によるものとの思いを強くするこの頃です。これについては、石垣島の「船超」(フナグヤ)の現地踏査のリポートと併せ別稿とさせて頂きます。 |
|
 |
| ▲ 玉取崎展望台から望む=石垣島本島が北東に伸びているが船越はその最狭隘部 |
|
|
以前は鹿児島県にはないとしていましたが、その後奄美にあることを知りました。写真は、さらに最果ての石垣島、沖縄県の「船越」です。
その船越が、半島が伸びる付け根の伊原間(イバルマ)地区の最狭隘部にあったのです。このような小さな地名はやはりフィールド・ワークでなければ発見できません。ここの船越には西側に港があり、さらに水路が百メートルは東に伸びていますので、実際に「船越」をする距離は百~二百メートルで済みそうです(高低差数メートル)。当然ながら痕跡があると思い周辺を少し探すと、明らかに「船越」を行っていたと思える通路が真っ直ぐ東側の海に延びていたのです。
このフナクヤを利用すれば、どう見ても、二五キロは節約できるでしょう。 |
|
 |
| ▲ 石垣島伊原間の船越 |
|
|
| 船 越(補稿) 対馬 阿麻氏*留神社の小船越 |
|
| * 阿麻氏留(アマテル)の氏*は氏の下に一 |
| はじめに |
七月上旬、三泊四日で対馬を散策してきました。と、言っても全体で四二〇キロの行程にもなるため、かなりハードなものであったことは言うまでもありません。
もちろん、対馬には"船 越"でとりあげた、あの阿麻氏*留(アマテル)神社があります。
当然ながら司馬遼太郎の「街道をゆく」13(壱岐・対馬の道)には海人神社(ワダツミ)の社家でもある地元の郷土史家(というよりも第一級の民俗学者、古代史家と呼ぶべきでしょうが)の永留久恵氏との探訪のエピソードが書きとめられています。また、民俗学者宮本常一による永遠のベストセラー「忘れられた日本人」に書きとめられた伊奈、志多留から佐護、佐須奈に向かう中山越えの話や、対馬の南端、豆酘(ツツ)の浅藻の梶田富五郎翁のエピソードがあります。 |
|
 |
| ▲ 阿麻氏*留(アマテル)神社 |
|
|
この島は、西日本を中心に走り回って来た私にとっても始めての土地であり、ある意味で私に残されたフロンティアという勝手な思い入れを持っていました。今回の対馬行は直接的には"船 越"を書いたことをきっかけにしたものですが、少なくとも自分の目で直に、万関、大船越の瀬戸、小船越の阿麻氏*留(アマテル)神社を見てみたい、梶田富五郎翁の話しに出てくる豆酘(ツツ)の多久頭魂(タクツダマ)神社と天道法師の禁断の聖地(シゲ地)を見たい。もちろん景勝地である和多都美(ワタツミ)神社も見たい、などと、多くの思いが重なる非常に欲張ったものでした。もちろん、神社だけを見たわけではありませんが、都合、二〇社あまりを見て周り第一回目の対馬行を終えたのです。
対馬の神社になぜこれほど思い入れがあるかというと、どうやら日本の神々の支配的ルーツがここにあるようだからです。前述の永留久恵氏による「海神と天神」の冒頭 3 対馬の神々 には、こうあります。
西海道の延喜式内社一〇七座中、二九座が対馬にある。上県郡の和多(わた)都美(つみ)神社(名神大社)以下一六座、下県郡の高御魂(たかみむすび)神社(名神大社)以下一三社で、次は壱岐に二四座、続いて筑前に一九座があり、西海道の官社の大半が玄海に臨んでいたことになる。大和朝廷がこの海域をいかに重視していたかが窺える。 |
|
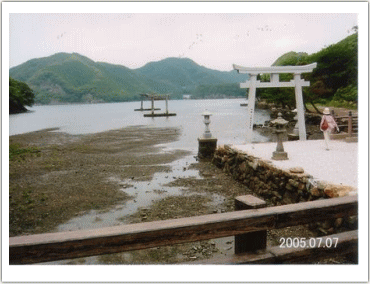 |
| ▲ 和多都美神社 |
|
|
船越は実在した
しかし、最大の関心は、阿麻氏*留(アマテル)神社の小船越が本当に"船越"できるような場所であるかを実際に現地を歩いて確認することにありました。 |
|
 |
| ▲ 小船越の港 |
|
|
| 道路改修工事や漁港修築事業などによって現地はかなり変えられ、神社の参道(石段)も、神社前にあったと思われる水路(きっとこれも海からの参道だったのでしょうが)もかなり付け替えられてはいるようですが、昔の地形は十分に想像することが可能でした。 |
|
 |
| ▲ 神社前の水路 |
|
|
| 結論を先にすれば、結果は実に感動的なものでした。なんと、阿麻氏*留神社のすぐ裏には(というよりも神社の前を左に船越すればその先にあるのですが)静かな入江がすぐそこまで延びていたではありませんか。 |
|
 |
| ▲ 阿麻氏*留(アマテル)神社裏の入り江 |
|
|
| この存在感は古田史学に魅了されている私だけのものかもしれませんが、うっとりするばかりのこの入江の美しさは、私ならずとも感じていただけるものと思います。一方、対馬の東側にあたる神社の表には参道の直前まで水路が延びており、距離にして一〇〇~二〇〇メートル、高低差五メートル足らずの小さな坂を越えるだけで、労することなく船越ができるように見えるのです。 |
|
 |
| ▲ 入り江から船越を望む |
|
|
勝手な想像ですが、まず、積荷を陸揚げして"船越"し、荷を運び再び積み直す。当然ながら、阿麻氏*留神社に対して通行料を納め、人手が足りないときには同社の氏子連に協力を求めて何がしかの労賃を支払うなど、この小船越にはそれなりに組織化され、ある意味で産業化された"船越"が存在していたのかもしれません。
前述の永留久恵氏には「古代史の鍵・対馬」「海神と天神」「古代日本と対馬」をはじめ多くの貴重な著書があります。今回、私はこのうち、四百数十頁の大著「海神と天神」(1988)を手に対馬を周ったのですが、フィールド・ワークによって多少とも得ることができた"か細い"イメージに、この本が吸い込まれるように入ってきます。それはともかくも、「古代史の鍵・対馬」(1975)にも「船越」という小稿があります。永留氏は、この中で、"対馬には大船越と小船越があるが、実際に船越をしていたのは小船越だけではなかったか"とされています。詳しくは本著にあたられるとして、一部をご紹介します。
浅海湾から東の海に通ずる要地として、二つの船越があった。大船越と小船越である。もう一つ鶏地の住吉があったが、ここには船越の地名はない。いまは大小となく万関の瀬戸を通行するようになったが、これは明治三三年に、帝国海軍が…中略…
それならば、古来海外に渡航した人たちは、大船越を利用したはずなのに、ここにはそのような伝承がない。…中略…
いまの大船越の部落は、江戸時代の初期に移住して来た、と里の人たちも伝えている。これに対して小船越は…応永二六年(一四一九)、朝鮮軍が浅海湾を急襲してきたとき、まず尾崎を焼き、ついで船越を攻め、さらに仁位を襲っている。これらの浦が特に狙い討たれたのは、そこが重要な拠点であったからにちがいない。『大宗実録』には訓乃串と書かれている。また、『海東諸国記』には訓羅串となっている。訓乃串、訓羅串、これが船越に当てた朝鮮語の表記だが、ここでわかることは、小船越ではないということだ。船越に大小はなく、ただ、船越があったのだ。そこで寛文の掘切ができて、大きな船が運行できるようになってから、大船越ができたのかといえばそうでもない。『海東諸国記』に吾甫羅仇時とある。それにしても小船越は、まさに古船越とよぶべきであった。
と。
そして
その外にも、豆酘(ツツ)の浅藻の梶田富五郎翁の話しに出てくる郵便局や梶田翁の家も控えめを心がけながら眼に焼きつけてくることができました。これは、これまでの熱い思いをとりあえず沈めるものでした。
さて、対馬は確かに豊かな自然が残る島でした、しかし、だからこそかえって破壊的な道路工事や河川工事が目に付き、それに追い討ちをかけるように、多くの照葉樹の森が役にも立たない針葉樹に変えられ続けていることが痛々しく感じられたものです。このままでは間違いなく対馬ヤマネコは絶滅することになるでしょう。 |
|
| 船越の新たな展開と収束 |
船 越 で以下の様に書きました。
民俗学の世界には"西船東馬"という言葉があります。これは中国の軍団の移動や物資輸送が"南船北馬"と表現されたことにヒントを得たものでしょうが、確かに西は船による輸送が主力でした。また、"東の神輿、西の山車"という言葉もあります。これは、それほど明瞭ではないのですが、東には比較的神輿が多く、西には山車が多いというほどの意味です。
非常に大雑把な話をすれば、全国の船越地名の分布と、祭りで山車(ダンジリ、ヤマ)を使う地域がかなり重なることから、もしかしたら、祭りの山車は、車の付いた台車で"船越"を行なっていた時代からの伝承ではないかとまで想像の冒険をしてしまいます。
直接には長崎(長崎市)に船越地名は見出せませんが、ここの"精霊流し"もそのなごりのように思えてくるのです(長崎の精霊船は舟形の山車であり底に車が付いており道路を曳き回しますね)。
七月は山笠、山鉾、山車の季節ですが、私が参加している古田史学会の内部では上記の内容がささやかながら新たな展開を見せています。
同会のホーム・ページ「新・古代学の扉」には「古賀事務局長の洛中洛外日記」という、大変面白い、興味深いコラムがありますが、その第七話、第十一話に"船越"の話しが出ていますのでその一部を紹介させていただきます。
第7話 「祇園祭と船越」
…この祇園祭の山鉾ですが、その淵源は古代まで遡るのではないか。山鉾や博多山笠の「山」は耶馬壹国のヤマと何か関係はないか、と以前から思っていたのですが、山鉾は古代の「船越」の様子を表現したものとする説が、最近出されました。
ホーム・ページ「有明海・諫早(ママ)干拓リポート」に掲載された古川清久さんの論文「船越」に次のように述べられています。
「全国の船越地名の分布と、祭りで山車(ダンジリ、ヤマ)を使う地域がかなり重なることから、もしかしたら、祭りの山車は、車の付いた台車で"船越"を行なっていた時代からの伝承ではないか」…中略…
そう言えば、松本市の須々岐神社のお祭り、「お船祭り」では「お船」と呼ばれる山車が繰り出されますが、これなど「船越」そのもの。古川さんの新説は以外と正解かもしれませんね。
第11話 「信州のお祭・お船」
…信州のお祭りで有名なものに、穂高神社(南安曇郡穂高町)のお船祭がありますが、安曇という名前からも想像できるように、海人(あま)族のお祭ですからお船と呼ばれる山車が登場するは(ママ)、よく理解できるのです。しかし、諏訪大社の御柱祭にまで主役ではないようですがお船が登場することに、その由緒が単純なものではないなと感じたわけです。
祇園山鉾や博多山笠の山車が、古代の船越に淵源するのではないかという古川さんの説を洛中洛外日記第7話で紹介しましたが、今回の調査の際、『隋書』倭国伝(原文はイ妥)の次ぎの記事の存在に気づき、新たな仮説を考えました。
『隋書』には倭国の葬儀の風習として次のように記録しています。
「葬に及んで屍を船上に置き、陸地之を牽くに、或いは小輿*(よ)を以てす。」
小輿*[輿/車](よ)は、輿の同字で輿の下に車。
倭国では葬儀で死者を運ぶのに陸地でも船を使用していたことが記されているのです。そうすると、山車の淵源は海人族の葬儀風習にあったと考えてもよいのではないでしょうか。祇園山鉾や博多山笠の「ヤマ」が古代の邪馬台国(『三国志』原文は邪馬壹国)と関係するのではないかという、わたしのカンも当たっているかもしれませんね。
最後に永留久恵氏の「海神と天神」の 第一部 海神編 第二章 対馬のウツロ舟伝説 10 葬送と舟 にこの話の解答に近いものがありますので、少し長くなりますが、その一部をも紹介してこの論考をひとまず終わりにしたいと思います。しかし、再び対馬を訪ねることになると思います。その時には再び、船
越(補稿)②を書きたいと思います。
…中国の史書「隋書」倭国伝を見ると、倭人の風俗を述べたなかに、「貴人三年殯於外、庶人卜日而葬」との記述があり、貴族は殯宮を建てて長期間 もごり をしたことがわかる。庶民は卜して葬(はふり)をしたが、その間にはやはり殯の仮屋をこしらえたはずである。
しかし、屍を安置する施設をもたないものは風葬に近い形がとられたであろう、と井上氏は説く。そして『続日本紀』文武天皇の七〇六年に、放置された屍を埋葬するよう令した詔が引用されている。
水葬について諸先学は、蛭子を舟に載せて流したという『記』『紀』の神話は水葬の習俗を映したものだと説いている。南方の海洋民族の間には、死者は船に乗って他界するという説話があり、死者を舟に載せて流す風習があったという。この南海の民族と、いろいろの点で似た習性をもっていた倭の水人に、水葬があったと考えることは無理ではない。志摩で棺をフネとよぶことには、遠い昔のある姿を想像して深い意味を感じる。志摩は、熊野へと続く海人の活動舞台だったからである。また、海辺の村で初盆に精霊船を流すのは、死者の霊が遠い海の彼方に帰るという信仰による。
葬(はふり)と舟について考えるとき、死者を載せて流すことばかりにこだわってはいけない。屍を葬地に運ぶためには船が必要だったからである。これを思うのは縄文晩期に始まる対馬の古い埋葬遺跡がほとんど海岸にあり、海に臨んだ突崎や、離れた小島にあるからだ。南西諸島では、今でもそのような場所に葬地を営んでいる。この葬地まで運ぶためには、当然舟を必要としたはずである。陸路から行けるところもあるが、舟による方が便利であり、また、舟なくしては不可能な場所が多い。死者を葬地に送るために、舟に乗せて運んだことは間違いない。
さきに引用した『隋書』のなかに、「及葬置屍船上牽之」と、屍を船上に載せて葬地に運ぶことが記されているが、この場合は水上を航行するのではなく、陸上を牽(ひ)いたのである。およそ推古朝頃の風俗を記したものであろうが、船と棺との区別がわからない。しかし、これについて上井氏が攝津の住吉大社の資料から分析した論考は明快である。その概要は、同社に深い関係を持っていた舟木氏があり、この舟木は舟の建造を職掌としたが、同時に棺をも造った。しかも木棺ばかりではなく、石棺をも作っていた。そこで『古事記』にいう「鳥之石楠舟」には舟と棺のイメージが混然としている。というものである。… |
|
| 武雄市 古川 清久 |