 |
|
�@�i��Ă̋�B�ꕶ�E�퐶�̓y��j |
|
|
�L�����j�̉�@�剺���i�@�i�Óc�j�w�̉�j |
|
|
|
|
|
|
| �P�D�͂��߂� |
|
| �ߔN�ADNA�̉�͋Z�p������I�ɐi�݁A���݂̐l�ނ̑c��͂Q�O���N���O�ɃA�t���J�Ő��܂�A�U�`�V���N�O�ɐ��E�e�n�ɗ�����,�A�W�A�ւ͖�S���N�O�ɂ���ė������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B����ɂQ���N�O���납�瓖���������ł������x�[�����O�C�����z���ăA�����J�嗤�֓n���Ă��܂��B�P���N�O�ɂ͑����m��D�œn�����O���[�v���o�Ă��܂����B |
�����̎j���ɂ́A��m�̂��Ȃ��ɂ���`�l�̍��̂��Ƃ�������Ă��܂��B�����đ����m�̌��������A��ẴG�N�A�h���ł́A���{�̓ꕶ�E�퐶�y�킪�o�y���Ă��܂��B
�Ñ�̐l�X�͉�X�̑z�����͂邩�ɉz�����_�C�i�~�b�N�ȓ������s���Ă����悤�ł��B |
|
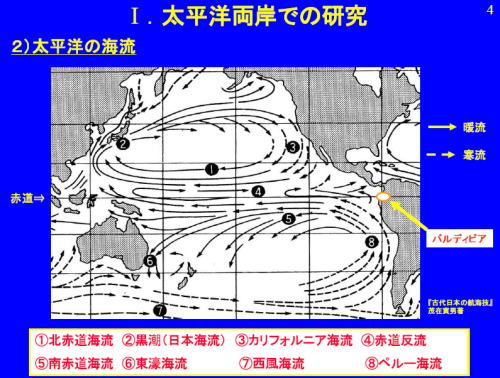 |
|
| �i�}�F�w�Ñ���{�̍q�C�p�x���w�فA�ݓВj���j |
|
| �Q�D�����j���ɕ`���ꂽ��Ă̘`�l�̍� |
|
| �C�j |
�O���u�E鰎u�`�l�`�i�R���I�㔼�ɋL�q�j |
|
| �E |
�ږ�ĂŗL���Ȃ��̖{�ɂ͎הn�䍑�����łȂ������́g�`�l�̍����h���L�ڂ���Ă��܂��B���̍Ō�̂Ƃ��낪�u�`���̓���̕����A�D�s��N�ɂ��āg�����E�������h�Ɏ���v�ł��B
���{�̓���̕����A�����̍s��������͓�ẴG�N�A�h���A�y���[�̉��݂ł��B |
|
| ���j |
�㊿���E�`�`�i�S���I�O���j |
|
| �E |
���̎j���ɂ́g���`�z�����h�̋���̂��Ƃ��u����������N�E�E�A�`����E���ɂ߂�B�����A�����Ɉ�����ȂĂ��v�g�`������E���ɂ߂����߂ɋ����^�����h�Ə�����Ă��܂��B�����āA�`�`�̖����ɂ͓�E�̂��Ƃ��u����A�D���s�邱�ƈ�N�g�����E�������h�Ɏ���B�g�w�i�g�ҁj�̓`���鏊�����ɋɂ܂�v�Ƃ̐���������Ă��܂��B�`��������Ă̂��Ƃ�������ɕ������߂ɋ��^����ꂽ���̂ł��B
�i�o�T�F�w�u�הn�䍑�v�͂Ȃ������x�Óc���F�B�Q�O�P�O�N�A�~�l�����@���[�B���j |
|
|
|
| �R�D�ꕶ�E�퐶�̍��̃G�N�A�h���E�R�����r�A |
|
| ����Ă̌Ñ㕶���Ƃ����A�}���E�C���J�E�A�Y�e�J�Ȃǂ��v�������т܂����A����ȑO�͓�đ嗤�̖k���A���̃G�N�A�h���E�R�����r�A�̑����m�݂ɌÑ㕶�����h���Ă��܂����B |
|
 |
|
| �C�j |
�G�N�A�h���̓ꕶ�����@ |
|
| �E |
������U��N�O�̃G�N�A�h���A���݂̃O�A���L���s�߂��̑����m�݂ɂ���o���f�B�r�A�ɓꕶ���l�����������x�ȓy�핶�����˔@�o�����܂����B���̕����͖�Q��N�ԑ����Ă��܂��B�ނ�͍q�C�̖��ŁA�D�ꂽ�q�C�Z�p�������A�k�̓��L�V�R�A��̓y���[�E�`���A�����ē��̓A���f�X���z���ăA�}�]���n��Ƃ̌��Ղ��s���Ă��܂����B |
| �E |
�Ñ�ɂ����āA�G�N�A�h�����ӂ̒n��͒���Ă̌�ʏ\���H�̒��S�Ƃ��ĉh���Ă����ƍl�����Ă��܂��B |
|
| �]�����y�� |
�o���f�B�r�A�y�� |
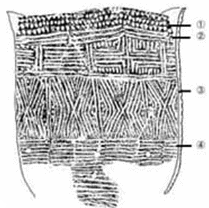 |
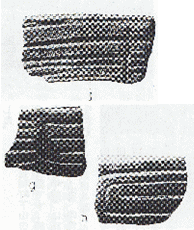 |
| �U��N�O�A�]�����y�킪��q���A����Ɋg�����Ă��܂��B�������A��ăG�N�A�h���̑����m�݂œ˔@���x�ȓꕶ���l���������y�킪�o�����܂����B�����̍s��������ł��B |
|
|
|
|
|
| �E |
�P�X�U�O�N��ɍl�Êw�҂ł��������O�A���L���s���G�~���I�E�G�X�g���_���ƃA�����J�̃X�~�\�j�A�������ق̍l�Êw�ҁA�G�o���Y�E���K�[�Y�v�Ȃ��A�o���f�B�r�A����o�y�����y�킪 |
|
| �@ |
�ꕶ�O���̋�B�̓y��Ɠ������l�������Ă��邱�� |
| �A |
�ގ���������Z�@�ō���Ă��邱�� |
| �B |
�����`���鍕���Ƃ�����ʎ�i�����邱�� |
| �C |
����܂ŃA�����J�嗤�ɂ͍��x�ȓy�핶�������݂��Ă��Ȃ��������� |
|
|
����u�ꕶ�y��̓�Ăւ̓`�d�E�Ñ�̑����m�ɂ����镶���̌𗬁v�Ƃ����e�[�}����܂����B |
|
|
|
 |
|
|
|
| ���j |
�G�N�A�h���̖퐶���� |
|
| �E |
�I���O�T���I����I���T���I����ɂ����āA�G�N�A�h���̖k���C�݃��E�g���^�n�悩��R�����r�A�암�̑����m�݂ɂ����ĉ����������h���Ă��܂����B鰎u�`�l�`�̎���ł��B |
| �E |
�����ł́A�퐶����ɖk����B�ő�ʂɍ���Ă��������p�̑�^�P�i�P���j�Ɠ����`�������P�������������Ɏg���Ă��܂����B�����͂�������P.�T���قǂł��B |
|
|
|
| ��B�E�g�샖���o�y���P�� |
|
���E�g���^�n��o�y���P�� |
 |
|
 |
|
|
|
|
| �n�j |
�R�����r�A�̓ꕶ�y��@�@�i�a.���K�[�Y�_�����j |
|
| �E |
�J���u�C���ɂ���T���n�V���g��Ղ���A�ꕶ���㒆���i�S�`�T��N�O�j�ɒ������{�Ő���ɍ���Ă����Ή��������̓y�킪�o�y���Ă��܂��B |
| �E |
�o���f�B�r�A����J���u�C���̃T���n�V���g�ւ̓R�����r�A�̑����m�݂𗬂��T���t�A��������ǂ��Ă䂭���Ƃ��ł��܂��B���̗���ɏZ�ރm�A�i�}����HTLV-�P�^�̃L�����A�[���������܂��B�`�l��������ʂ�J���u�C���ֈړ����Ă����\�����l�����܂��B |
|
�iHTLV-�P�F��B�E����Ȃǂ̐�����{�ɑ����E�B���X�ŁA�A�����J�嗤�ł̓A���f�X�̎R���ɂ����������Ă��܂��j |
|
|
|
��đ嗤���k�������m�� |
|
|
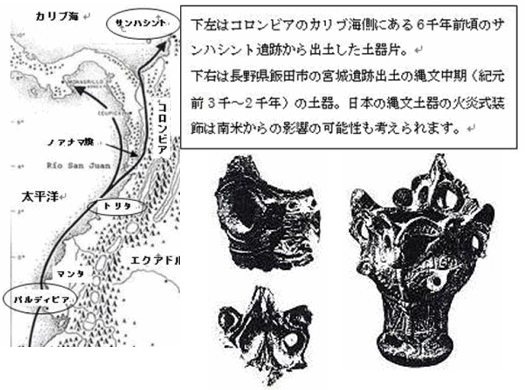 |
| �S�D���̑���Ă̓��{��n���Ȃ� |
|
| �E |
�o���f�B�r�A�̖k�Ƀ}���^�Ƃ����傫�Ȓ�������܂��B���̖��O�͋��̃}���^�i�G�C�j����R�����Ă���Ǝv���܂�������ł̓G�C�̂��Ƃ��J�}���^�ƌĂ�ł��܂��B�@�i�Ð쐴�v�j |
| �E |
���̖k�̊C�݂ɂ��鑺���n�}�ƌĂ�Ă��܂��B�C���f�B�I�̌Â�����̒n���ł��B |
| �E |
����ł͍ŋ߂܂Ō��ꕶ�����g���Ă��܂����B�������ꕶ�����T��N�O�̌Ñ�y���[�̈�Ղ�����������Ă��܂��B |
|
|
���̑��c�m�`�̗ގ��ȂǁA�����̕���ŌÑ�̑����m�̌𗬂��������Ղ��������Ă��܂��B
�o���f�B�r�A�ɂ͎����ق�����܂��B��Ă֗��s�ɏo�������鎞�͐���G�N�A�h���w�䂫�`�l�̑��Ղ����Ă��ĉ������B �@�@�@�@�@�@ �@�@ |
|
| (2013�N7��10���剺�L) |
| NPO�@�l�@�Ƃ�Ȃ��s�������l�b�g������ |
|
| �y�Q�l�����z |
|
| �P�j |
�w�u�הn�䍑�v�͂Ȃ������x�Óc���F���A�Q�O�P�O�N�A�~�l�����@���[�i�P�X�V�P�N�����V���Ђ̕����Łj |
| �Q�j |
�w�C�̌Ñ�j�x�Óc���F���A�P�X�X�U�N�A�����[ |
| �R�j |
�w�V�E�Ñ�w�x��S�W�A�V�E�Ñ�w�ҏW�ψ���ҁA�P�X�X�X�N�A�V��� |
|
�E�����̐i���Ɠ`�d�i�����m�����`�d���̏Љ�j�F�x�e�B�E���K�[�Y |
| �S�j |
�w�Ȃ������E�^���̗��j�w�x�l���A�Óc���F�ҁA�Q�O�O�W�N�A�~�l�����@���[ |
|
| �E |
��Ă̌Ñ�n���F�Óc���F�B�h�G�N�A�h���ɘ`�l���c��������́H�h�B |
| �E |
�G�N�A�h���ŕ��ꂽ���W�L���iEL UNIVERSO)�F�|��剺���i |
|
| �T�j |
�w�Ȃ������E�^���̗��j�w�x�܍��A�Óc���F�ҁA�Q�O�O�W�N�A�~�l�����@���[ |
|
| �E |
�����E�������̍��̓�āF�@�剺���i |
|
| �U�j |
�w�Ñ�ɐ^�������߂āx�\��W�A�Óc�j�w�̉�ҁA�Q�O�O�W�N�A���Ώ��X |
|
| �E |
�l�ނƓ��{�Ñ�j�̉^���F�@�Óc���F�u���^�B |
| �E |
�G�N�A�h���̑�^�P���@�F�@�剺���i�B |
|
|