|
|
| �ł���"�Ƃ���������"�̂Đ� |
|
�Ă̐����"�ł�������"�Ɩ��ł���"�Ă��Ɏ̂Đ�"�̃C�x���g���s���Ă��܂��B
�P�ӂōs���Ă�������𝈝��������ʂ�"��������"���Ƃ͖{�ӂł͂���܂��A��������Ƌ@�ցi���ȁA���y��ʏȁA���t�{����j���{�������Ă��͂��߂�ƂȂ�ƁA�ǂ��l���Ă�����̓����o���Ɠ����ɖ���̘I��Ƃ��������l������܂���B
����͈��ł� |
| �@ |
��s�s�̉������͑ł���������������܂��I�I�i���m�点�j
�����P�W�N�V���P�S�����₢���킹�恄
�s�s�E�n�搮���lj����������������ہi����34133�jTEL�F03�]5253-8111�i��\�j |
| ���y��ʏȂ̃z�[���E�y�[�W���� |
|
|
| �@ |
�@���̃L�����y�[��������Ă���̂��A��s�s�̒n�\����J���܂ł�D���A�q�[�g�E�A�C�����h���ۂ̌����҂ł��蒣�{�l�ł��葱���Ă��鍑�y��ʏȂ̕��}�ł��鉺���������������ۂƂ����̂ł�����A�u�ƍߕ��v�Ƃ��ĂȂ�����m�炸�A�����@���ւ̊�b�I�Ȓm���������̂��A�����B������Ă��邱�Ƃ̈Ӗ������������������Ă��Ȃ��̂��H�c�Ƃ����v���Ȃ��̂ł��B
�@�܂��Ă�A�u�n�����g���ɗ�[����߂đł����őR���悤�I�v�ȂǂƁA�}�X�R�~�܂ł��������܂�đ����n�߂��A�܂��͉Ȋw���̂Ȃ���Q������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
���ɁA�u�b�n�Q���g���_�v���S���̃f�}�ł��������Ƃ��A�N���C�����[�g�E�Q�[�g�����ɂ��S���E�I�ɖ����ɂȂ��Ă��܂����A�p��m��Ȃ��̂��H�܂��A�M������ł���̂��H���̃L�����y�[���͌p������Ă��܂��B
�@����͂Ƃ������Ƃ��āA��Z��O�N�āA���m���]���41���A�R�����b�{40.7���A�R��������40.5���c�i���̏Z�ލ��ꌧ�ł��A�ߋ��A����s�ŎO��D�Z�x�Ƃ����L�^���������Ǝv���܂����j�A���܂���"�ł�������"��������Ƃ���ŁA���x��������͈̂ꕪ���炸�̏u�Ԃɉ߂����A��x���������ƌւ炵���Ȋ��Ȃ̏���l���A���̏ꗽ���̃p�t�H�[�}���X���I����ĉ��K�ȕ����ɖ߂�A��[�̉��x����܂œ�x�ȏ�͉��������Ȃ������ł��傤�B
�@���͂�唼�̐�����C�ɊC�ɗ�������A���܂����A�J���̈ꕔ�܂ł��������Œn���ɗ������ނ��Ƃɂ���Ēn�\���琅��D���Ă����Ȃ���A���x�㏸�́u�n�����g���̂��߂ł͂Ȃ����H�v�ȂǂƂƂڂ����b�����Ă���̂ł��B
�@���̎��Ԃ������Ȃ��قǂɔj�ꂽ�s�s�̐��z�ƁA���̔w�i�ɂ���Ȋw���̑r���ɂ͂��狰�낵��������������̂ł��B
�@"�ł�������"�ɂ��ẮA�܂��͑���Ƃ����Ƃ���ł����A���͏��Ă�����قǎ��Ԃ͊y�ςł��Ȃ��̂ł��B
�@���������A����قǂ܂łɓs�s�̕\�ʉ��x���㏸�������̔w�i�ɂ͓s�s�̊�����������̂ł��B
�����Ă��̕ې��͂����킹�s�s�̍������𑣐i�������̂����A���H��ܑ����s�����A���[���H�����^�͐�Ɏ���܂ŁA�܂��A�͐�Ǘ����H��������Ɏ���܂ŁA�O�ʒ����a��R���N���[�g�A�A�X�t�@���g�ŕ����Ă������y��ʏȂł������̂ł��B
�������A����قǂ܂łɕs�K�v�ȃ_���𗐔������ɂ�������炸�A�s�s�^�������������ނ��Ƃ������ł����ɁA���Ȃ��炻�̊O�s�c�̂�"�ł�������"�Ƃ��ł���������Ɏ����A�܂��A����̉ʂĂɁA"�����Đ������u�ł����v�p���Ƃ��Ďs���ɖ����Œ���"�Ƃ����̂ł�����A���͂�A���m�̗����A���̒��ŋQ��ɂ���đ����̖����o�^�o�^�Ɠ|��Ă������ɁA"�\"��"�a��"���ƕ����Ă����������R�Ƃ̂��Ƃ��D�낳�Ɗ����������ł��B
�������Ă���Ԃɂ��A��s�s�̕Ћ��ł́A�G�A�R�����g�����ɔM���ǂő����̖����|��Ă���̂ł��B
�@���ɂ́A�ł����͊��Ȃ��獑�y��ʏȂ̊����ǂ��̊�ɂ����Ђ��|����ׂ��ł���A�M�d�Ȑ��̑ł��̂Ă͒f���Ă�߂�ׂ��i�Đɐ��j�A�ł����ɑ�ʂ̗\�Z������邮�炢�Ȃ�A�R���N���[�g�������������I�ł������͒��萅���I�����Ɩ{���I�ȑ�����I�Ƃ��������悤���Ȃ��̂ł��B |
| �@ |
| �n�����g���ƃq�[�g�E�A�C�����h |
| �@ |
�@���āA"�b�n�Q�n�����g�����͌��q�͎Y�Ƃ��痬���ꂽ�����ȃf�}���I"�Ƃ������b�́A�u���g���͗J���ׂ����Ƃ��낤���v�g�b�n�Q�n�����g�����А��̋��\�h�i�s�m�Ώ��[�j�𐢂ɖ��ꂽ�ߓ��M�����ɂ܂�����Ƃ��āA�����"�ł���"����q�[�g�E�A�C�����h�Ɋւ���b���������Ǝv���܂��B
�����A���̑O�ɁA�����ɑ��݂��Ă��鉷�g���X���ƃq�[�g�E�A�C�����h���ۂƂ�����������K�v������ł��傤�B
�@�������A�v�ʓI�ȈӖ��ŁA�s���������Ă��錻���̋C���̏㏸�̒����炱���̗v�f�����鎖�͕s�\�ł��傤�B
���ꂩ�珑�����́A�����܂ł��o���Ɋ�Â����_�ł�������܂��A�ŋ߂̓s�s�̋C���㏸�͐q��ł͂���܂���B
���ہA���B���q���̍�����قǂ܂łɏ������h���Ǝv�������͂���܂���ł����B
�ȑO�ɂ����������Ƃł����A���w�Z����̉Ẳۑ�A"�u�Ă̗F�v"�Ƃ����������̂̓��L��ǂނƁA�u�����͓��.�ܓx���������������I�v�ȂǂƏ����Ă��܂��B
�܂��A���A������ʂ��ĎO�Z�x���z������͓�T�Ԃ��z���Ȃ������悤�Ɏv���܂����A�قځA�����[�����~��A�����ܓx�ȉ��ɂ͂Ȃ������߂ɁA�{���ɐQ�ꂵ�����͏\�����z���鎖�͂߂����ɂȂ������Ƃ����L���i��ہj�������Ă��܂��B
�������n������Z����̈Ⴂ�����T�Ɍ�����͂�������܂��A�\�Α�̕��܂łɂ͂�����x���ӂ��Ă���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���ꂪ�A�ŋ߂̂��̂���l�ł��B�m���ɑS�̂Ƃ��Ẳ��g���͎����ł��傤�i����͂������N�C�ے����F�߂�悤�ɒቺ���Ă��܂��j�B�����A��Ƃ��ēs�s���ɂ����ĉĂ̑ς������������ɂȂ����ׂ��Ȃ���]���A�唼�̐l�X��"�n�������g�����Ă���̂�����d�����Ȃ�"�ƍl���Ĕ[�����Ă��邱�Ƃ̑����̕��������ۂɂ̓q�[�g�E�A�C�����h���ۂɂ����̂ƍl���Ă��܂��B
�@�n�����g�����ۂƃq�[�g�E�A�C�����h���ۂƂ͈�؊W������܂���B
����͐l�ԁi��Ƃ��čs���j���l�דI�Ɏ��R�Ɏ�������āi�s�s�����c�Ȏ��R�ƍl����ł����j���z��ύX�������Ƃ���Ǐ��I�ɔ����������x�㏸�ł����Ȃ��A�n���S�̂̕��ϋC���A���ω��x�̏㏸�Ƃ͑S���W���Ȃ��̂ł��B
�@���Ȃ��Ƃ��A�s�s������قǂ܂łɃR���N���[�g�œh��ł߂������A����قǂ܂łɐ��H���������Ȃ������Ȃ�A�܂��A���݂��͒n��̐����͕ۂ���[�������������A�Ă̏����ɑς���ꂸ�ɓ|���l�X�͏o�Ȃ��������Ƃł��傤�B
�@�q�X�e���b�N�Ȃ܂ł�"�b�n�Q�n�����g����"�̖����̔w�i�ɂ́A�n�����g���Ƃ͑S���W�̂Ȃ��A�s����擪�Ƃ����Ԃ��܂߂��s�s�̃R���N���[�g���A�������ƁA��ʏZ��n�ɂ�����R���N���[�g������u��������A����ɂ́A���z����������Ȃ��A�a�������������Ȃ��A�}�ł����������Ȃ��A�܂��A������ł��Ȃ������Ă���s�s�Z������]�T��D�������㎑�{��`�Љ�̍\���ɂ���Ē�グ���ꂽ"�q�[�g�E�A�C�����h����"���w��ɑ��݂��Ă��邱�Ƃ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@�����ɁA�s�s�Z���̐����ɐM����܂ł̉Ă̏������������s������̖������u��"�ł�������"��"�n�����g���_"�ł��܂��������ɋ����ׂ��ł͂Ȃ��̂ł��B |
| �@ |
| �q�[�g�E�A�C�����h���ۂ̕����I��b |
| �@ |
| �@�@�n���ւ̎̂Đ� |
�@�܂��A��s�s�̊������̌����̈���������A�㐅���̊����A�㉺����n���Ɏ��������ɂ���ƍl�����܂��B
�ς����Ȃ��܂ł̃q�[�g�E�A�C�����h�����A�������\�N�O���甭�����Ă��鎖���l����A�㐅���̐����܂ł�G������K�v�͂Ȃ������ɁA���܂���䒃�m���ȗ��i���R�̂����p�ɗ��p���ꂽ�N�����]�ˏ�ɋ����j�̏㐅�ɂ܂ň����߂����͕s�\�ł�����A��ʓI�ɂ͏㐅��藣���ċc�_���ׂ���������܂���B
�����A�����͂������Ƃ����F�������͎����Ă����ׂ��ł��傤�B
�@���݁A�������ɂ͉J�������̍��������ƁA�J���Ɖ�����ʁX�̊ǘH�ŗ�����������������܂����A�����A���Ȃǂ̑�s�s�ł͂قڕS�p�[�Z���g�̕��y���ɂȂ��Ă��܂��B
�@�������A�����P���ɕ����s�s�ƍl����l�X�͕����̈�ʂ������Ă��Ȃ����Ƃɂ����Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@�Œ�ł������G�r�����������ɗ�������ɁA�B��̉J���܂ł��������ɗ������݁A���z�A���x�z��O��I�ɔj��悤�Ȃ��Ƃ�����Ă��Ă͓s�s�̃q�[�g�E�A�C�����h���������~�߂邱�ƂȂǎn�߂���ł��Ȃ��̂ł��B |
| �@ |
| �b�x��@�@�g�y��ڎw�����l�ԁh |
| �@ |
���������A�s�s�̃q�[�g�E�A�C�����h���Ȃǂ͎��������Ƃ͖��W�ł���A����������~�߂邱�Ƃ����y��ʏȂ̔C���Ƃ͍l���Ă��Ȃ��i����́A�ł��������^��ł���Ă��邱�ƂɔF�����Ȃ����Ƃ��ؖ����Ă���A�����A�����łȂ���A�p���������āA�l�C��肾���̂��Ղ葛���Ȃǂ��Ȃ�����ŁA�ނ�̒ʐ����炵�āA�����A�Ђ��B���ɂ��Ă����͂��Ȃ̂ł��j���Ƃ�����̂ł����A�����������q�[�g�E�A�C�����h���̍ő匴���ҁ����Q�҂ɂȂ��Ă���Ƃ����������Ȃ����Ƃ��ő�̖��Ȃ̂ł��B
�u���X�A�y�����l�Ԃ͐��т������A�����≻�w��������Ȃ��A���������v�ƁA���̐e���ȓ��呲�̗F�l�������Ă��܂������A�u��قǂ̔n�����A�R�����������y��ʏȂŏo���ł���̂��I�v�ƌ������̂����̗F�l�ł����B
��͂�A�́A���R�A���A���y��ʏȁA�ł����ˁH |
| �@ |
| �A�@�s�s�͐�̉J�� |
�@��s�s�̓����d���������̑唼���㐅���Ŏ������܂�A�Ăщ������Œn������n���ւƉ^�ы����Ă��邱�Ƃɑ��āA������̐��z�̗v�f�Ƃ��ẲJ���ɂ��āA�s�s�͐�̖��Ƃ��čl���Ă݂܂��傤�B
��s�s�̏ꍇ�͍����������̐ݒu������ȏꏊ���������߂ɁA������x�̉��������͎d�����Ȃ��Ƃ��Ă��A�ݒu���\�ȏꍇ�͂ł�����菈���r�����͐�Ɋҗ������i�ǂ����痈������������Ȃ����̂��Ҍ��Ƃ��җ��ƕ\������̂͑����^�₪���邩���m��܂��j�A�͐�ɑؗ�����\�w���̐�Ηʂ��m�ۂ���ׂ��Ȃ̂ł����A����ȑO�ɁA�~�����J�̑唼���������������A�C�Ɏ̂ċ��鎖�����l���Ă��Ȃ����݂̓s�s�͐�̐����̂�����ɂ����ő�̖�肪����̂ł��B�@ |
 |
| �[���Q���[�g�����z����T�^�I�ȓs�s�^�͐�B��l�ł��������甇���オ��Ȃ��B |
| �@ |
�@�Œ�ł��J���J���̕����H�͂�߂�ׂ��ł���A�܂��Ă�n���̋�������H�Ɏ����Ă͋����Ƃ��������悤���Ȃ��̂ł����A�����͂܂��܂��t�̕����Ɍ������Ă���Ƃ����v���܂���B
����ɂ́A�t�����Ēn�����̑�K�͂ȏ����Ƃ����b������܂����A�{��ɂ́A�قځA�W������܂���̂ł���ȏ�͂ӂ�Ȃ����ɂ��܂��傤�B
�@���ǁA���[�l�R���������ɐŋ�������ł���悤�Ȍ`�ɂ������Ƃ̕�����������ꂸ�A��ʉ͐�̕\�w���̑ؗ����i����Ȃ��̂͂�����x�̒Ⴂ���⌊�J�����邾���ł������Ɏ����ł���̂ł��j�����킹�A�͐���ӂ�����͔ȗт���y�܂ł����킹�A�����|���̔��������Z�����g����^���Ōł߂��e���͐�����Ō떂�����Ă���̂ł�����A���̍��y�ɑ���G�ΐ��͖��炩�ł��B
���Ȃ��Ƃ��A��s�s�̑�^�͐삩�疖�[�̏��r���H�Ɏ���܂ŁA�������������邱�Ƃ����l���Ă��Ȃ��͐쐮�����͐�s�����̂��̂��ǂ��ɂ����Ȃ���A�s�s�̊������͎~�܂�͂����Ȃ��̂ł��B
�@�����A�G�s�\�[�h�I�ł͂���܂����A���̒ꗬ�ɂ́A�����ȗ��A�]�ˊ��̓`���I�ȉ͐�Z�p���̂ċ���A�ꋓ�Ƀ��[���b�p�̉͐�H�w�A�y�؋Z�p�Ɉڍs�������ƁA�܂��A���ɐ��̉͐�s�������������\�w���𗬂��o���Ƃ����͐�Ǘ��������嗬�Ƃ���I�B���̎��������̉�����ɁA�V���n�A�헬��h�A�֍s�͐��������A�����I�͐�Ǘ���ڎw�����֓��������p���̂ċ���ꂽ���ɂ�����������ƌ����Ă���̂ł��B |
| �@ |
| �B�@�s�s�����̂��肩�� |
�@�{���A��s�s�Ƃ����ǂ����������悬���̉j���삪���z�ł��邱�Ƃɕς��͂���܂���B
�������A�S�Ă̐�ɂ�������߂邱�Ƃ͂��͂�s�\�ł��傤�B
������ł��A�n��Ɍ����|�������̓`���I�͐�������鎖�͂ł��܂����A�����A�����I�ɂ͍s���Ă͂���̂ł����A����͂����܂ł��ꕔ�ł����Ȃ��A���F�͌��肳�ꂽ�������ɉ߂��Ȃ��̂ł��B
�����A������A�q�[�g�E�A�C�����h�Ɋւ��Ă͗L���ł�����A���ꎩ�̂�ᔻ���Ă��A���Ƃ��̖��Ɋւ��ẮA�Ӗ��͂���܂���B
���ɐ����̑��݂��Ȃ��v�[���ł������Ƃ��Ă��A���x�������鎖�ɂ͖��ɗ��̂ł�����A"�ł�������"�Ȃ�"���Đ�"���s�����́A�v�[�����̂��Ԃ̑ł������ʂ���������"���萅"�i���萅������I�j�ɂ���ׂ��Ȃ̂ł��B
�����A�c����s���͖��S�Ɠ꒣��ӎ��̐��x���ł�����A�����S���������A�|���⎖�̂̐ӔC����̗v������A�J���Ő��鎖������낤�Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂ł��B
�@���ړI�ȊǗ��҂́A�u�����t���v�Ƃ��A�u�{�E�t�����N���ĉႪ��������Ǝ�����������c�v�Ƃł��������ł��傤�B
�@�v�[����A�����������^�����ߗp�̗V���n�ɉ��݂̐��グ�r���������A�J���ŏ\�Z���`���x�̐[���Ő��邾���ł��A����Ȃ�̌��ʂ��]�߂�̂ł��B
����Ȃ��̂�"�ł�������2006�`"�̐�`�o��̖����̈�̔�p���|���Ȃ��ʼn\�ɂȂ�q�[�g�E�A�C�����h��Ȃ̂ł��B
�������A�^�ʖڂȓw�͂������ɁA�V���������߂𒅂���ŁA"�ł���"�Ȃ邽����"�̂Đ�"�p�t�H�[�}���X�ōς܂���̂ł�����A�������������Ƃ��������悤������܂���B
�@����ɕt��������A�S�Ẵr���̉���Ή��A�ǖʗΉ��ƉJ���ɂ��"���㒣�萅"�����ł������ɓs�s�̉��x���P��I�ɉ����鎖���ł���͂��ł�����A�i�K�I�ɐi�߂�A�\�N�Ƒ҂������đ傫�Ȍ��ʂ��o�Ă���͂��Ȃ̂ł����A�S�����łƂ��Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂ł��B
���ǁA�������⊯���ǂ��́A���Ƃ�s���{���ł��ɂ���Ď���̎x�z�́A�e���͂��g�債�A�������痘�v�i�s���n�l�j�������o����ꍇ�ɂ����������Ƃ͂��Ȃ��̂ł��B
���炭���[�l�R�����n�߂Ƃ��āA����̑��̊|����������Ƃ������V���ȃr�W�l�X�E�`�����X�Ƃ��ē���������܂ł́A�����Ď������������Ƃ͂��Ȃ����Ƃł��傤�B
���̂��߁A����Ή��A�ǖʗΉ��ɂ��Ċ��ɋZ�p���m�����Ă���x���`���[��Ƃ�Ɨ��n�̏���Ƃɂ͑S���`�����X�͗^�����Ȃ��̂ł��B���ꂪ�A�䂪���̍s�����ԂȂ̂ł��B |
| �@ |
| �b�x��@�@�g��t���̘d�G�Ƃ��Ă̍ďA�E�h |
| �@ |
�����\�`��\�N�قǂŁA�e���̌������̕����K�����ُ�ȂقǂɌ��i������܂����B
���̂��Ƃɂ���āA�͕̂��ʂɉ��s���Ă��������ڑҁA�Ǝ҂Ƃ̉�H�s�ׁA�Ε�̕t���͂��A�]�A�]�E�j���c�͏����A���Ɍ����ȍs�����m�����ꂽ���̂悤�Ɍ����܂��B
�������A���X�ɂ��Č�������舵���������ꍇ�́A�A�ŗy���Ɍ��߂�����K�͂ȕs�����s���Ă��邩��ł����āA��������Ƒ傫�Ȉ��������߂ɂ́A���[�̐E���̋K������������A�����ł���悤�Ɍ��������Ă��邩��ƍl����̂��������ł��傤�B
�y�؍s���̌���ł́A���܁A�������߂ƈ�ʌ����̐�`�Ƃ��āA�ڂ����đf�s�̈�������l�������E������邱�Ƃ�����̂ł����A�ʏ�A�y�؍s���̌���ł͒��ړI�ȋ��K�̎���ƌ����������炳�܂ȑ����d�͂߂����ɍs�Ȃ��͂��܂���B
����ȕ��@�����Ȃ��ōςނ悤�ɁA���S�Ŏ����I�ȕs�����s�Ȃ��Ă���̂ł��B
���ƂŌ`�����ꂽ�{�H�Ǝ҂Ɗē��闧��ɍ݂�Z�p�n�E���Ƃ̊ԂɌ`�����ꂽ�e���ȊW���ǂ������u�M���W�v�́A���R�ɂ��ސE����܂ň��p����A��s���ēV���肵����i�̈����ɂ���āA�@�O�ȋ��^�ň��肵���֘A��ƂɍďA�E�ł��邩��ł��B
��ʂ̘J���҂��ސE��ɏ\���~�O��̒�����Ŏ��ʂ܂œ�������Ȃ����ŁA���ɗ����̃X�L�����Ȃ����ے��N���X���A�O�\���~�O��̋��^�ōČٗp����Ă���̂ł��B
���́A���ꂱ�����Օt���̘d�G�ł���A����ɂ��₩�邽�߂ɁA���������A�����A�{���ē��ׂ���Ƃ̕s���Ɋ���Ԃ葱���X���͂��葱���Ă���̂ł��B
���̂悤�Ȃ��Ƃ�h�����߂ɁA�������ɂ͈�ʂƔ�ׂđ����D�����ꂽ�N�����x���ێ�����A���h�Ɋē��邱�Ƃ����߂��Ă����̂ł����A�ő��A���̈Ӗ��͊��S�ɖY�ꋎ��ꂽ�ƌ����Ă��ߌ��͂Ȃ��ł��傤�B
���ꂪ�A�s�A�����x���̘b�Ƃ���A���[�l�R���ƌq���鍑�N���X�̍����������ǂ̂悤�Ȃ��̂��́A���ڂ͌��������Ă��Ȃ����߁A���]�Ƒz���̈���o�܂��A����̌����͎����ƕt�����ƌ������̂ł��B |
| �@ |
| �C�@�g�傷��A�X�t�@���g�ܑ��Ɏ��łāI |
�@���܂�A�x�O�^�`�F�[���E�X�g�A����A��^�X�𒆐S�Ƃ���p���[�E�Z���^�[�Ɏ���܂ŁA�X�܂�{�݂̖ʐςɐ��{���钓�ԏꂪ�L�����Ă��܂��B
���ꎩ�̂̓��[�^���C�[�C�V�����������炵���s�s���ɂ�鍻�����ɉ߂��Ȃ��̂ł����A����ɂ��Ă��ł�͏\���ɂ���̂ł��B
�@�Œ�ł��A�V�K�o�X�ɍۂ��Ē��ԏ�̑S������ꕔ�i���ԃX�y�[�X�����ł��Ӗ�������͂��ł��j�������K�Ɠy�Ő���������Ƃ��A�S�̂ɓ������ܑ����`���t����Ƃ��i�ʏ�͏d�ԗ�������Ȃ��̂ł����狭�x�͖��ɂȂ�Ȃ��̂ł��j�A����́A�����ɓs�s�^�^���ɖ𗧂͂��ł����璼���ɂ��ׂ��ł���A���z�m�F�\�����ɕܑ��̋K�������ׂ��Ȃ̂ł��i����͌l�Z��A�}���V�����ɂ��Ă����l�ł��j�B
����Ƃ��o�X�K�����ł��闧��ɂ��鋌�ʏ��Y�ƏȂɂ͉��g�����q�[�g�E�A�C�����h����؊W���Ȃ��������قȂ邽�߂ɕ��u����Ă���̂ł��傤���i���z�m�F�\���͍��y��ʏȏ��ǂȂ̂ł����H�j�B
�@���l�ɁA������ł���ʊ�Ƃ̒��ԏꂩ�烉�[�������̒��ԏ�A�}���V�����A�s�������A�����قɎ���܂ŁA�����̒��ԏ�̒��ԕ��������ł���o���A�����K�⎩�R�Ƒ��i����Ȃ��͓̂y�����c���Β����ɐ�����j�Œ��ԏ�����邾���ł��A����Ȃ�̌��ʂ͂���A���X�ҁA����҂����X�ɑ����Ă���͂��Ȃ̂ł��B
�@���͂�A���H�ʐςƒ��ԏ�ʐϔ䗦�̓��X�E�A���W�F���X�Ȃ݂Ɋg�債����̂ł����A�A�X�t�@���g�ܑ��͍����ȉ��̕ې��͂����Ȃ����ɂ��낻��C�t���A�{�C�ő���l����ׂ��ł��傤�B
�����A��������炭�s�\��������܂���B���ǂ́A���Ԏ哱�ŁA�g���ԏ�ɖؐ��u���b�N�ⓧ�����ܑ����{���Ė؉A�����₵����A����������Ɨ��X�q���������̂ŁA�����o����|���Ă������������������I�h�ƁA�Ȃ�Ȃ���������I�ɂ͕s�\�ł��傤�B
���ۂɂ́A���ނ���̌o��A�J�́A���Ԃ��팸���邽�߂ɁA�t�ɕܑ������i��ł��܂��X���ɂ���̂ł��B |
 |
| �{�茧���ѐ�k�J |
| �@ |
| �D�@�l�łł���q�[�g�E�A�C�����h�� |
�@���̖����������ɂǂ�قǂ̈Ӗ�������̂������̋^�������̂ł����A��l�̌l�I�w�͂ɂ���ẮA�������ܑS�̂̃q�[�g�E�A�C�����h�����}������ׂ����Ȃ��A���̎�̓w�͂͂���Ӗ��Ń{�����e�B�A�I�Ȏ�̗̈�A���������t�@�b�V������l�I�u�ƍߕ��v�̗̈�ɂȂ�̂����m��܂���B
�@����ɂ́A�s�K�v�ȃR���N���[�g�ܑ�������K�v�ŏ����x�ɗ��Ƃ��B
�Z���̑��a�Ɍ��Ԃ�Z�����ɂ���B
�������O�ʒ���ł͂Ȃ���ʂɏ����l�ߍ����̂ɂ���B
��̋��ɏ����ȃo���J�[���x�̐Z���^�̌E�݂�B
�����ɍ~�����J��������|�������̐�����A�y�������ł���Ɋ|�������B
�C��������[���b�p���K�[�f�j���O�Ȃǒ����Ɏ~�߂Đ����̑�����A����B�������Ƃ�������������̂ł����A���z��◎���t�~������a�����܂ł������镗���������������A�����������Ƃ����l�����܂���B |
| �@ |
| �E�@�����A�X�H�̐����̂�����ɂ��� |
�@����̐X�Ƃ͈قȂ�A�����͎����I�ȗ]��n�ł�����A����Ӗ��ŕ��u���{���̐A���ɖ߂��ł���Ȃ�Ε��т����邱�ƁB
�ǂ����Ă������ɂ������̂ł���A�y�����ƓV����̘A�����������ׂ��ł���悤�ȃ��[���b�p�^�̊������������ł͂Ȃ��A�ݗ��̐X��тɋ߂����̂ɂ��ׂ��ƍl����̂ł����A�����s���ɂ����Ă����A�s�����Ǘ����₷���悤�ɕ\�ʂ���y��D���s�����A�R���N���[�g�Ōł߂Ă��܂����˂Ȃ������Ȃ̂ł�����Q���킵������ł��B
�@���������A���{�ɂ͌����͂���܂���ł����B
���{�ŏ��̌������ǂ��ł��������܂ł͊S�������̂ł����A��y���i���R���j�A���Z���i���䌧�j�A��y���i��錧�j�Ƃ��������̂́A�����܂ł��r�c�ƁA���ˉƁA�O�c�ƂƂ������ˎ�̎��I�Ȓ�ɉ߂����A���Ђ̒뉀����V�c�Ƃ���Ƃ̂���Ɏ���܂Ńp�u���b�N�E�K�[�f���ł͂Ȃ��̂ł��B
�@���̊�Ȃ��̂����{�Љ�Ɏ������܂ꂽ�̂��A�����̉�������ɂ����̂ł����Ȃ��i�����Ƃ������t�����������ȑO�ɂ͑��݂��Ȃ��͂��ł���A�����̖������̋}�����ꂽ���ꁁ�e�N�j�J���E�^�[���ł����Ȃ��ł��傤�j�A���O�͐₦���c����R�т�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł����āA�ނ���A���R�Ɛڂ��邱�Ƃ�a�܂��������v���Ă����̂ł��B
���̂��ߓ��{�Ɏ������܂ꂽ�����̓��[���b�p�N���̂��̂ł����Ȃ��A������z�����w�I�Ȑv�ŎŐ�����܂ŋK���I�Ɋ��荞�ނȂǁA���悻�A���{�̓`���I�Ȓ뉀�Ƃ͑S���قȂ������̂Ȃ̂ł��B�@
�@�]���Ă��̉����ɂ���������A���͂���{�̕��y�ɍ��������̂ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���A���܂��Ɍ��݂̌����̂�����ɂ͈�a������������Ă��܂��B
���ʂƂ��āA�G���ȃ��[���b�p�뉀�̃C���[�W�ŁA�y�̕������ǂ�ǂ炳��A�ې��͂��������뉀������ꑱ���Ă���̂ł��B
�ŋ߂ł͗����t�����������A�l�b�g�ŖؑS�̂��A�͂�t���W�߂ăS�~�܂ɓ���Ď����o����Ă��܂��̂ł�����A���z�͂��납�A�h�{�A�Ђ��Ă͕����z�܂ł��������Ă����̂ł��B
���̂悤�ȋ����Ȏ��𑱂���A���͌����A�ŏI�I�ɂ̓~�l�����܂ł����������̖͂�����炽�Ȃ��Ȃ邱�Ƃł��傤�B
�@���Ȃ��Ƃ��u�����t�����ł������̓y�ɖ߂��I�v�ƌ��������̂ł����A�s���͉����C�ɂ��Ă��Ȃ��悤�ł��B
�u�����t���炢�ʼn���傰���ȁc�v�ƌ����邩������܂��A�Ȃ��A���̂悤�Ȏ�����ɂ��邩�ƌ����ƁA��s��ł�����ꂽ�y���c������ɉ����Ă��A�����t���y�ɖ߂�A���t�y���L���ɂȂ�A��������쒹�⌢�L�܂ł�����Ă���悤�ȂƂ���قljh�{���L���ɂȂ�i���A��r�[���܂߁j�����ɖ��ې��͂��ێ����邩��ł��B
���������A�����t�܂ŎY�p�p�̑܂ɓ���ďo���悤�ɂȂ����̂́A�Y�p�Ǝ҂̗����\���ɍs������e���c���i�����钬��c�����`���b�J�C�c���j��A���[�̎�����܂ł��������܂�Ă��邩��Ȃ̂ł��B
���I���I�Ɛ����ɋ��Ԋ���������A���������̕��E���ɔM�S�ŁA�����ᔻ����Ɣn�������o�b�V���O����̂ł����A����ȘA���͊��ȂǑS���������Ă��Ȃ��̂ł��B
�Ԉ���Ă�"���̎U���ŕ����Q��"�ȂǂƖ���킩�炸�ɑ呛�����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�܂Ə��^�̃X�R�b�v����ɎU�����鈤���ƂقLj���Ȃ��̂͂Ȃ����̂ł��B |
| �@ |
| �F�@��̉_ |
�@�u�s�s�̔p�M���̂̓q�[�g�E�A�C�����h���̌����ł͂Ȃ��v�ȂǂƂ܂ł͌�������͂���܂���B
�@�����A���z������M�ɑ��Đl�Ԃ������M�̐�Ηʂ͂���قǑ傫����ł͂Ȃ��i���{�̃G�l���M�[����ʂ͍��y�̂��ׂĂ̕��n�����z��������G�l���M�[�̂S�����x�^�w�n�����E�ǖ{�x�j�A��s�s�������͊����ɂȂ��Ă���Ƃ��Ă��ߑ�ɕ]�����鎖�ɂ͐T�d�łȂ���Ȃ�܂���B
�������A�����͌����Ă��l�Ԃ̊���Ƃ������̂͂���قNjq�ϓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ȏ�A�ꉞ�͍l���Ă����K�v������ł��傤�B
�G�A�R���̎��O�@�̎��t�������ŗׂƑ����ɂȂ�̂��l�ԂȂ̂ł�����A���̗v�f�͖����ł��Ȃ��̂ł����A�_���I�Ɍ����A�{���A���̓{��͍��y��ʏȂɂ�����������ׂ��Ȃ̂ł��B
�u���A���Ȃǂ̒ᑬ�ő��鍂�����H��ɂ͊�̉_���|�����Ă��邱�Ƃ�����v�Ƃ����b�������Ƃ�����܂��B
�����ʂ�A��i��j�̉_�Ȃ̂ł����A���ʂ�"�������H�ŏa�𑱂����^�g���b�N�Ȃǂ���r�o���ꂽ�M�ɂ���ď㏸�C�����������A����ɕ����Ēn��̐����Ȃǂ������グ���A���ŗ�₳��ĉ_�ɂȂ��Ă���̂�"�Ɛ��������̂ł��傤�B
�������A�ǂ��l����A���͂⍑�y��ʏȂ������N�������������ɂ���āA�n�\�ɂ͐������Ȃ��Ȃ�A�r�C�K�X�̒��Ɋ܂܂�Ă��鐅���C���㏸���ĉ_�ɂȂ��Ă���̂ł����āA���y��ʏȂ̔n�������ǂ��ɂ���Ēn���ɗ������܂ꂽ�J���́A���ɓs��̏�Ɋ|����_�ɂ͊�^���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���قǂł��B
"�s��̐l�Ԃ������̓V�R�������݁A����~���A���̐����ƃT�E�W�A���r�A�̒n������^��Ă����Ζ��Ɋ܂܂�鐅�f�������R���Đ��ɂȂ�A�_�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����i�܂��ɕ����z�̌���I�j��ł��ˁj�H"�ȂǂƖϑz���d�˂Ă���̂ł����A����͊m���鍪���̂���b�ł���܂���̂ł��̂���œǂ�ł��������B
�@���Ȃ݂ɁA�Y��ΒY��R�₵�Ă��A��v�ɂ͓�_���Y�f�����o�܂��A�Ζ���V�R�K�X�Ȃǂ͒Y�����f�ł���A�R�₹�Γ�_���Y�f����ł͂Ȃ�������������̂ł��B |
| �@ |
| �b�x��@�@�g�����Y�h |
| �@ |
������₷���Y�ΏĂ̘b�����Ă����܂��傤�B
�����Y�����Ă͂₳��鎞��ł����A���㉮�����q���Ă����Y�ł��낤���A�C���h�l�V�A����A�����ꂽ�ؒY���낤���A�����͒Y�f�����ł�����A�R�₵�Ă���_���Y�f���o�邾���ŁA�����C�͈�؏o�Ȃ��̂ł��B
���̂��ߐH�ނ͏����Ă���ԂɂȂ炸�A�\�ʂ��J���b�Ǝd�オ����������̂ł��B
�R�₷�ƁA�����ɐ�������������K�X�ȂǂŏĂ����E�i�M�∼����������͂Ȃ��̂ł����A����͂����܂ō��z�Ƃ̎��ԂƂ̑��k�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��B
�t���E�^�C���̃p�[�g�Ƃ�������I�ɂ��Ӗ��s���̘J������������Z���������̐l�B�ɁA��ԁA�ɂ��|���������@��v�����Ă��A����͓y�䖳���ƌ������̂ŁA���ǁA�{���ɔ������H�ו��͒m���������������A�������ɋ�������ґ�Ȃ̂ł��B |
| �@ |
| �Ăсu��̉_�v���� |
�������A��i��j�̉_����{���ɉJ���~��̂ł���A�߂����b�ł͂���܂����A�s�s�̐l�Ԃ́A�a���ᑬ�ő��鍂�����H�Ɋ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�������܂���B
�@���̂悤�ɁA��s�s�̐��z�͊��ɋ�~�����J���������ĉ_�ɂȂ�A�ĂсA�J�ƂȂ��Ēn�\�ɖ߂���A���̏z�ߒ��̒��ŔM�����ɕ��o����Ƃ������ʂ̐��z�A�M�z�����ꂩ���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ��������l���Ă����K�v������Ǝv���̂ł��B
�@���ɁA��s��ő�J���~�����Ƃ��Ă��A���̐��͍��y��ʏȂɂ���ĉJ���ꂽ�����͐�ɂ���Ĉ�C�ɊC�ɑ���o����A��J���オ��Βn�\�͒����Ɋ���������悤�Ȑ��E�ɕς����Ă��܂��Ă���̂ł��B
���̂��߉J���͑�s�s�̏��ɉ_�ݏo�����̋������Ƃ͌����Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ��̂����m��܂���B
�@���̈���A�������Ȃǂ��N���Ƃ��鐅��n���̏㐅���ǂȂǂŎ��A������c�萅�̑唼�������Ƃ��Ēn���̉������ǂɗ������݁A�J���~���Ă�����n�������H�≺�����ǂɑ��荞��ł���̂ł�����A���ɑ唼�̐H�ނ���~�l�����E�E�H�[�^�[�Ɏ���܂ŁA��s�s�ł͎��牽�����ݏo���Ȃ��̂ł���A�������ꂽ�y�n�̐�����s�s�̐l�Ԃ̊��⑧�Ƃ��ĉ_�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���邱�Ƃ́A���Ȃ������Ƃ������Ȃ��̂ł��B
�@���Ă݂�ƁA���A���Ɋ|�����̉_�A�܂��̉_�Ƃ͑�s�s�̏k���������z�̍Ō���ے����Ă���悤�Ɏv���Ă���̂ł��B
�@���̂悤�ȋ����ȍ��y�ɂ����A���͍����ɓy�������ӂ�ׂ��Ȃ̂ł����A���܂��ɉ������߂����ɂ͂���܂���B |
| �@ |
| �������[�� |
| �@ |
�@����Ȃ��Ƃ͎O�A�l�\�N�O�܂ł͑S�������������Ƃł����A�[�����ɒ[�Ɍ����Ă��邱�ƂƁA�q�[�g�E�A�C�����h���ۂ͊m���ɑΉ����Ă���悤�Ɏv���܂��B
�[�����~��Ȃ��ƒn�\�͗�₳�ꂸ�A����S���C���������炸�M�і邪�����Ă��邱�Ƃ��A�唼�͂��ꂪ�����ł��傤�B
�ł́A�Ȃ��[���������Ă���̂ł��傤���H
�@�����܂ł��Ȃ��n�\�̕ې��͂������A���́A�\�w���ƌĂ�ł���̂ł����A�n��ɑؗ����鐅�̐�Ηʂ������Ă��邩��ɊO�Ȃ�܂���B
�܂��A�W�������Ȃǂ̔M�ѐ��X�R�[���Ƃ͎ܔM�̑��z�ɂ���ď��������n�\�̐������y���Ȃ��ď㏸���A�ĂсA���ŗ�₳��J�ƂȂ��Ēn�\�ɕԂ���Ă�����̂Ȃ̂ł��B
�������A�������Ƃ͌����A�n��ɂ̓W�����O���␅�c���L����A�펞�A�������߂��Ă��邽�߂ɁA���̏��U�ɂ���ċC���M���D���A�n��̉��x��ቺ�����A�Ăю��̃X�R�[���Ƀo�g���E�^�b�`����Ă����̂ł��B
����M�тƉ������s�s�ɂ����Ă��A�����@���͓��l�ɓ����͂��ł����A���͂�s�s�̒n��ɂ͐����Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł��B
����łȂ��Ƃ��������ɂ���čP��I�Ȑ��z���j��Ă���̂ł�����A���킸�����Ȃł��傤�B
�@��s�s�̃q�[�g�E�A�C�����h���ۂ̓G�A�R���̔p�M��Ԃ̔r�C�K�X�Ȃǂ������ƍl���Ă���l�������̂�������܂��A�{���ɏd�v�Ȏ��͓s�s�̃R���N���[�g���≺�����̐����Ȃǂɂ���Ēn�\���琅�������A�]���̐��z�A�M�z���j��n�\�̔M������ɕ��o����ɂ����Ȃ��Ă��邽�߂Ȃ̂ł��B
�[���Ƃ͌���Ώ��ƒn��Ƃ̊Ԃōs���鐅�̃L���b�`�E�{�E���ł���A�[���̏����̓{�E�����̂��̂̌����̌��ʂł����Ȃ��A��s�s�̃q�[�g�E�A�C�����h���ۂƂ͓s�s�̊������ɂ���Ă����炳�ꂽ�[���̏����ƁA���̌��ʂƂ��Ă̐V���Ȋ������ł������̂ł��B�@
���ǁA�s�s�̊������Ƃ͗[���̏����������ł��蓯���Ɍ��ʂł�����̂ł��B
�@�܂������A�[���̏����͓V�b�Ƃ��Ă̍ŗǂ̔r�M�i�]�v�ȔM�̕��o�j�̕��o�V�X�e���̔j��ł���A����������炵�����̂����A�͐�̉J�ƉJ���̒n�����i�n���ւ̐Z���Ȃ�ǂ��̂ł����A�������ւ̗������݁j�𐄐i���Ă��鍑�y��ʏȂȂ̂ł��B |
| �@ |
| �_���̃q�[�g�E�A�C�����h |
| �@ |
| �@�ł́A�_����n���s�s�͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���A���͂����ł��ڂ����ė[�����������Ă���̂ł��B |
| �@ |
| �@�@�c���̃q�[�g�E�A�C�����h�� |
�@�܂��A��s�s�ɏZ�ޕ��X�����܂育�����Ȃ��b����n�߂܂��傤�B
�l�A�\�N�O�܂ł̔_���ɂ́A�܂��A����n�ɂ��"�r�N��"��"��~��"���c���Ă��܂����B
�������A���̌�̃e�[���[����g���N�^�[�����đ�^�g���N�^�[�̓����ɂ���čk�ς̌`�Ԃ͑傫���l�ς�肵���̂ł����A���́A���̋@�B�̓����ɂ���āA�c�A���͔��ɑ傫���ς���Ă��܂����̂ł��B
�@�B�ɂ��k�ς́A�[���Ă���Z�`��܃Z���`���[�g���A��ʓI�ɂ͘J�͂ƔR������y�����邽�߂Ɉ�Z�Z���`���x�����k���܂���B
���n�k�̏ꍇ�͓�Z�`�O�Z�Z���`�̐[�k���\�ł���A�������̂悤�Ȏ��c�����ɑ��������̂ł����A�@�B�ɂ��N�k���唼�ɂȂ�ƁA�@�B���g���Ղ����邽�߂ɁA�S���œW�J���ꂽ�ُꐮ�����Ƃɕ����Ċ��c�����i�߂�ꂽ�̂ł��B
�_�Ƃ̑唼�����Ɖ�����悤�ɂȂ��Ă���ƁA�ȗ͉��̂��߂ɗp�r�H�͍a������������Ȃ��Ă��ςނ悤�ȎO�ʒ���̃R���N���[�g�Ōł߂����a�ɕς����A�J���͂����ǂ���ɉ͐삩��C�ɉ����o����čs���܂����A���c������Ԕ_�Ƃ���������}�����̂ł��B�@
�ُꂻ�̂��̂��A�u�c���̐ؑւ��ł���悤�Ɂv�Ƃ����U�ꂱ�݂ŁA�R���Q�[�g�E�p�C�v�𒆐S�Ƃ���Ë��r�����قƂ�ǂ̓c���Ɏ{�H���ꂽ�̂ł��B
���̂��߁A�唼�̔_�n�̓S���t��ƕς��Ȃ��悤�ȁA���Ɋ������₷�����̂ɕς����Ă��܂����̂ł��B
�������A��A�����Ă���̂ł�����ċG�͐��������Ă��܂����A���ɁA�����͎O������l���ɒB���A�k������̑���������āA������͔������A���{�S�̂ōl����A�É����Ȑ��̔_�n�ł͑S���Ă�����Ă��Ȃ��̂Ɠ�����Ԃ��o�����Ă���̂ł��B
�k��������i�ޒ��A�]��c�͔��Ƃ��đ哤�ȂǐA�����܂�����A�������͈�w�i��ł���̂ł��B
�܂��A���[�R�V�q�J���Ȃǂ��Ƃ������A�ċG�ɂ͊������܂ō͔|����Ă��܂�����A�[�����K�v�ȋG�߂ɂ͐������Ƃ���Ă���̂ł��B
���̏�ɁA�_�n�̓]�p�Ȃǂɂ���čk�n�ʐς��̂��̂��������Ă���̂ł�����A�������͎~�܂�Ƃ����m��܂���B
���炭�A�S���̐�����ʐρi���R���鐅�c�̖ʐρj���̂��̂́A�������J�n����Ĉȍ~�A�S���I�ُꐮ�����Ƃ̊����������āA����ȑO�Ɣ�r����قڔ������Ă���ƍl���Ă܂��ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B
�@���̂��߁A�_������n���̓s�s���ɂ����Ă��͐�̒������A�J�͓��l�ɍs���Ă���̂ł�����A��s�s���Ɠ��l�̊��������i��ł���̂ł��B
�@�]���āA�n�\���M�����ď������鐅���C�̐�Ηʂ��������A�O�a�Ɏ���e���|�A�s�b�`�������A�[���̌�����������ւƓ˂��i��ł���̂ł��B
�@�_������n���s�s�ɂ����Ă��A�[���ɂ�鐅�z�A�]���ĔM�������j��Ă���ƍl���ĊԈႢ�Ȃ��̂ł��B |
| �@ |
| �A�@�R�̃q�[�g�E�A�C�����h�� |
�@�ω��́A�R�ł��N�����Ă��܂��B
�j�t���т̑����ɂ��ې��͂̌��ށA���h�H���Ȃǂɂ���Đi�ސ��H�̎O�ʒ���A�s�K�v�ȗѓ��H���Ȃǂɂ��R�ю��̂̊������i�ѓ��̓��H���a�͕��n�܂ő����J��ɓ������̂ł��j�ɂ��A�R�ѕ\�ʂ̐��̐�Ηʂ��������A�R�ɂ����Ă����̃L���b�`�E�{�E���i���̏z�j���������Ă���Ƒz������̂ł����A�����g���R�тɏZ��ł���킯�ł��Ȃ��A�܂��A�s�s�A�_���A�R�сA�C�m�ł̍~���ʂ̌n���I���������Ȃǂ���͂����Ȃ��A�����̈���o����̂ł͂���܂���B
�@�����A�j�t���щ��ɂ��R�т̊������A�������Ƃ������͓s�s���ɏZ�ޕ��X�ɂ͔��ɕ�����ɂ����Ǝv���܂��̂ŁA�ߋ����x�������Ă������Ƃł����A�����̐��������������Ǝv���܂��B
�@���R�сi����Ȃ��͎̂����㑶�݂��܂��j�ł���тł���A�{���̐A���ɍ��������L�t���̎R�Ƃ������̂́A���N���̊Ԃ̑䕗�⍋�J�A�\���A�R�Ύ��A�n�k�ȂǁA�z���ł��邠��Ƃ�����ЉЂ��o���������Ƃɂ���āA���̎R�̂̌X���������x���̑傫�ȕ�����o�Ă���Ȃ�Ɉ��肵�����̂ɂȂ��Ă��܂��B
�L�t���̓I�[�o�[�E�n���O�̋}�s�Ȋ��̊���ڂɂ���������A�����̕ǂɂւ�t���Ă������x���܂��B����ɔw����Ⴍ�A���̎��̂����Ȃ₩�ł��邽�߂ɁA���J�ɂ������A�L�����邱�Ƃɂ���Đ����y���ۂ��Ă����̂ł��B |
 |
| ���Ȃ��Â������̂���Ă��Ȃ��j�t���сB�����͐������A�قƂ�Ǖ���Ȃ����̗t�ɕ����Ă��邪�A���鑐�ł͂Ȃ��̂œy������͂��Ȃ��B |
| �@ |
�@����ɑ��đS���t�Ȃ̂��j�t���тł��B
�{���A�j�t���̓V�x���A�̃^�C�K�̂悤�ȁA����قǕ��������Ȃ����肵�����ܓx�����т̕��n����ɌX�Βn�тň���̂Ȃ̂ł��B
���������A���̂悤�Ȏ������{�̂悤�ȋ}�X�Βn�ɐA���邱�Ƃ��n�߂�����Ƃ����Ό��Ȃ̂ł��B
�@��ʓI�ɁA���ђn�͍L�t���̐X���F�����ăX�M�A�q�m�L��A����̂ł����i�Z���F�������j�A���̌X�͍L�t���̐X�ł��������Ƃɂ�蒷�N���̊ԂɈ��肵�����̂ɂȂ��Ă�����̂ł���A���ɋ}�����ꂽ�悤�ȁA�ɂ킩�d���Ă̐j�t���т�̂ɓK�����Γx�ł͂Ȃ��͂��Ȃ̂ł��B
�@���炸�A�L���ȕ��t�y���`�����Ȃ��j�t�����X�Βn�ɑ��݂��Ă��邾���ł��A�J�̑唼����C�ɊC�ɗ�������ł��邱�Ƃ��z���ł��܂����A���͂����Ƌ낵�����Ƃ��N�����Ă���̂ł��B
�@����́A�����ɑ��݂��Ă���j�t���т̑唼���Ԕ����}�ł����s���Ȃ����߂ɁA�т̒��͒��ł��Â��A�z�������Ȃ��n�ʁi�я��j�ɂ́A���������Ă��Ȃ������o���̕\�y���L���肻�̑唼�����o���Ă���̂ł��B
�@���̌��ۂ͏��q���ƍ����̏����̒ቺ�ɂ��Z��H�����̔����ƁA�Z��̃v���n�u���ɂ���āA�A�����ꂽ�ă}�c�ɂ��p�l���H�@���������A�����ɁA���A�O���g���ݗ��H�@�ɂ��a�����z�����������\�`��ܔN�قǑO����N�����Ă����̂ł�����A�s�s�̏Z��A�قځA�S�ƃR���N���[�g�ƃK���X�ƃv���X�e�B�b�N�ő�����}���V�����Ɉڍs���Ă��邱�Ƃƕ����čl����A�S���̐��A�O�͂��̈ꕔ�������āA�O�`�l�\�N�O�قǑO����މ��͌��I�ɒቺ���A�قځA����Ȃ��Ȃ��Ă����ƍl���Ă܂��ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B
���̂��Ƃ���A���`���Z�N�ォ��Ԕ����}�ł����s���Ȃ��܂܁A���u����Ă����ƍl������̂ł��B
���̌��ʁA�R�̓y��͑�J�̂��тɗ���o���A������͐��덻���̏�ɗт�����Ă��邾���ɂȂ��Ă���̂ł��B�@
�@�����ɕې��͂������̂͂�����܂��ł���A�R�̊������������ׂ���Ԃɂ��邱�Ƃ͎����ł��傤�B
�@���̂悤�ɏ����Ƒ��т̐����������ق���і쒡��ыƊW�҂��甽�_���������Ă������ł����A���̖��ɑ��钼�ړI�Ȑ����Ƃ�����ł͂���܂��S���ڗ����Ȃ����̂ł������A�����F�߂���Ȃ��V���L��������܂����̂ŏЉ�Ă������Ǝv���܂��B |
| �@ |
| �u�ې��͂̒������R�т��D�ʁv��Ӑ�u�̃_���v�\�z������ł��B�u�����Ȃ̐�Ӑ�_���v��i�F�{���j�̑�ֈāw�̃_���x�\�z�������邽�߂ɁA���Ȃƃ_�����Δh�������Ŏ��{�����т̕ې��͂̒����ŁA��Ӑ�㗬�̐l�H�т̎Ζʂ𗬂�鐅�ʂ��A���R�т̖�Z�{�ł��邱�Ƃ����������B�����҂́w���R�т̕ې��̗͂D�ʐ��𗠕t����x�Ǝ咣�B���Ȃ́w�J�ʑS�̂��猩����͖����ł���x�Ƃ��Ă���B�v |
| �i��Z�Z�l�N��Z������t�������V���j |
|
|
| �@ |
�@���������Ȃ̂ł����A�s�����ǂ̗і쒡��"�j�t���тƍL�t���т̊Ԃɂ͒������ې��͂̍���n���ւ̐Z���\�̍��͔F�߂��Ȃ�"�Ƃ��Ă���̂ł��B
���X�͍L�t���̐X�ɂ���đn���A��܂ꂽ�y��𗘗p���Đ��������j�t���т������āA�y��ێ��͂ɂ��卷�Ȃ��Ƌ��ق��Ă����̂ł��B
�@�풆�A����ʂ��ēÎR���ɂ��^���̋}���i�����j�ɂ���ă_�����݂��n�܂�i������O�A�풆�܂ł͔��d�p�Ȃǂ̗����_���͂����Ă��A�^�����ߗp�̃_���Ƃ������̂͂قƂ�ǂȂ��Ǝv���܂��j�A���̌�����тƏ̂��čL�t���̂����������ʁA�R�̃_���@�\�͎����邱�ƂɂȂ�A�^�����p�����邱�ƂɂȂ�܂����B
���̂��߁A�R����̓y�뗬�o�͎��~�߂��|����Ȃ��Ȃ�A�㗬�Ƀ_�����Ȃ����n�̉͏���ł͓y�����͐ς��邱�Ƃɂ���āA�t�ɁA�^���̊댯�����������ƂɂȂ��Ă���̂ł��i���y��ʏȂ̌����ł̓_���ɂ���đS���I�ȃ��x���ł͉͏���͍�@�ɂ���āA�ނ���A�͏���͉������Ă���Ƃ���Ă���悤�ł��j�B����͂��̂Ƃ���ł��傤�B���ꂾ���_���������Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�������āA�_���Ȃ�����j���X�ɂ���Ĕ�������^�����ꎞ�I�Ɏ~�߂邽�߂Ɂi�����ɖ��܂��Ă��܂��̂ł�����n��̓y���Ǝ҂Ɏd����^�������Ă��邾���Ȃ̂ł��j�A���R�Ə̂��č��h�_������������A�����ݏȂ��������ЂƂ��ă_�����݂���ԉ�������Ɏ������̂ł����B
�@�L���ɂ́u�̃_���v�\�z�Ƃ���܂��̂ŁA���炭�L����w�̒������������Ȃǂ��֗^����Ă�����̂Ǝv���̂ł����A�і쒡�Ƃ��Ă͔F�߂����͂Ȃ����F�߂���Ȃ��g������ؐl���o�Ă����悤�Ȏv���ł��傤�B
�@���̖ڂ���́A���݂̗і�s���Ƃ������̂́A���͂⍑�Ƃ̂��߂ł��A���y�̂��߂ł��A�R�я��L�҂̂��߂ł��Ȃ��A�і�s���S���ҁA�X�ёg���E���A���ʓI�ɕ⏕������ыƎ҂⍻�h�_���A�ѓ����̑��̌��Ǝ҂̂��߂ɑ��݂��Ă���悤�Ɍ�����̂ł��B
�@���Ȃ��Ƃ��A"���������͐X����č��y�����ǂ��d�������Ă���̂�"�ȂǂƂ������A�v���オ��Ƃ����o�Ƃ������ʋ����Ō�����v�����݂����͂��낻�땥�@���Ă��炢�������̂ł��B
���ꂪ����"�ъw�Ȃ̂�"�ƌ����̂ł���Α���Ƃ��������悤������܂���B
�ނ��S�Ď�ɂ������Ƃ���ł����A�ނ�ɂ͔s���܂Ŏc����Ă����L���ȍL�t���̎R������`�����c���Ă���̂ł��i�������A�j�t���тɉ��|���ĕ��u���������A��قǑ����m���Ȃ̂ŁA��ɂ��Ă�����ɍ\��Ȃ��̂ł����c�j�B
���̂܂܂ɂ��Ă�����Ă͌܁A�Z�N�O�̋㌎�ɋ{��Ŕ��������悤�ȑ�K�͂ȐX�ѕ���i�y������Ƃ����ɂ͂��܂�ɂ��K�͂��傫�߂���A�S���{�̐��A�O���|�ꂽ�{��s�c��̊Ǘ����ꂽ�����L�̑��ђn�j���A������p�ɂɋN���葱���邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
���͂�A�^���ׂ����Ȃ��͂��ł����A�S���̑唼�̐j�t���т͑�K�͂ɓy���r�����A����I�ɕې��͂������A�R�ɂ����Ă��q�[�g�E�A�C�����h���͐i��ł���ƍl����ׂ��Ȃ̂ł��B
�@���ɐX�эs���A�і�s���Ɍg���l�Ԃ��u�R�d���͏����Đh���v�Ȃǂƌ����Ă��A�u����͂��܂��B�̂������v�ƌ��킴��Ȃ��̂ł��B
�@���͂�"�q�[�g�E�A�C�����h����"�͓s�s�������̖��ł͂Ȃ��̂ł��B |
| �@ |
| �ӔC�����Ȃ��c����s�� |
| �@ |
�@�q�[�g�E�A�C�����h���ۂ͊��ȏ��ǂƂł�����Ă���̂ł��傤���B
���������A�l�דI�Ɏ��R�����ς������ɂ���Ĉ����N�����ꂽ���R�̂����ؕԂ��ł���q�[�g�E�A�C�����h���ۂ��A������̂�����ʼn���̎����I�����������Ȃ����Ȃ̏��ǂƂ���Ă���Ƃ����̂����Ɋ�Ȋ��������܂��B
����͂Ƃ������Ƃ��āA���̈Ӗ��̒ꗬ�ɂ́A�ǂ������̌��ۂ�"�����B�̐ӔC�ł͂Ȃ��A�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��V�ЂƂ��ُ�C�ہi����͓�\�ܔN�Ƃ��O�\�N�Ɉ�x�����Ȃ��悤�Ȍ��ۂƂ����������̂ł����j�Ƃ��������ʂő����Ă���̂ł͂Ȃ���"�Ƃ�����ۂ�����̂ł����A����͎��̊����ɂ����̂ł����Ȃ���ʓI�ɐ����ł��Ȃ����̂ł��B
�����A�����ł��Ȃ���A����قǐ[���ȃe�[�}�ɑ��āA�u�ł�������v�ȂǂƂ�������قnjy�����o�̋C�y�Ȃ��Ղ葛�����ł���͂����Ȃ��Ǝv������ł��B
�@���Ƃ��A���y��ʏȂ͎����Ȃǂ��d���ł���A�����J���Ȃ͈��肵�ėǎ��̐����������邱�Ƃ��d���ł��傤�B
�܂��A�і쎖�Ƃ͔_���Ȃ̎d���Ƃ���Ă��܂��B���Ȃ͎��ۂɉ�������Ă���̂���̓I�ȃC���[�W�����N���Ă��܂���B
�@���炭�A���y��ʏȂ͎����B������Ă������Ƃ��q�[�g�E�A�C�����h�̍ő�̌����ɂȂ��Ă��鎖��S�����o���Ă��Ȃ��ł��傤���A�X��_�n������Ă����ƐM������ł���_���Ȃ��A�q�[�g�E�A�C�����h�̈ꕔ��S���ł���Ȃǂƌ�����ƁA�u����n���ȁI�v�ƌ������ł��傤�B
�Ƃ肠�����A��s�s�ɂ����Ă͐�O�ɂ����Ȃ萅���͍s���n���Ă����킯�ł�����A�q�[�g�E�A�C�����h�ɂ͑傫���֗^���Ă��Ȃ����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl�����Ɛӂ���Ƃ��Ă��A�J������ꂳ�����Ɉ�C�ɗ������鎖���Q���ɂȂ�Ƃ͑S�������o�������͂��ł���A���Ɉꕔ�ŗ������Ă���D�G�Ȋ����������Ƃ��Ă��A���ꂪ���݉����Ȃ�����A�����ĐӔC�Ƃ���Ƃ����������ɂ͓����Ȃ������͂��ł��B
���ǁA����͔ނ�̏��ǂł͂Ȃ�����ł��B
���炭���݂܂ł̓s�s�͐�≺�����̐����̓q�[�g�E�A�C�����h���ۂ��A�܂����������ĂƂ������ȋC�ۈٕςƂ��������x�ōς܂���Ă������ォ��̉�����ɍs���Ă��������̎��ł����Ȃ��A�ڂɌ����Ȃ��悤�ɏ��X�Ɉ����N��������K�͂Ȋ��j��́A�߂Ƃ�������Ȃ���A����̎���ł��Ȃ��ƍl���Ă��邱�Ƃł��傤�B
�@�{���A���Ƃ͂��̂悤�Ȏ��ɑΏ����邽�߂ɍ������x�����A�Y�I�ł����Ă��A�D�G�Ȑl�ނƂ��Ă̊������ق��A�w���̂���Ȋw�҂⌤���҂��ێ����Ă���͂��Ȃ̂ł����A���ƌ��͂ɋ��͂��邾���̌�p�w�҂⍑�Ƌ@�ւ̌ʓI�ȏȉv�����ɕ�d����w��������ƍl����悤�Ȃ܂�Ȃ��l�Ԃ������d�p����悤�ɂȂ�ƁA���͂�N��l�{���̎����������A���������A���̂悤�Ȏ��Ԃ��̂��Ȃ������Ȕj��������炷���ɂȂ�̂ł��B
���ǁA�Ō�ɋꂵ�ނ͔̂ނ���܂ލ����Ȃ̂ł��B
�@��s�s�ł���A�_�n�ł���A�R�ł���A�n�\��n���ɖL�x�Ȑ������肳������A�M����ꂽ���͋C�����鎞�Ɏ��ӂ�����M�Ƃ��ĔM��D���n����p���܂��B
����ɒn�\�ŔM����ꂽ��C�͌y���Ȃ萅���C�Ƌ��ɍ���ɏオ��A�����ŗ�₳��ĔM����o���A�����C�͉J�Ƃ��Ēn�\�ɖ߂���͂�₵�܂��B
���l�ɋ�C����₳��ė₽�����~�C���ƂȂ��Ēn�\�ɖ߂��Ă���̂ł��B
��C���i�㏸�C���j�̋�������ɍ��C���i���~�C���j������Ɨ������Ȃ鎖�͊F���o���I�ɒm���Ă��鎖�ł����A��������l�̌��ۂȂ̂ł��B
�@�����A���{�͊C�Ɉ͂܂ꂽ�ג������y�ƕ��G�Ȓn�`�������A���̉e�����₷�����߂ɉe������r�I�ɘa����Ă���̂ł��B
�����ɂ����Ă��傫���p�����������p�̂������ŎܔM�̒n�\�ɂ͂Ȃ炸�A�j�ŏI�i�K�܂Ői��ł��Ȃ��̂�������܂���B
���R�ɂ��A����̓ߔe���O�Z�����x�Ȃ̂ɓ����ߕӂ��l�Z���Ȃ̂́A���肪�C�ł��邩��Ȃ̂ŁA���ꂾ���ł��b�n�Q���g���_���f�}�ł����Ȃ����Ƃ����炩�Ȃ̂ł��B
����Ƃ��A����͂b�n�Q�̔Z�x���Ⴂ�Ƃł������̂ł��傤���H
�@�܂����A���̂悤�ȕ����w�̊�b�I�Ȓm�����Ȃ��A�y�����m��Ȃ��y�����c�����x�̓������Ȃ��l�Ԃ������Ȃ��Ƃ��v���Ȃ��̂ł����A���y��ʏȂ̐l�Ԃɂ��q�[�g�E�A�C�����h���ۂɊւ���Ɠc������ߓ��M�����̒����Ȃǂ�ǂ�ŗ~�����Ǝv�����̂ł��B |
| �@ |
| �^�R�}���̋��P |
| �@ |
�@�u�y�����m��Ȃ��v�ȂǂƔl�|�������y��ʏȂ̋Z�p�����̒N������m���Ă���͂���"�^�R�}���̋��P"�Ƃ����L���Șb������܂��B
�@����́A���l�Z�N�A���O�����V���g���B�ɑ���ꊮ����������̃^�R�}���Ƃ����݂苴���A�͂���ろ/���̕��ɂ���Ĕ�����������U���i�Q��U�j�ɂ���ėh���Ԃ��A���݁A����A�u���Ԃɕ��Đ�ɗ��������Ƃ��������Ƃ��Ă͗\���������������v��A�\����̎��s�Ƃ���Ă�����̂ł����i�v�Z��Z�Z��/���̕��܂ł͑ς�����Ƃ���Ă����̂ł��j�A���̌ケ������P�Ƃ��āA���勴�ł͕��ɑ��铮�I�Ȉ��萫���l�������v���s���悤�ɂȂ�A���̎�̋�������́A�Ȍ�A�������Ȃ��Ȃ����Ƃ���Ă��܂��B
�@����͂��̋����傫���h��������Ă����ߒ����N���ȉf���ŋL�^����Ă��邱�Ƃ�����A�����v�ł͔��ɗL���Șb�ł��B
�@���s�́A���ꂪ���s�ƔF������鎖�ɂ���ċ��P�ɕς��A���ǂ���P�Ɍq���鎖�ɂȂ�̂ł����A���y��ʏȂ͂��Ƃ��A���Ȃ܂ł����q�[�g�E�A�C�����h������̐ӔC�ƔF�����Ă��Ȃ�����A����Ƃ���s�s�̔M�Ђ͑����A�����͋�a�����܂���Â��鎖�ɂȂ�ł��傤�B
�@���āA�X�тɌb�܂ꂽ�X�y�C���͑�ʂ̖؍ނ��o���A�C�������̑�͑��i�A���}�_�j�萢�E�̊C�𐧔e���܂������A�Ղɂ͍����������c��A��s�}�h���[�h�͋C���܁Z�x�ɂ��Ȃ�ܔM�̊����s�s�ɕς��͂āA���͂𗎂Ƃ������ɖv�����܂����B
�@�ΊD�Ɍb�܂�L���ȐX�т����������{���A��ʂ̃Z�����g��R���N���[�g�Ōłߑ�����R���Ȃ��"�Ȃ炸���̏W�c"�Ƃ��Ă̓y�����͂ݏo���A���Ӗłы��鎖�ɂȂ�ł��傤�B�����āA�����悤�ɎܔM�̊����s�s���c�����ɂȂ�̂ł��B |
| �@ |
| �Ō�� |
| �@ |
�@"���g����J���ׂ���"�ǂ����͒u���Ƃ��Ă��A�������\�N�]��A����ő̊����鉷�x�����X�ɏ㏸���Ă��鎖�͊ϑ����ʂɂ���Ă��A�܂��A���������ɂ���Ă��F���ł��邱�Ƃł���A���ꎩ�̂�ے肷��l�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@����A��s�s����ł͂Ȃ����{�̍��y�̑唼�Ńq�[�g�E�A�C�����h���ۂ͌��I�Ɋg�債�Ă����ƍl�����܂��B
�@���̂��߁A�����ɐi�s���Ă��鉷�x�㏸�Ƃ�����̌��ۂ��l���鎞�ɁA��ʓI�ɂ͂��̉��x�㏸���ǂ���ɂ���Ĉ����N������Ă���̂��A�܂��A���̎傽�錴�����ǂ���ɂ���̂��Ƃ��������ɂ��ẮA�v�ʓI�ɕ������鎖�͔��ɍ���Ȃ��ƂȂ̂ł��B
�@��s�s�A�n���s�s�ɏZ�ݔM�і�ɋꂵ��ł���唼�̏Z���ɂƂ��ẮA�������͂����ăq�[�g�E�A�C�����h�ɂ���ċꂵ��ł���̂��A�b�n�Q�ɂ��n�����g���ɂ���ċꂵ��ł���̂��H�Ƃ������Ƃ�������͗����ł����ɍ�����Ԃɂ���悤�Ɍ����܂��B
�@��_���Y�f�n�����g�����i���g���͎����Ƃ��Ă���_���Y�f�̑����ɂ���Ă��ꂪ�����N������Ă���Ƃ����̂͌��Ƃ����ȏ�Ƀf�}�ƍl���Ă��܂��j�Ɋ�Â��\���ł́A���ϋC�����Q�`�S���㏸����Ƃ��Ă���̂ł����A���ϋC���̏㏸�Ƃ��Ă��A���݁A��s�s���ŋN�����Ă��鉷�x�㏸�́A���̒��x�̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ����������ǂȂ������������Ǝv���܂��B
�]���āA���݁A��s�s�ɏZ�ސl�Ԃ��ꂵ��ł���v�f�̑����̕��������y��ʏȂɑ傫�ȐӔC������s�s�̊������ɂ��q�[�g�E�A�C�����h�ɂ���A�قƂ�ǒn�����g���ɂ����̂ł͂Ȃ��ƍl����ׂ��Ȃ̂ł��B
�@�s���́A�����O�A�l�\�N�ő�K�͂Ɏ�������Ă����s�s�̐��z�̕ύX�ɂ�葽�����n�߁A������Ԃ������Ȃ��܂łɏ�ԉ������Ă��܂����l�דI�ȃq�[�g�E�A�C�����h���ۂ�I�ɏグ�A�����������ΔR���̑�ʏ����G�A�R���̑�ʎg�p�ɂ��s�s�̔p�M�Ȃǂ̉�����ɂb�n�Q�n�����g�������݂��Ă��邩�̂悤�ɕ`�����Ƃ��Ă���悤�ł��B
�J�Ԃ��ɂȂ�܂����A�q�[�g�E�A�C�����h���ۂ͐��z�̐ؒf�ɂ��M�z�̕ϒ����Ǐ��I�ɔ������ċN���Ă�����̂ł���A�n�����g���Ƃ͑S���W���Ȃ��̂ł��B
�܂��A"�b�n�Q�n�����g�����А�"�͌��q�͎Y�Ƃ�����̑����̂��߂Ɏ����������ȃf�}�Ȃ̂ł��B���x���������Ƃł����A��_���Y�f�͉��g���ɂ���ĊC���������C���ɕ��o����Ă���̂ł����āA��_���Y�f�̔Z�x���オ���Ă��邩�牷�g�����Ă���̂ł͂Ȃ��̂ł��B
�@�u�������l����v�g�����̉Ȋw�I������_����h�Ƃ����z�[���E�y�[�W�̊Ǘ��҂ł���ߓ� �M�����̐V���u���g���͗J���ׂ����Ƃ��낤���v�b�n�Q�n�����g�����А��̋��\ �ߓ� �M���i�s�m�Ώ��[�j�ɂ����Ă��q�[�g�E�A�C�����h�Ɋւ��镔��������܂��̂ŁA���̈ꕔ���Љ�Ă����܂��傤�B |
| �@ |
| 3-3�@���z�̔j�����炷������ |
| �@ |
| ���z�̔j��́A�h�{�z�̒��ړI�Ȕj��Ƃ����ڂɊW���Ă��܂��B |
| �@ |
| �_�Ƃɂ�鍻���� |
�@�X�т̂��Ċ����_�@�i�����n�ş����s��Ȃ��_�@�j�ɂ���K�͔_�n�����A�n�\�����������̏����ʂ��������܂��B��K�͂ȏĔ��ɂ��_�n�̊m�ۂ������ł��B�����n�̟�ꂽ�_�n�ł͍L�͈͂ʼn��Q���������Ă��܂��B�܂��A���w�엿�̑����ɂ���ēy��̒c���\�����j��ĕې��\�͂��ቺ����A�����̉J�ŗ{����������邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�����̔_�n�͂₪�čk��s�K�n�ƂȂ��ĕ������ꍻ���ƂȂ�܂��B��U����������ƁA���z���˂ɑ���n�\�̔��˗����傫���Ȃ�A���̏����ʂ����邱�ƂƂ̑�����ʂō������͈��肵�������тƂȂ�A�܂��܂��J���~��Ȃ��Ȃ�܂��B |
| �@ |
| �s�s�ɂ�鍻���� |
�@�s�s���̐i�s�ɔ����āA�s�s���̒n�\�͕s�������ɂȂ��Ă��܂��B�~�J�͒n�\�ɂ͐Z�������A��K�͉�������ʂ��ĒZ���ԂŊC�֎̂ċ����܂��B�l�����x�̍����s�s��{�����߂ɉ��u�n�ɗp���_�������݂���A���D�I�ɓs�s�ɋ������s���邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�_���ɑ�ʂ̐��𗭂ߍ��߂ΐ������������A�_�������̉͐여�ʂ��������܂��B�������ă_�����ݒn���ӂ̐��z�͔j��A�����ɐ��Ԍn���j��܂��B����ȃ_���͋�C���ɑ�ʂ̐����C���������邱�ƂɂȂ�܂��B�����C���܂�Ōy���Ȃ�����C�͏㏸�C���ƂȂ�A����Ɏ��ӂ��琅���C���܂�C���z���邱�ƂɂȂ�܂��B�������ӂ��������n�тł���A�������̐i�s���������邱�Ƃɂ��Ȃ���܂��B
�@�_���`�A����ɂ�鎡���V�X�e���́A��ʂ̉J���𑬂₩�ɊC�֗������邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ł��B�͐�f�ʐς�傫�����A�֍s�����͓����I�ɕύX���ē������z��傫������Ƌ��ɁA�͓����R���N���[�g�Ŕ핢���邱�Ƃŕ\�ʑe�x�����������܂��B���������\�����͒���n�Ƃ̐��z�ƕ����z���Ւf������̂ŁA���̌��ʂƂ��Đ��Ԍn�̉h�{�z�͕n��Ȃ��̂ɂȂ�܂��B |
| �@ |
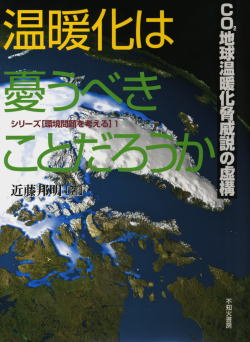 |
|
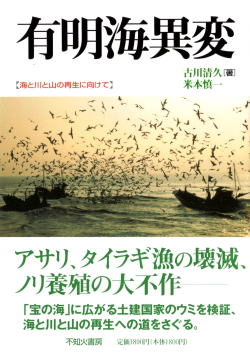 |
| �u���g���͗J���ׂ����Ƃ��낤���v |
|
�u�L���C�ٕρv |
| �ߓ� �M���i�s�m�Ώ��[�j |
|
�Ð� ���v�@�Ė{ �T��i�s�m�Ώ��[�j |
|
| �@ |
| �s�m�Ώ��[ |
��810-0024 �����s���������3-12-78�@��092-781-6962 |
|
| �@ |
| �w�b�n�Q���g�����͊Ԉ���Ă���x�@�Ɠc �֒��@�̂����E |
| �@�u���g���͗J���ׂ����Ƃ��낤���v�b�n�Q�n�����g�����А��̋��\ �ߓ� �M���i�s�m�Ώ��[�j�͍D���̂悤�ł����A��s���ďo�ł���Ă���Ɠc �����̐V���ɂ��ꕔ�ł����A�q�[�g�E�A�C�����h���ۂɊւ���L�q������܂��̂ł��Љ�Ă����܂��B |
|
| ����n���ɑ��݂����C�̏z�ł́A���͒n�\�̔M�ď������đ�C�������ɂ���B���̎�����C�͒n�\����̓`�M��������B���̂悤�ɂ��Ď�����C�ƂȂ��ď㏸���A�n�\���瓾���M�R�O���C���ɉ^�яグ�A�����ł��̔M���F���ɕ��o���ė�p����A������C�Ƃ��ĉ��~����Ƃ��������z�ɂȂ��Ă���B��������C�́A���̂悤�ɉ��g���K�X�ł����Ă��b�n�Q�Ƃ͈Ⴂ�A�n�\�Ƒ�C�ɑΗ��������N�����A��C���p���铭�������邱�Ƃ͏d�v�ł���B���́u����v�Ɓu���v�@�\���A�n�����Q����J���n�i63�ŎQ�Ɓj�ɂ��A�����̑��݂������Ă���̂ł���B��� |
| �@ |
| ����s�s�̏����Ȃ錴����s�s�̔��M�ʂ̑傫�������ɋ��߂�l�͑������A���˗�p�A���A����Ƃ����@�\���������肵�Ă���A�ȒP�ɏ��M����邩����ł͂Ȃ��B�Ƃ��낪�A�����̗�p�@�\���������s�s�́A���������ܔM�n���ɂȂ�̂ł���B��� |
|
|
|
�ڂ����͓�����ǂ�ł��������B
�w�b�n�Q���g�����͊Ԉ���Ă���x�@�Ɠc �֒��@�i�ق���o�Łj |
| ������ ���_�� �@�����s��������3����21�|10 �@��03-3947-1021�@�^ 1,200�~ |
| �@ |
| �@���e�͎��ɖ����ł��B��ʂ̓ǎ҂�Ώۂɕ�����₷��������Ă��܂��̂ŁA���̂悤�ȑf�l�ɂ��N���A�[�ȃC���[�W���X�g���[�g�ɓ����Ă��܂��B�Ɠc�����A�ߓ��M�����̒����ɂ��Ă͐��m�ȃR�����g������\�͂�����܂���̂ŁA�ڂ����͋ߓ��M�����̃T�C�g��ǂ�ʼn������B |
| �@ |
| �M�@�� �i�ł���������A�R���N���[�g�������������I�j�@ |
| �L���C�E�|���p���|�[�g�ҏW���@�Ð쐴�v�i�������̐E���j |
| �@ |
| �M�@�́i�l�b�J�j |
| �@ |
��������ɑn��o���������̂��̂ł����A�q�[�g�E�A�C�����h�̈Ӗ���������������Łu�M�Ёv�i�l�b�J�j�Ɠǂ݂܂��B
�@"�l�b�J"�ƌ����A�������F���ς���x�ߎ��ς̓D���Ɉ������荞�܂�邫�������ƂȂ������F�i���j�̈�ȁA�M�͏Ȃ������čs��ꂽ�u�M�͍��v(*)���v���o���Ă��܂��܂����A����ɂ��ď����n�߂ẮA�ŏ�����E���ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�@�����A�s�킩�玵�\�N���o�āA�ЂƂ�悪��̍��y��ʏȂ̊����ɂ���Ă����炳�ꂽ�q�[�g�E�A�C�����h�Ƃ������̐V���Ȕs��i�������ւ�ЉЂ�s��ƌ����Ȃ�j���v�����A�u�M�Ёv����u�M�́v���v�������ׂ鎖�ɑS���K�R�����Ȃ���ł��Ȃ��̂ł��B
�@�܂��A�q�[�g�E�A�C�����h���ۂ͐l�Ԃ̎�ł͂ǂ����悤���Ȃ��V�ЂƂ��ُ�C�ہA����ɂ͓V�ϒn�قƂ����������̂ł͑S���Ȃ��A�������\�N�œ��B�������y��ʏȂ�擪�Ƃ��鍑�Ƌ@�ցi�_���ȂȂǁj�̖\���i���Ă̕����͂▴�c���@��Ƃ������A���������N���������R�̖\���j�ɂ���Ă����炳�ꂽ�l�ЁA���ɂ�鍑�y�A�������̌���I�j��ł����Ȃ��̂ł���A���̖��\�ɂ܂�Ȃ����Ƌ@�ւƂ��������ƍ��y�ւ̓G�Ύҁ������ɂ���Ĉ����N�����ꂽ���̔s��ɓ��������̂Ȃ̂ł��B
�@"��"��"�킴�킢"�ł���A�S�̂Ȃ��Ɓi���U�j�̃n�q�����肳�܁@�̂��Ƃł����A�l�ԂƂ����������y��ʏȂ̂����炵���Г�̂��Ƃ��Ӗ�������̂Ǝv���Ă��������č\���܂���B
�@����͂Ƃ������Ƃ��āA�O�i�́u"�ł�������"�̑�Ԕ����v���q�[�g�E�A�C�����h���̑��_�Ƃł������ׂ����̂ł��������ɑ��āA����́A���y�̍Č��Ɍ������e�_�ɂȂ���̂ł���A����ɉ����b�Șb���������Ǝv���܂��B |
| �@ |
| �M�͍�� �F |
���F���͖��F���ςɂ�蒆�����k�O�ȁA���Ái�M�͏ȁj�ɐ��������A���n���Ɓi���͖{���A���F�͖��F���̍��y�ł����Ċ����̂��̂Ȃǂł͂Ȃ��ƍl���Ă���A"���{��������N������"�Ƃ��������肫����̋c�_�ɒP���ɂ��݂��邱�Ƃ͂��܂���B���F�������̗̓y�ł���Ƃ����c�_�͗��j���L�ۂ݂ɂ���l�Ԃ̌������ł����Ȃ��A���S�����Ƃ����������I�ȈӐ}���������͎̏̂g���܂��j�ł����B���̔M�͏Ȃ̎�Ȃł������������h�̓��ʗفiij�ޮ��݁j�͒��w�ǂƒʂ��A�M�͏ȒD�҂̂��߂̍R���R��g�D���ĐN�����J��Ԃ��܂��B���̂��߁A���O�O�N�A�֓��R�͔M�͍������R�C�ւ��̂���Ɏ���܂��B���F���ς̌����ł������Ό��Ύ��͖��F���m�ۂ��鎖����`�I�ۑ�Ƃ��Ē�������z���Ē����{�y�ɓ���悤�Ȑ���̊g��ɂ͈�т��Ĕ����܂����i�R�C�ւ��z����ȁI�j�A���F�����ł���M�͂�����肹���A���̌�̖k�x���ςւƔ��W���Ă����̂ł��B
�@���̍��́A����ł͊֓��R�̋@����킪�}�ɂ������āA��\���ԂŔM�͏Ȃ�|��(�����Ƃ�)�������A�O�����{�A�������͂��߁A������d�v�֖���U������i�ɂȂ��Ē��������R�̊拭�Ȓ�R�ɂ����A�\�z�O�̋��𖡂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���̂��߂ɁA�퓬�͒�������z���āA�₪�Č�̂��i�O���Ɏ��{���{���A���ɖj�����ɂ�Ȃ�̂ł���B |
 |
| �u�֓��R�v�ݖ����R�̓Ƒ��@���c�r�F�i�u�k�Њw�p���Ɂj |
| �@ |
���@����A���B�̕\�L��"���F"�Ƃ��܂����B�O�q�̓��c�r�F�ɂ�� �u�֓��R�v�ݖ����R�̓Ƒ� �ɂ����Ă��A�\�L��"���B"�Ƃ���Ă��܂��̂ŁA�K�������S��K�v�͂Ȃ��̂ł����A�c���O�[�X�n�̖����ł���"�}���`�����A"�̕\�L�́A���ɐ����閯�Ƃ̔F������"���F"�Ƃ��ꂽ�̂ł���A�{���A���̕����������ƍl���邩��ł��B
�@�������Y�}�����͂��̖������ł����Ă����Ƃł��鐴���̑��݂��悵�Ƃ����i�����������ɂ���Ďx�z����Ă����j�A���ɐ������Ɨ����������̋L�������������ƍl���Ă��邩�̂悤�ł��B |
| �@ |
| ���������̏��� |
| �@ |
�@�\�N�قǑO���犴���Ă������Ƃł����A�����͈ӊO�ɗ������Ǝv���Ă��܂����B
����͂��̂܂ܗ��������Ǝ����I�ɂ͌���ɂȂ�Ǝv���̂ł����A"��s��̉Ă͏����Ă��܂�Ȃ�"�Ƃ���������ς������o�債�ēc�ɂ���o�ė������ɂ́A���A�͗����������p����̕����ɂȂ��Ă���r���̒J�ԂȂǂł͑u��������������ꂽ�̂ł��B
�@���͍���̕Гc�ɂ̒n���s�s�ɏZ��ł���l�Ԃł�����A�ĂɂȂ�Ǝ���ɂ��鑽���̐��c�ɂ͐��������Ă���܂��B
���̂��߁A�����������������͂̋C���͒Ⴂ�Ƃ��Ă��A���x�����ɍ��������������������܂��B
����A�R���N���[�g�Ōł߂�ꂽ��s��͎��x���ɒ[�ɒႭ�A���A�ɓ���Ό��\������̂ł��B
�ŋ߂͏��Ȃ��Ȃ�܂������A"�J���t�H���j�A�́A�C���͍������̂̃J���b�Ƃ��Ă��đu�����I"�ȂǂƂ������C������b�����Ă͗ǂ����������̂ł����B
���̎�̘b�����Ȃ��Ȃ�����́A�������̎���ł����ۂɂ��̂悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă�������Ȃ̂�������܂���B
�������A���̂��Ƃ́A�����㍂�������ƌ����Ă������{�^�C��̏����Ƃ������A�X���A�т������A��������s����̍Ŋ��̎p�������Ă���Ƃ�������̂ł��B
�@�F����͍����ł������������y�������܂����H���ꂪ�������ƍl���܂����H���ĉ��͌o�ρA�Љ�A�����̖ʂ���ł͂Ȃ��A���R���̖ʂł��}���ɐi�s���Ă���̂ł��B |
| �@ |
| �R���N���[�g�̃��C���E�R�[�g |
| �@ |
�@�s��R���N���[�g�̃��C���E�R�[�g�ɕ����Ă��邱�Ƃ́A���ɁA�u"�ł�������"�̑�Ԕ����v�ł�����x�����܂������A�ő�̃��C���E�R�[�g�ɕ���ꂽ��Ԃ́A�n���s�s�Ƃ������ׂ��n���X�ł��傤�B
�������A���̖��������o���ƍ������܂��̂ŁA�����ł́A�����������i�ނƉ��͗��扩�y�����̌����Z��̂悤�ɒn���Ő������Ȃ���Ȃ�Ȃ���������Ȃ��Ƃ��������Ă����܂��B
�@�s��R���N���[�g�ɕ����Ă��鎖�̃����b�g���l�����ꍇ�A�����o���̓y�͉J�ɂ���ė���o���܂��B
�s��̉^���ꂪ�A�ꎞ���R���N���[�g�����ꂽ�w�i�ɂ͓y��̗��o�ƁA���̓y�̕�[����̃R�X�g���Ԃ����ɂȂ�������ł��������̂ł����A����́A�����o���Ă��邩��ł����āA���{�̂悤�ȍ��������̓y�n�ł͕K������������A����̂ł�����A�����ۂ��Ă�������A����قǗ���o�����Ƃ͂Ȃ��̂ł��B
�@���͒��ԏ�Ƃ������ł��傤���A�Ԉ֎q�܂ł��l���Ĉ��ܑ̕��͂���Ƃ��Ă��A�S�Ă��J�̂��܂�~��Ȃ����[���b�p�뉀���ɕς���K�v�ȂǂȂ��̂ł����āA�����ɂ������ȗ��̉�������̎c�悪�����B�ꂵ�Ă��܂��B
�@���ɕܑ�����Ƃ��Ă����悤�͂�����ł������ŁA�G�A�p�����A�p���Ɠy���Ď{�H�����������A�����n���ɐZ������悤�Ɏ{�H���ăR���N���[�g�ܑ���K�v�ŏ����Ɍ��肷��Ηǂ������Ȃ̂ł��B
�@�����ɂ����܂����A���ɃR���N���[�g�Ŏ{�H�����Ƃ��Ă��債�����x�͂Ȃ��̂ł���A��A�O�\�N������Η��Ĕp�����ɐ��艺���菈�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@��������A�����t�~������肷��Ƃ��Ă��A�͂�Ă͐����A���N�A���N�A�V���ȗt��~���A��������J��a�炰��̕����͉i���ɂ��̂ł��B
����́A�����A�����A���ԏ�A�ǖʁA��[�ȂǑS�ĂɌ����鎖�ŁA�R���N���[�g�̕����Ȃǂ͕K�������K�v�͂Ȃ��̂ł��B
�ŋ߂ł͖ؐ��i�Ԕ��ށj�̃u���b�N������܂��̂ŁA���s�҂ɐh�������A���H�����ǂ��邱�Ƃ͌����ē���Ȃ��̂ł��B
�@���������A�A�X�t�@���g�͔M�e�ʂ��傫���A���Ԓ~�ς��ꂽ��ʂ̔M��ۂ��Ă���A��Ԃɂ��ꂪ���o����邱�Ƃ�����͂̋C���͈���ɉ�����܂���B
�z�[�����X�͂��̎���m���Ă���̂ŁA���H�ŐQ��Ƃ��Ă��~��̓R���N���[�g���̓A�X�t�@���g��I�Ԃ̂ł��B
�@���H�\���߁A�͐�\���߁A���z��@�A���̑��̕⏕���̋K���ȂǁA��͐l�Ԃ����߂����̂ɉ߂��Ȃ��̂ł���A�ǂ̂悤�ɂ��Ȃ�̂ł��B |
| �@ |
| ���H�œ����l�X�ɐl���� |
| �@ |
�@�^�Ă̓��H��Ƃقǐh���d���͂Ȃ��ł��傤�B
���̉��V���ōs����A�X�t�@���g�ܑ��̍�ƂɎ����Ă͌܁Z�x�ɂ��オ�邻���ł�����A���̐h���͑z����₵�܂��B
�����v�����Ƃł����A�ЂƂ����\��̐Ŗ������Ȃǂ�"�n���a����"�̌����������ꂽ���Ƃ�����܂������A���y��ʏȂ̐V�ăL�����A�����Ɍ���̎��Ԃ������邽�߂ɂ��A���H�ܑ��̌�ʐ����ł������Ă݂Ă͂������ł��傤�B
�܂��A�����Ńm�b�N�E�A�E�g�Ƃ͌���Ȃ��܂ł��A�܂��A�ꎞ�ԂƂ͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�������������A�̂́A�Ẳ��V���̒ނ������Ă͂����̂ł����A�\�ܔN�قǑO����ď�̐������͒ނ肩�犮�S�P�ނ��Ă��܂��B
�ʔ����Ȃ�����m�炸�A�����ʔ������Ȃ����V���̌�ʐ����Ȃǂł���͂�������܂���B
���ہA���̐h���댯�Ȏd����ǂ�������̂��Ɗ��S�����������܂����A�܂��A�J����@�ɂ͊��S�ɒ�G����ł��傤�B
�@�C�ۑ�ɂ���ē`������ō��C���Ƃ��������̂́A�S�t���̒��Œ��˓�����������Ȃ�����̂�����x�̂���ꏊ�ł��鎖�����ʂł�����A���˓�����������A�r�C�K�X�ƁA�R���N���[�g�Ȃǂ���̏Ƃ�Ԃ��ɔ������j�ꂽ���̘H�ʂƂ͑S���قȂ���̂Ȃ̂ł��B
�@�����܂ł��s�K�v�ɃA�X�t�@���g�����ꂽ�^���ȘH�ʂō�Ƃ���y�؍�ƈ��A��ʐ����v���ɂƂ��āA�J�⋭���͂��ꂱ���V�̌b�݂Ɏv����ł��傤�B
�܂��A�����̒n�\���x�A�̊����x�Ƃ������̂͌܁Z�x���z���Ă���͂��ł���A�l���̖ʂ�������V���̓����ł̍�Ƃ͋֎~���A���q�͎Y�ƂȂ݂̊댯�Ɩ��Ƃ��ĒZ���ԁA�Z���̌�㐧�A��ƒ��ł��p�ɂȌ�㐧��~���ׂ��ł��傤�B
�@�ŋ߂͌�ʏa������邽�߂Ə̂��Ē������A�����Ԃ̖�ԍ�Ƃ��s���Ă��܂����A���ۂɂ͍�ƈ����Ή��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��鎖�����f����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv������ł��B |
| �@ |
| �b�x��@�g�i���ɑ������H�H���ɂ��ʍs�����h |
| �@ |
�@���X�g���̖����ƁA���Ǝ҂̌��������Ɉ��������Ĕ������Ă��频�ʂ̎��E�ң���ƒ�������ĐV���Ȗ��Ƃ��Ă̎�N�J���҂̖��A�J�i�t���[�^�[�A�j�[�g�A�v���[�E�z���C�g�j�̊g��B
�@�Ƃ肠���������Ă����Ă���l�X�͎���̍K���Ɉ��g���Ă��܂����A���̔ނ�����͋ɂ߂ĐƎ�Ȋ�b�̏�Ő������Ă��邱�ƂɊ��ɋC�Â��Ă��Đg�ׂ̍�v�������Ă���悤�ł��B
�@����قǖ��O���ꂵ��ł���ɂ��S��炸�A��s�ɂ͖��V�O���������сA�n���Ƃ����ǂ������ꏭ�Ȃ��ꂻ�̎�̖��Ӗ��Ȍ��������O�����������Ă��܂��B
�@�헐�̒��ł̘b�ł����͑S���قȂ�̂ł����A���m�̗����A���s�̖��O���]���ɂȂ��Ă��܂����B�H�����̂Ɏ������o�^�o�^�Ɖ쎀���Ă��܂����B�������A���̑O��A�������R�͗B�̕ʑ��Ƃ��Ă̋��t���A��t���c���\��a�̂ɔM�����Ă����̂ł��B���̊ԁA�J�ʼn��l�����̂����A�S���C�ɂ������Ă��Ȃ������悤�ł��B
�@���������A���̍��܂ł́A�u�̗L�v�Ƃ����l���͂����Ă��A�u�{���v�Ƃ������l���͑S���Ȃ������̂ł����āA�����̎��A�n���Ƃ��������̂Ɂu�o�ς��ǂ����邩�v�Ƃ��A�u���O�̐������ǂ�����悢���v�Ƃ������ϔO�͑S������͂��܂���ł����B
��l���R�`�������`����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂�������܂���B
�@�u���オ�����v�Ƃ��A�u�䐭�����Ȃ��Ă��Ȃ��v�Ƃ������l���́A�����炭�]�ˊ��̖��{�a���ȍ~�̂��Ƃł����āA���̍��܂ł̐������͂ɂ́A���悻�u�����v�Ƃ��������o�͂Ȃ������悤�Ȃ̂ł��B
�@�Ƃ���ƁA�ނ�͉�������Ă����̂ł��傤���B
����͒P�ɕx�����D���A����Ă��������������̂ł��B
���ǁA�����̌��̖͂{���͂��ꂾ���������̂ł���A�ȗ������Č����A���l�̐��ݏo�����x�����D���Ă��������������̂ł��B
�@�ł́A����̌��͂͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���B
�Ⴆ�Ό����H���Ƃ��������̂�����܂��B�m���ɁA�K�v�s���ȃC���t���Ƃ��Ă̓��H�̕�C�␅���ǘH�̕�C�����C���^�i���X�Ƃ��������̂́A���ꂪ�u�K���v�ɍs����͈͂ɂ����Ă͖��O�̂��߂̂��̂Ƃ���������ł��傤�B
�@�������A�K�������u�K���v�ɍs���Ă���킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�N�������ɂ����m�̂Ƃ���ł��B���͂�����H���̋㊄�����k���ɂ����̂ł��邱�Ƃ́A�u�N�����m���Ă��āA�m��Ȃ����Ƃɂ��Ă��邾���v�̌��R�̔閧�ł�������܂���B
�]���āA�S���K�v�̂Ȃ��]�����\�Z�������č��ɂɕԊ҂���邱�Ƃ͖����A�n�����g�̔����̂��ƂɊ��S������O��ɒn��̓y�����ǂ��ɗ������ނ����̕s�K�v�Ȏ��Ƃ��s��ꑱ���Ă��܂��܂��B
�Ƃ����̂́A���������Q���\�������ɋ��łɂł��������Ă��邩��ł��B
���̍\���Ɩ��W�ɂ͒������A�n�������͂����݂ł��Ȃ��Ȃ��Ă���A���R�ɂ��̍\���̕s�f�̑��B�Ɏg���Ă��܂��Ă���̂ł��B
�@���H�ܑ��Ƃ����A�h���C�o�[�Ȃ�ΒN�ł����^��Ɏv�������H�������݂��܂��B
�{���A�ܑ��H���Ƃ������̂́A�Ԃ����S�ɒʂ��悤�ɁA�ʂ�Ղ��悤�ɂ��邽�߂ɍs����͂��̂��̂ł��B
�������A����͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�Ƃ����ƁA�K�v���Ƃ��������Ƃ����������̂Ƃ͖��W�ɕܑ��v�悪�����Ă��Ă���A�\�Z�͑O�N�Ɠ����x�ł���A���R�̔@�����܂肫�����Ǝ҂��������Ă������ƂɂȂ��Ă���̂ł��B
����́A������A�y�����̌Œ苋�Ƃ��������̂ɑ������܂��B
����Ɍ����A�O�N�Ɠ����x�̗\�Z�ł���Τ�H���ɂ��a�͑O�N�Ɠ����x�ł���A�����������S�ɃX���[�Y�ɒʍs�ł���悤�Ɉێ��Ǘ��H�����s����ׂ��ł���̂ɤ�ړI�Ǝ�i������ւ���Ă��܂��Ă���̂ł��B
�@���b������܂��B�u�Ȃɂ䂦�ܑ��H�����J��Ԃ����̂��Ƃ����ƁA����ܑ͕��H�������邩�炾�v�Ƃ����̂ł��B
�܂�A�S���œ��H�H���p�̑�^�_���v�g���b�N��d�@�^���ԗ����ʂ邩�炱���ܑ����ɂ݁A���x�����ւ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����āA���ʂȓ��H�H�������Ȃ���A�ܑ��H��������قǂ̃s�b�`�ł��ւ���K�v���Ȃ��̂ł��B�܂��A����͏�k�̗ނł����B |
| �@ |
| �܂����]�[�g�J���̕����܂��� |
�@�h���C�o�[�ɂƂ��ĕ�������������̒ʍs�~�߂Ƃ������܂��܂ŕt�������H�ܑ��Ƃ����i�v�ɑ����������Ƃ�����܂����A���炭�ߏ�ɂ����߂��\�Z�����S�Ɉ��ݍ��ލ\�����������Ă���A�ܑ��̉��C�ȂǕK�v�����Ȃ����H���H���ɉꑱ���Ă���̂ł��B
�@�܂��A���̎�̎��Ƃ͐V���Ȋ��j���Ȃ��������܂��Ȃ̂ł��B
�@�������Ƃ����̎�̈ێ��Ǘ����ƂɌ��肵�A�{���ɕK�v�Ȃ��̂�����K�v�o����ł���čs���A���炭���̎�̎��Ƃɑ���o��͔�������O�����x�܂łɂ͍팸�ł���͂��ł����A���͉i�v�ɉ��ё�����A�V�����A�������H�A��ʍ����̉��C�A�_���A�`�p�H���A���h�A�ѓ����ݥ���̕��ł��傤�B
���]�[�g�J���̕��͌o�ό������ѓO���Ă��܂�����A�ׂ���Ȃ��ƂȂ�ƁA�f�B�x���b�p�[�͒����ɓP�ނ��A���̎��_�Ŏ��Ƃ͎~�܂�̂ł����A�����H���̕��́A�ׂ��낤���ׂ���܂����A���ɗ��Ƃ������܂������\���Ȃ��Ȃ̂ł��B
���ǁA���]�[�g�J���̕����܂����ƌ�����̂ł��B
�@���ɁA�y�Ɋւ���������Ɣ���팸���A�{���ɕK�v�ȕ���ւ̓������K�v�ɂȂ��Ă���͂��Ȃ̂ł����A���܂��ɓy�؍H���͉i�v�ɑ��������ɂ���܂��B
�@���̂悤�ȕs�K�v�ȓy�؍H�����~�߁A�{���ɕK�v�Ȏ��Ƃɗ\�Z�Ɛl�I�������Ĕz�u���邱�Ƃ��v������Ă���̂ł����A�ł��K�v�Ȃ̂͂��̃V�t�g�ύX�̐U�������ł��傤�B
�@�܂��A�_���ɑ͐ς𑱂���y���̉��C�ɂ��̐A�̍��̍팸�A�����c�𗘗p�������R�^�V���n�̌��݁A�R���N���[�g��݂��r�I�g�[�v�E�^�C�v�ɕς���A�j�t���т��������čL�t���тɕς��饥��Ƃ�������������܂����A�܂��A������������Z�p�̂Ȃ��Z�p�n�E���̍Ĕz�u�̖�肪����܂��B
�ނ�͌��X���Y�I�ȘJ���ɏA���Ă����ł͂Ȃ��A�ŋ��Ɋ��Ă��邾���ł����āA�����������ɗ����Ă���킯�ł͂Ȃ��A���Ɏd�������Ȃ������Ƃ��Ă��������s���v���邱�Ƃ͂���܂���B
�ނ���A�d���������č���̂͂���܂Ō����H���ɂ�����Ă������ݘJ���҂̕��ł��傤�B���́A�V�t�g�̕ύX����������܂ł̊��ԁi�܁`�\�N�j�́A���Ԃ̍ЊQ�~�����Ƃ������g�D
�ɍĕҐ����A�V���ȐE�ƌP�����s���Ȃ���O���i�����j�`�Z���i�ꑮ�j���x�̏����ۏ���s���Ηǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�ߏ�J���͂̎Y�ƍĔz�u�͋}���ł���A������Ȃ��y�؍H�����J��Ԃ��Ă���]�T�͈�Ȃ��͂��Ȃ̂ł��B |
| �@ |
| �y���ɂȂ�ƍ~���Ă���J |
| �@ |
�@�ЂƂ���A"�y���ɂȂ�ƉJ���~��"�Ƃ��������Ƃ������Ă��܂����B
�������j�ގt�̒[����ł�������A�J�╗�ɂ͕q���ł����C���܂킵�܂��B
��Q�҈ӎ�����`���Ă��A�m���ɂ��������������������Ă��܂����B
�������A���ł͂��ꂳ���������Ă����Ƃ������C�����Ă��܂��B
�@���́A"�y���ɂȂ�ƉJ���~��"�Ƃ����A�ɂ킩�ɂ͐M�����Ȃ��悤�Șb�́A�C�ۗ\��m�Ȃǂ̊ԂŚ�����Ă������̂̂悤�ł����A��������s�s����ł͂Ȃ��A�n���̓s�s���ɂ����Ă͂܂���̂ƍl���Ă��܂��B
���R�Ȃ���{���̎��R���ۂł͂Ȃ��̂ł��B
�@��ʓI�ɐl�Ԃ̊����͏T�P�ʂōs���܂��B
�y�A���A�Փ��ɓ��������l�Ԃ������Ă���͎̂����ł����A�ʏ�A�Y�Ɗ����͌��j������j�ɂ����čs���A���̌��ʁA�J�����Ȃ���Α�C���̕��V���o�ʂ��ł���������̂��I���ɂȂ�ƍl������̂ł��B
�@�͕̂��C���ϐ������g�[�������d�ɗ����Ă����̂ł�����A��C���ɂ͉����Y���A������Ì��j�Ƃ��ĕ��̖������͒������ǂ��o�����̂ł��B
������͂��̂悤�ȗD��ȕ��i�͉ߋ��̂��̂ł��B
�@�ŋ߂͍H��̂����i���̌��t������ɂȂ����܂����j�������Ă��܂�����A����̋Ì��j�Ƃ́A�������߃f�B�[�[���ԂȂǂ̔r�K�X���o�ɂȂ�ł��傤�B
�@���̑�C���ɕY�����o�ʂ��ł��傫���Ȃ�̂��T�����Ƃ���ƁA�T���ɂȂ�ƉJ���~��₷���Ȃ�̂͗ǂ������ł���̂ł��B
��U�A�J���~��A�J�ƂƂ��ɑ�C�����畲�o���n�\�ɐ��Ƃ����̂ł�����A�Ăѕ��V���o���~�ς����܂ł͉J���~���Ȃ�Ƃ�����ł��B
���ꂪ�Ȋw�I�ȕ��͂ł��邩�ǂ����̔��f�͓ǎ҂ɂ��C������Ƃ��āA���̌��ۂ������ǂ�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����̍��ł��B
���͂�s�s�ł͂�����Ì��j����������Ă��A���������J�ɂȂ鐅���������ǂŎ��������A�n�\�ɂ͑��݂��܂���B
�Ȃ��Ȃ��̓s�s�^���J���������y��ʏȂ̋����Ȑ���̂��ƁA�S�Ă��������ǂŎ��������J��Ɖ������s�s�^�͐�ŊC�Ɋ��Ă��Ă��܂��B���ɂ͍��y��ʏȂ͋C�������Ă���Ƃ����v���܂���B
�@���x�������Ď���ł͂���܂����A�y����낤�Ƃ���l�Ԃ͗��H�n�Ƃ͌����Ă������≻�w��������Ȃ������A���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv�킴��܂���B�ނ�͌��ǁA�q�[�g�E�A�C�����h�̔�������d�g�݂ȂǗ����ł��Ă��Ȃ��y�����オ��̒n���c���Ɠ����x�̓��Ȃ̂ł͂Ȃ����ƥ���B������"�ł�������"�ȂǂƂ����Ė��Ӗ��ȃp�t�H�[�}���X�ɉ����Đ�����z�����肵�Ă���̂ł͂Ȃ����ƥ���B |
| �@ |
| �s�s�^�W�����J |
| �@ |
�@�s�s�^�W�����J���ڗ����n�߂��̂́A��\�N�قǑO���炾�����ł��傤���H
�@��Z�Z�Z�N�������{�ɂ����̖L���Ŏ��ԉJ�ʈ��Z�~���Ƃ����s�s�^�̏W�����J���������܂������A���̐����ǂ��������Ă��Ă���̂����l���Ă��܂����B
�����ɉJ���~��Ȃ��͍̂����̕\�ʂɐ����Ȃ���������ł����A���ɁA�s�s�����̕\�ʂ��琅�������Ă���̂ł��B
�L���͑��k���u�˂̔�r�I�̑����ꏊ�ł���͎̂����ł����A�ǂ��������̐��������W�߂č~�����Ƃ͍l�����܂���B
�@�s�s�͔M�����㏸�C�����������܂��B
�������A�������Ă��邽�߂ɂȂ��Ȃ��J�ɂ͂Ȃ�܂���B�����A���܂�ɔM����ꋐ��ȏ㏸�C�����`�������ƁA���ӂ̔_�����Ȃǂ��炩���W�߂�ꂽ�����𑽂��܂�C�ƊC���瑗�荞�܂�鎼�����앗�Ƃ���C�ɉ����グ��ꋐ��Ȑϗ��_���`������ēs�s�^���J�ɂȂ�̂ł��B
����͐����܂����̂悤�Ȃ��̂ł����A���̑�J���s�s�Z������͊������Ă��邽�߂ɁA���������r������C�ɉ���������Ă��܂��܂��B
���ǁA�s�s�̊�������h�����̉J����������ޗ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B���͂�A���y��ʏȂ�@���ׂ��Ȃ�����A�L���Ȏ��R���T��ɂ���������͖߂��Ă��Ȃ��ł��傤�B |
| �@ |
| ������ |
| �@ |
�@�������ɂ�鐶���p���̒n�������s�s�̊������ƋC���㏸�ɊW���Ă��鎖�͊��ɏq�ׂ܂������A�Ȃ��Ȃ��̉J���������n�������H�ɗ������݁A�삻�̂��̂ɊW������Ƃ��������Ƃɂ���Ċ����������s�s�̂���Ȃ銣�����𐄂��i�߁A�C���㏸�Ɏ��~�߂��|����Ȃ����̂ɂ��Ă���̂ł��B
���݁A���y��ʏȂɂ���Đi�߂��Ă��鎖�ƂɃq�[�g�E�A�C�����h��}������̂͒��������Ƃ�����܂���B
���������̍߉ȂɎ��o���������Ƃ���A������A�ނ�ɂ���ēs�s���̔j��͍ŏI�i�K�܂Ői�ނ��Ƃł��傤�B
���̒��Ŕ�������s�s�^�W�����J�ɂ���ĉJ������C�ɉ͐�ɗ��ꍞ�݁A���ʂ���C�ɏ㏸���邽�߂ɉJ�����t������̂ł����A�����ނ�͓����×��ƌĂ�ł��܂��B
���ʁA�n�������̋�C������C�ɏ㏸���A��C�e�̂悤�Ƀ}���z�[���̊W����яオ�錻�ۂ��������Ă���Ƃ������܂����A�܂��ɁA�s��͍��y��ʏȂɂ���Ĕj��s���������ʁA���̂悤�ȉ���ۂ��N���邨�������~�Ɖ����Ă���̂ł��B |
| �@ |
| �J�i�[�g�Ƃ��Ă̏㐅�����l���� |
| �@ |
�@�����A�W�A�Ȃǂ̊����n�тɃJ�i�[�g�ƌĂ��n�������A�n�����{�݂����邱�Ƃ͗L���ł��B
�I�A�V�X�_�k���͉��X�ƃg���l�����ێ������̐���������Ă���̂ł��B
�@�ł́A�Ȃ��ނ�̓g���l�����@���Ă܂Ő�����n���Ɏ������̂ł��傤���B
�������n��ɐ������Ă������ɍ��ɖ��܂���肩�A�����ɒn���ɐZ�����c�������������ɏ������Ă��܂�����ł��B
���̐�Ηʂ��s������ǂ����悤���Ȃ����������y�n�ł͂��̂悤�Ȑ����鎖�����ł��Ȃ����A���ꂱ�����������̂ł��B�ł́A���{�͂ǂ��ł��傤���A����ɑ����̐�������ɂ��ւ�炸�A�����͎��Ƃ��ĕS�L���ȏ�����ꂽ�ꏊ���狟������Ă���̂ł��B
�@�{���A�㐅�������݂��ꂽ�w�i�ɂ͑�K�͂ȓs�s�����������̂ł��B
�����������������i�ł������̂̓��w���W���_���ł������j���[�}�����X�Ɛ��������̂ł����A��{�I�ɂ͐��̐�Ηʂ��s�����Ă�������ł�������܂���B
���{�͓`���I�ɔ_�ƍ��Ƃł��������߂ɐ��₷���悤�ɕ��U���ċ��Z���Ă����̂ł����B���̂��߁A�㐅�͂��������Ȃ�����̗��R����l�����A����������̐��H�ɗ����Ă����̂ł��B
�@���͎O�\�N�قǑO�ɌF�{���̐l�g�ɋ߂��R���̏W���i���������ꏟ�n�j�Ō܉E�q�啗�C�̂���_�Ƃɔ��܂����o��������܂����A���N����ƃ^�I����n����Ƃ̗��̐��H�ɍs���悤�Ɍ����܂����B
���ɏo��Ƃ��ꂢ�ȗp���H������Ă���A�����Ŋ���������������܂����B
���̂悤�ɁA��㔪�Z�N��ɂ����Ă����㐅�Ɖ�������̂̏ꏊ���c���Ă����̂ł��B
�������A����Չ�����Ȃǂƌ�������͂��炳�炠��܂��A��r�I���Ɍb�܂�Ă�����{�ɂ����ẮA�\�Ȍ��萅�͎��ӂŒ��B�����ӂɊҌ�����ׂ��ł���A�㐅���A���������I�ƍl����̂͂��낻���߂�ׂ����Ǝv���̂ł��B
�{���A���͎g�p�����l�Ԃ����̏�ŏ��Đ�ɖ߂��ׂ��ł���A�e�X�ɕ��G�ɉ����ꂽ����S���܂Ƃ߂ď������悤�Ƃ���ȂǕs�\�ȏ�Ɍ����������̂ł��B
�V���𗘗p����ȂǁA���X�ɍL�扺������p�~���A�����ȒP�ʂł̏��������ɖ߂��ׂ��ł���A�㐅���ƌ����ǂ��g�p�����l�Ԃɂ��̏�ŏ��������A�z�����A�ɗ͔p�~��������Ɍ������ׂ��Ȃ̂ł��B�������āA��A�������̔p�~�̉����ɐ��z�A�M�z�̕������]�߂�̂ł��B |
| �@ |
| �b�x��@�g�S�p�[�Z���g�n�����ŏ㐅���d���钬�ɂ܂Ń_���̐����g�킳���h |
| �@ |
���O���ŗL���ȌF�{�s���n�����Ɍb�܂ꐅ������n�����Řd���Ă��邱�Ƃ͒m���Ă��܂����A�������̒}��n���ɂ��A���݂Ȃ���������S�p�[�Z���g�n�����Ɉˑ����钬������܂��B
�Ƃ��낪�A�㐅���p���_�����݂̗��R�Ƃ��Ė������˂����܂�i�����͕K�v�ɂȂ�\�������邩��Ƃ��������j�����Ƃ���A�_���̕����𗘗p������Ȃ����ƂɂȂ��Ă���̂ł��B
�~���������̂̓_�����݂Ƃ��������H���ł����Ȃ��A�����ă_���̕����Ȃǂł͂Ȃ������̂ł����A�_���̗U�v�̂��߂ɂ́A�_����������A�����̕��S���킹�A�n�����ŏ\���������Ă���Z���ɐ������������Z���邱�Ƃɂ����̂ł��B |
| �@ |
| ����̊�� |
| �@ |
�@�Z�����ǂ��ɍ\���邩�Ƃ��������l�����ꍇ�A�S���̖ڂ��猩���D�n�͌����č���̊��Ȃǂł͂���܂���B
��O�I�ɋ{�茧�̍���䒬�A���V�e���ȂNJR�n�̏�ɏW��������ꍇ������܂����A����͍앨�i�T���ĎG���j�ւ̓��Ƃ��d����������ł��B
���̏ꍇ�ł��w��ɖL���ȗ��R������A���̊m�ۂɂ͖�肪�Ȃ���������ł����B
�@�ߔN�A����i���X�ɂ��ďd�v�ȗ��R�j��j�A�����P�u�A������Ƃ������X���Ȗ��̕t����ꂽ�ɂ킩�����n�ɏW�܂��ďZ�ތ���������܂����A�ꍠ�O�܂ł̈��_�k���̖ڂ��猩���ꍇ�A���̂悤�ȓy�n�ɉƂ����Ă��҂͏��Ă��܂������ł��傤�B
�@�S���ɂƂ��Ă̏Z��D�n�Ƃ́A�w��ɖL���ȗ��R���T���A�Z���̕�C�ɕK�v�Ȏ��ށi�|�A���A�؍ށA�y�j������A�R���i�d�A�����t�j�̊m�ۂɍ���Ȃ��y�n�ł���A���A�ʍ싗���̒Z���ꏊ�ɋ��߂����̂������̂ł��B�@
�@�y�����n�c���Ȃǂ��D�ޒ��]����������̍��@�������鍂��Ƃ��������̂́A���悻�Z�ݒ������ȂǂƂ͍l�������Ȃ��������ł���A������i�Ƃ��Ă����ɒႢ���̂������̂ł��B
���̂悤�Ȋ��o�œs�s�������ꍇ�A�Z�{�q���Y�ȂǂƂ��������w�r���Q�́A���ƁA�ØV�̕S���̖ڂɂ́u�ǂ����Ă��̂悤�ȏꏊ�ɏZ�����Ƃ��܂����Ȃ��v�Ƃ������̂ɂȂ�ł��傤�B
���R�Ȃ���A��������d�����琅�A�H���A�R���̒��B����A�p�����������������ɍ������A�n��ɍ~��鎖�����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��B
��d��Z���Ԃ̂��̂ƍl����̂̓C���[�W�A�z���͂̌��@�����l�Ԃƌ����ׂ��ŁA�����ւ̚����掂�͖Ƃ�Ȃ��ł��傤�B
�����܂œs�s�������Ȃ��̂ƍl����̂͌��Ȃ̂ł��B�������A���w�r���͂��ƃq�[�g�E�A�C�����h�̑��ʂ��猩��A�����ʂ�A��r�I���K�Ƃ̘b�͕����܂��B
��ЊQ�A�\���A�����A�푈�A����Ôg�A�G�l���M�[�̍����A���˔\�ЊQ�i����͓s�s�A�_���ɊW�Ȃ��j�]�ɓ����܂����j�ȂǁA�s�s���̍s���������悪���w���ł���A�ς��������܂ł̃q�[�g�E�A�C�����h�����̐�ɍT���Ă���̂��Ƃ���A���ǂ͍��w���ɂ���Đ��ݏo���ꂽ��n��Ή����A���щ����Ă����������@�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B
�@���ƁA�q�[�g�E�A�C�����h�̑��ʂ���s�s�������ꍇ�A���ʂ͐l���Z�ݒ����Ȃ������ꏊ�̊R�n�ɂ܂Ől���Z�ݒ������R��j�����A���Ɨ��R���ɂ����_�Ƃ��̂ċ���ُ�ȋ�Ԃ��`���������A���������_�����琅���ǂɂ���Ĕz����̂Ƃ��Ă��܂������߂ɐ�����������J����f���o�����߂̂��̂ƍl���A���܂����R���N���[�g�ŕ����A�n�������H�ɂ܂ŕς��悤�Ƃ��Ă��鎖�̉����Ɍ��݂̃q�[�g�E�A�C�����h�Ƃ�������K�͂ȋ��j������݂��Ă���̂ł��B |
| �@ |
| ���y��ʏȂɂ���Ĕj�ꂽ��s�s���ǂ��Č����邩 |
| �@ |
| �@�j�@����Ή��A�ǖʗΉ� |
�@����͋Z�p�I�Ȗ������A�u���܂łɂǂ̒��x�`���t���邩�v�Ƃ��������ł�������܂���B
���ɋZ�p�͊������Ă���̂ł��B
���Ԓ��x�Ȃ璼���ɂł��\�ł��傤�B�u�ł�������̑�Ԕ����I�v�ŏ������ȈՉ��㒣�萅�ƕ��p���Ă��ǂ��̂ł��B
�l�Ŏn�߂�Ƃ��Ă��A����Ɏg�p�ςݎ����ނi�A���ւ̑��i�K�̉h�{�͂���ŏ\���ł��傤�j�Ȃǂ�~���l�߁A���̏ォ�獻��D�⏬�������Â~���l�߂邾���Ŋ�������̂ł��B
���́A�D�̗��o�Ɣr�����̖ڋl�܂�ł��傤���A���������Ƃ��A�r���a�����͂ނ悤�ɐv�[���i�����r�j���{�H������̖��͉����ł���ł��傤�B
�����ꐅ���Ȃǂ������A�g���{�������Y�݂ɗ���悤�ɂ��Ȃ�͂��ł��B
�@���́A�����A�����邩�ł��B
�������A�������炵�̉���ł�����A���������đ䕗�Ȃǂŗ�������悤�Ȏ��Ԃ͋������͂�������܂���B
���̏ꍇ�́A�r���̊O�s�̘g���`���t����ΑΉ��ł���͂��ŁA�y��̐[���𐧌���������A����قǑ傫�Ȏ��ɐ�������͂��͂Ȃ��̂Ŗ~�͂̑�Ɠ����Ȃ̂ł��B
�@�ǖʗΉ��͂���قNJȒP�ł͂���܂��A�ӂ킹�邮�炢�͂����ɂł��\�ł��傤���A�ې����̂���ǖʗΉ��Z�p�͂�����x�m�����Ă��܂��̂Łi�~���N���E�\���H�@�ł������A�����̕ǖʂł��Ή����\�ɂȂ�̂ł��j�A��ʏZ��⏬�K�̓r�����x�ɂ͂����ɂł��Ή��ł���̂ł��B |
| �@ |
| �A�j�@���H��� |
�@���H�ܑ������̂��̂ɕς��Ă����X������ʓ��H�ł��F�߂��܂����A����͉J�V�ł̃X���b�v���̑�Ƃ������b�ɉ߂����A�q�[�g�E�A�C�����h�ɑ��Ă͂قƂ�nj��ʂ�����܂���B�Ȃ��Ȃ�A�z�����܂ꂽ���͒�Ŏ��A���H���a�ɗ��Ƃ���Ă��邩��ł��B
�������A����ł������͓��H���a�ɗ�����r���������邱�Ƃɂ���āA�����炩�̌��ʂ鎖�͉\�ł����A�{���͏����ł��n���̒n�ՂɐZ��������i�t�ɒn���̒n�Ղ��琅�������o����j�����d�v�Ȃ̂ł��B�����A���p�͉\�ł�����ŏ�����ے肷�鎖�͎~�߂Ă����܂��傤�B�v�͂�肩���Ȃ̂ł��B
�@���H�ܑ��ɂ��ẮA�H�Ոȉ��ɉJ����Z��������Ɛ����i�~�Y�~�`�j�������A�זv���̂��������邽�߂ɓ������ܑ����h���������������܂����A����������p�x�̖��Ȃ̂ł��B
�q�[�g�E�A�C�����h��̂��߂����Ȃ�A�H�Ոȉ��ɂ͎�𒅂����ɁA�����ނp�̑f�ނ�X�|���W��̍��������i�z�����|���}�[�j��~���l�߂Ă��ǂ��ł����A�זv���Ȃ��悤�Ƀ��b�t���\����n�j�J���\���ɂ��Ă��ǂ��̂ł��B
�@����܂œ������ܑ��͋��x����肾�Ƃ���ĕ��y���x��Ă��܂������i���͖{���ɋ��x���Ⴂ���ǂ��������������̖��Ɨ������Ă��܂��j�A�����ɂܑ͕��������Ȃ��Ă��ǂ����̂܂ł����A�H�����s���A�z�������\�Z�����S���������H�ܑ���Ɓi��́A���n��̕ʉ�Ђ�q��ЂȂ̂ł����j�ɋz�����܂��d�g�݂ɂȂ��Ă���Ƃ����b���������Ă��܂��̂ŁA���F�͛������̗ނɉ߂��Ȃ��ł��傤�B
�@�����̕��͊זv���̂̐S�z���ԓ��قNjC���g���K�v�͂���܂��A���x�Ȃǂ��炳����ɂȂ�܂���B
����ɁA�����ܑ̕��������ȂǂقƂ�Ǖs�v������ł��B����ȑO�ɁA�{���ɕܑ����K�v���ǂ��������^��Ȃ̂ł��B
�܂��A�X�H���̂�������́A�n���ɐ�������悤�ɂ����ƒn�ʂ�傫���J���ׂ��ł��傤�B
�܂��A�����⊢��Ώ�Ɠy�ƂŎ{�H���A���̐����镔���𑝂₵�Ă��\��Ȃ��̂ł��B�W���M���O��E�H�[�L���O�ŕ����l�Ԃ���ԂɃV�t�g���Ă���̂��A�������h�����Ă��邩��ŁA�d���A�X�t�@���g����������y���ŕ��������͂��Ȃ̂ł��B
�@�܂��A������H�ʂƓ������x�̍����Ɏ{�H���A�ԓ��ɍ~�����J������̒��Ɉ������݁A�ؗ��^�̏��͐���Ă��ǂ��̂ł��B���ꂾ���ł����H�͐l�ԂɂƂ��ď����̂�����̂ɕς��͂��Ȃ̂ł��B
�@���������A�Ȃ��������ԓ����グ�Ă����̂���k��A�����ȗ��̎s�X�n�̕������������[���b�p��͔͂Ƃ��A���̉��^������n�܂������̂��A�����Ӗ����Ȃ������Ă��������̘b�ł����Ȃ��̂ł��B
���[���b�p�̊X���̕������H�ʂ��������{�H���ꂽ���R�ɂ��Ă͏�������悤�ł����A�g�C���b�g���������Ă��Ȃ���������ɂ͓��H�ɖʂ�����������l������������銵�s������i�������n�Ԃ��嗬�ł���������ł�����n�̕��A�͂�����܂��������̂ł����j�A�J���~��Ƃʂ����œ�����������قƂ�ǂł��Ȃ��������߂ɕ�������������������Ȃ������ƌ����Ă��܂��B
�{�����ǂ����͂킩��܂��A�n�C�q�[���̋N�������ꂪ���R�Ƃ����b�������Ƃ�����܂��B
���{�ł́A���H�ɐl���𓊊����銵�s�͑S�������A�m���ɏW�߂��Ĕ엿�ɂ���Ă����̂ł�����A�����ɗ������Đl�����{�͐����ȓs�s���ƕ]�����Ƃ����b����������̂ł��B
�@���݁A�s�s���ɑ���ꂽ�����͂Ƃ������Ƃ��āA�Ԃł̈ړ������S�ɂȂ��Ă���n���s�s��_���ł́A�o���Z�̏����w�����̂����ĕ���������Ă���l�Ԃ͂قƂ�ǂ��܂��A��n�߂Ƃ��Ċό��n�𒆐S�Ɏ������n�߂Ă��ǂ��̂ł��B
���݂̕����͊��ɓ��H���ߏ苟���ɂȂ��Ă��钆�ŁA�Ȃ����A���H�H�����g�債�������߂����֖̕@�Ƃ��ė��p����Ă������̂ł����Ȃ��i�ԓ��g���A�l�Ԑ����A�����A�����������Ɠ��H�H�����g�傳���Ă������y��ʏȂ��A���낻��ߏ苟���ɂȂ��Ă��鎖�͏\���ɔF�����Ă���͂��Ȃ̂ł��j�A������Ȃ��H�����J��Ԃ����̓q�[�g�E�A�C�����h��Ƃ��Ă̓]����}��ׂ��ł��傤�B
���������A�q�[�g�E�A�C�����h�̌����͍��y��ʏȂȂ̂ł�����ӔC������Ă��炤�ׂ��ł��B |
| �@ |
| �B�j�@�s�s�ܑ̕���ς��� |
�@�s�s�̗Βn�����ቺ���Ă��鎖�͌����܂ł�����܂���B�������A�����葁���q�[�g�E�A�C�����h����s���Ƃ���Ȃ�Γ��H�����ȒP�ł��傤�B
���ԏ��e���X�Ƃ��������̂̃A�X�t�@���g�A�R���N���[�g�ܑ��������������A�p�ނ�Ԕ��ނȂǂŊȈՕܑ��ɂ���Ηǂ��̂ł��B
�y�Ƒ��̕������\�Ȍ���g�債�A�{���ɕK�v�ȕ���������ܑ�����Ηǂ��̂ł��B
�@���̎�̂��̂́A�s���@�ցA�w�Z�A�����٥���Ƃ��������̂��琏���s���Ă����A�\�N��҂������Ă��Ȃ��̓I�Ȍ��ʂ������Ă���ł��傤�B
�@���̒��x�̎��Ȃ�A�������قƂ�ǎ����Ȃ����Ȃɓn���Ă��ǂ��͂��Łi���Ă̊���b�̏��r�S���q��"�ł�������"�ł͂��Ⴎ���x�ł�����A���炭���̏d�v���ɂ��Ă͑S���������Ă��Ȃ��̂ł��j�A�⏕���Ŏ����I�ɍs�킹�邩�i���Ԋ�Ƃ̕~�n�ܑ̕��ɂ��ĐV�K�͖@�ŋK�����A���ɂ�����͕̂⏕���ōs���Ă��ǂ��ł��傤�j�A�@���ŋ������邩�͍��Ƃ̑I���̖��ł����A�\�Z�K�͂Ƒ�̃X�s�[�h�A���ԂƂ̐킢�ł�������܂���B |
| �@ |
| �C�j�@�q�[�g�E�A�C�����h��ƌ��z�m�F�\�� |
�@�ƁA�}���V�����A�I�t�B�X�r�������Ă�ۂɌ����̐v�R�����s���܂����A���̍ۂɒ��ԏ�A���ցA��Ȃǂܑ̕����\�Ȍ��萧�����A�Œ�ł��������ܑ̕��ɂ��邱�Ƃ��`���t����ׂ��ł��傤�B
�r���H�⑤�a��Z�����̂��̂Ɏ{�H���A�J�����ꎞ�I�ɒ�������ꌊ�̋��h�ΐ����i�v�[���j�̐ݒu���`���t����Ƃ��A��̋��ɑf�x��̒n���Z������悤�ɂ��鎖�����シ��̂ł��B
�@����͐V�K�̒��H���ɍs�����̂ł����A���̂悤�ȍl�����Œn�ʂ̉��z��i�߂Ă����̂ł��B
�����̎{��͂����Ƒ����s���Ă��Ă����������Ȃ��̂ł����A���y��ʏȂɓs�s�̃q�[�g�E�A�C�����h���̐ӔC�������B�ɂ���Ƃ����F������������Ȃ��������ɂ��S���ł���Ă��Ȃ��̂ł��B |
 |
| �ǂ��ɂł�������R���N���[�g�ŕ���ꂽ���ԏ� |
| �@ |
| �D�j�@����n�������r |
�@�����s�́A�s�s�^���J�ɂ���Ĉ��o�������̎M�Ƃ��āA������̊����̒n���l�Z���[�g���̂������[�x�n���ɉ������L���A�����\�͐��\���g���Ƃ������咙���r���ꕔ���������Ă��܂��i����A������v�F�����l.�܃L���A�l���g���j�B
���݁i����͏��������_�ł̘b�Ō����_�ł͊m�F���Ă��܂���j�A���̌v��͓s�̍��������ɂ���ē�������Ă��܂����A�{���͓����p�܂Œn���͐�Ƃ��ĐL�����ƂɂȂ��Ă���̂ł��B
����ł͊������Ă��Ȃ��n�������H�ʼnJ�����ꎞ�I�ɗ��߂���̂ł�������܂��A�����ԗ��߂ė��p�ł���\��������A�܂��A�������ɖ{���̉͐�i�_�c��j�ɏ㗬�悩��җ��ł���\��������̂ŒP���ȕ]���͂ł��Ȃ��ł��傤�B
�������A�͐�̒n�����v�́A���ꎩ�̂Ƃ��ēs�s�̃q�[�g�E�A�C�����h�����K�͂ɑ��i������̂ł���A���F�͐��܂�Ă��܂������������ǂ����邩�Ƃ��������x�̘b�Ȃ̂ł��B
���Ȃ��Ƃ��A�ď�̑�s��̒n���ɋ���Ȑ����邱�Ƃ��ꎩ�̂͑����̗�p���ʂ�����Ƃ͌�����̂ł����i����������͂܂��Ƃ������x�̂��̂ł��j�A�����A�㐅�@�\����������v�悪����̂��A�^�������l���A�ꎞ�I�ɒ������ď��X�ɕ�������̂���������܂���B
�@�������A�^�����߂��ړI�Ȃ�Βʏ�͋�ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ŁA��J�̌�ɁA�͐�Ɋҗ�������A���̎������͈��̌��ʂ�����Ƃ������x�̑㕨�ł��B
�@���̌v��͎��ԉJ�ʌ܁Z�~����z�肵�����̂ł������A��N�i2005�N�j�㌎�̘Z�Z�~���ɑ��Ă͖��͂ł������ƌ����Ă��܂��B
���ݔ��Z�Z�Z���~�𓊂��ē����̖ړI�ł������^�����߂������B���ł��Ă��Ȃ��̂ł�����A�܂��́A���[�l�R���ɂ���Ă�������Ƃƌ��킴������Ȃ��ł��傤�B
�n�������r�̓_���̗}���A�Đ����̏z���p�Ƒ����̉\���������Ă��܂����A����̓q�[�g�E�A�C�����h���S�̘b�Ɍ��肵�Ă��܂��̂Ŋ������܂��B |
| �@ |
| �E�j�n���X�A�n����Ԃ��ǂ��]������̂� |
�@�������̋������ɓ��P�������悤�ɁA���̎˂����܂Ȃ��n���ɓ��邱�Ƃ͂���Ȃ�̌��ʂ�����͎̂����ł����A������ǂ��l����̂��͂��Ȃ������ł��B
�@�Ăɏߓ����╗���ɓ�����ꂾ���ł����Ȃ���������Ƃ͂ǂȂ����o������Ă���ł��傤�B
�ߓ����╗���Ƃ���������Ȃ��̂Ɍ��炸�A�g���l����h�i����Ȃ��̂ɂ͂��܂����ꂽ�o���͂Ȃ��ł��傤���j��_���̒�̓��ʘH�ł�������x�͎����ł��܂��̂ŁA�`����"���y�����̌����Z��̂悤�ɒn���Ő������Ȃ���Ȃ�Ȃ���������Ȃ�"�ȂǂƏ������킯�ł��B
�ł́A�n���X��A�n����Ԃ͂ǂ̂悤�ɕ]������ׂ��ł��傤���B
�@���̎�̘b�͋ߓ��M�����̗̈�ɂȂ�܂��̂ŃA�h�o�C�X�Ȃ���Ȃ�܂���ł������A�ނɂ��ƁA�R���N���[�g�Ōł߂��l�H�I�Ȓn����ԂƏߓ����╗���Ƃ��������̂ɂ͑����\���I�ȈႢ������A�������鎖�͂ł��Ȃ��Ƃ������ł����B
�����̃��[���ł̂����ł������A���m���������߂ɁA�ȉ��A�ߓ����������̂܂܌f�ڂ��܂��B |
| �@ |
�@�ߓ����Ȃ��������̏ꍇ�A�ΊD��̐Z�H�n�`�ł��邩�A�ΎR���n�`�ł��邩�ɂ͍�������܂����A���ʂ���̂͑��E���̍\���������Ă��邱�Ƃł��B��͊���Ȏ����ɒn�\�ɒʂ��錊���犦�C���N�����đ��E���̕�����ߓ������̕ǖʂ�~�M���u�Ƃ��ė�p���Ă���Ƃ������̂ł��B�ꍇ�ɂ���Ă͕����I�ɕX���ɂȂ��Ă��镔��������ł��傤�B�Ăɂ͊O�C���������ሳ�ɂȂ邽�ߑ��ΓI�ɍ����ɂȂ���������ߓ��������C�����o���邱�ƂɂȂ�܂��B������̗��R�͗v����ɗ�p���̑��݂ł��B�n�������̂��n�ʂ̒f�M�ɂ���ĔN�ԂƂ���15�����x�ň��肵�Ă���͖̂ܘ_�ł����A����ɕ�����ߓ������̕ǖʂɂ��ݏo���n��������������Ƃ��ɐ��M���z�����邱�Ƃɂ���čX�ɗ�p����Ƃ������̂ł��B
�@�n���X���K�͉������́u���B�v�����s��ł́A�܂��n�����ʂ��ɒ[�ɒቺ���Ă���ƍl�����܂�����A�n�\����̏����ʂ������Ă��܂��i�q�[�g�E�A�C�����h���ۂł��ˁj�̂ŁA�n�\�ʂ̒f�M���ʂ͂��Ȃ�Ⴍ�Ȃ���肩�A�t�ɃR���N���[�g��A�X�t�@���g�Ŕ핢���ꂽ�~�M���u�Ƃ��ċ@�\���邽�߁A�s�s���ȑO�̒n����ԂقǗ������͂Ȃ��ł��傤�B�܂��n�����͂������Ƃ��Ă��A�s�s�̒n����Ԃւ́u�R���v�͎ז��҂Ƃ��đ��₩�ɔr������܂�����A�����̐��M�Ƃ��ė�p����Ƃ����@�\�����҂ł������ɂ���܂���B |
|
|
|
| �@ |
�Ƃ������̂ł��B�����Ȃ��疾���ł��ˁB�����ł����z���M�z�̌��ł��鎖��������܂��B
�@�����������̂Ƃ��āA�j�V�F���^�[�Ⓑ���Ԑ��q���錴�q�͐����͓����̔M���̖�肪����܂��B
�O�҂͕��˔\�̗�������؋��₷�鎖��ړI�Ƃ��邽�߂ɑ����銮�S�ɕ����ꂽ��Ԃł���A��҂͊C���̐����͓��Ƃ������S�ɕ����ꂽ���ł����A�ő�̖��͐l�Ԏ��̂�������̉��Ɛl�Ԃ̐����ɔ����p�M�̏����ƌ����Ă��܂��B
���ꂪ�O�҂ɂ����Ă͓��ɓ���̂ł��B
�@�n���X�͕K���������S�ɕ����ꂽ��Ԃł͂���܂��A�����̔M�̖��ɂ���Ē����ɗ�p���u�ɗ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�̂ł��傤�B
�r�C�����g���ĔM����ꂽ��C��r�o����Ƃ��Ă��A�ւ��̋�C������ȏߓ����̂悤�ȑ傫�Ȓn����Ԃ���i�v�ɋ����ł���Ȃ�Εʂł����A���̂悤�Ȃ��Ƃ͂قڕs�\�ł���A�n���X�́A���z�̒��ڕ��˂��Ղ鎖���\�ɂȂ�ȊO�́A���̈Ӗ����Ȃ����̂ł��邱�Ƃ�������Ǝv���܂��B
�܂�A�f�x��̕ǖʂ��ێ����鉩�y�����̌����Z��ȉ��̂��̂ł���Ƃ������Ƃ͖��炩�Ȃ̂ł��B
�@���ɁA�ߓ����╗���Ƀ��X�g������������Ƃ��Ă��A��ɐ����Ă��܂�ɂ������̂��q������Ă���A�����ɔj�]���A��^�̗�p���u���K�v�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B
�n���X���A�n���}���V�����i����Ȃ��̂�����ł����j�������ďZ�������K�ɂ͂��Ȃ��̂ł��B |
| �@ |
| �F�j��A���������ǂ�����̂� |
�@����ŏ�A��������S�Ĕp�~���鎖�͕s�\�ł��B
�������A��A�������͊��Ɍ�i���̂��̂Ɨ������ׂ��ł��傤�B
�@�{���A���͂�����g���l�Ԃ̎��ӂŒ��B���A�ɗ͂��̐l�Ԃ̎��ӂ̉͐�ɊҌ�����ׂ��Ȃ̂ł��B
���̎��ӂ͈̔͂��ǂ̂悤�ɍl���邩�́A���̓y�n�����A���ɂ���đS���ق�ł��傤���A����������A��ƒP�ʂōH��Ƃ��̎Б�Ȃǂ̋��Z���ɂ����ĉJ�����ꎞ�I�ɒn�������r��V���n�ɏW�߂��̈ꕔ�����̕~�n���ŏ��Ďg�p����̂ł��B
���p�܂ŗ��p���邩�ǂ����͑I���ł���A�n�����ɗ����ꏊ�ł͒n�������A�܂��A�J���ɂ��V�����p���ł���W���ʐς�����A��������Ďg���Ă��悢�ł��傤�B
�㐅�A�܂��g�C���A���C�Ȃǂ̒����ɗ��p���Ă��ǂ��̂ł��B
���ŏ��������Đ����͉������ɗ������ɉ͐�ɗ����̂ł��B��������A������A�����̏�A����������Ɨ������G���A�������ł���̂ł��B
���ɂ��̐��������̍�������㐅����͊�Ƃ̓P�ނ��Â��ɐi�s���Ă��܂��B
���̗��R�̓_���̉ߏ苟����Ԃ̒��ł��V���ȃ_�����������ꑱ���A���̖��ʂȎ��Ƃ̃R�X�g�����������Ɋm���ɏ�悹����Ă��邩��ɊO�Ȃ�܂���B
�@������A��ƂȂǂ𒆐S�ɑ�^������������P�ނ��n�܂邱�Ƃł��傤�B
���������s�X�n����x�O�ւƉ��������т�ɏ]���āA�ǂ̑�^���A�{�݂̋��剻�����䋉���I�Ɋg�債�A�������͔��Ɋ����Ȃ��̂ɂȂ��Ă���̂ł��B
�@��A�������Ƃ��Ɉ�ɏW���^�̂��̂ɂ���̂ł͂Ȃ��A�����̖[�̂悤�ɏ��K�͂ȘA�g�̏W���̂ɕς��Ă����ׂ��ł���A���̂Ԃǂ����\�Ȍ��苐��f���E�G�A�̂悤�ȏ����̏W���̂ɕς��Ă����ׂ��Ȃ̂ł��B
�@�������ő����̐�����ӏ��ɏW�߂ď������鎖�����X�����Șb�ŁA�N����������₷�������ȃG���A�ŏW�߂��������̉����ɍ��v��������������̂������I�ł���A�ԁA�A���A�A���A���A�D�Ƒ����̊G�̋�ō����������̂�^���ɖ߂����́A�Έ�F��������������^���ɖ߂������ȒP�Ȃ̂ł��B
����������i���̂��̂��ƌ������̂́A���������Ӗ�����ł��B
���x�����Ƃ������Ă͂��܂����A���Ԃ͋ɂ߂Ă��������̂��Ƃ����b�͉������W�҂̊Ԃł͏펯�Ȃ̂ł��B
�@�㐅�ɂ��Ă��A����Ȓ��ԏ�≮���ŏW�߂�ꂽ���������C�ɗ�������ł��錻��قNj����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
���ɓs�s�͐�̒�����Ŏ搅������������ł���s�s�Z���������킯�ł�����A�����I�ɂ͉���������ł���̂ƕς�肪�Ȃ��Ƃ����b���ǂ������܂��B
���̂悤�Ȓ��ł͂���Ɉ�w�J���̗��p��i�߂�ׂ��Ȃ̂ł��B���Ȃ��Ƃ��ߏ苟���̒��Ń_�������݂��������^����K�v�͂Ȃ��̂ł��B
�@�l���x���ł���ƃ��x���ł��A�\�Ȃ�Ώ㉺��������ɗ͓P�ނ��邱�Ƃ��������߂��܂��B
�����̓R�������������Ă���悤�Ȍ�i���ł����L���ȃV�X�e���Ȃ̂ł��B
���ɁA�J���̗��p�A���ɂ�鏈���̋Z�p�����͗y���ɏオ���Ă��܂��B��A�������̔p�~�͐V���ȎY�ƂƖL���Ȏ��R�����߂�����ƂȂ�̂ł��B�@
�@�܂��A�V���Ȕ��z�ƐV���ȗ��z�̍\�z�����̉�����ɏ�A�������Ɋ�������y���Ǝ҂╅�s���������A�c���ǂ��̒Ǖ����\�ɂȂ�̂ł��B |
| �@ |
| �G�j�ő�̖��ł���͐���ǂ�����̂� |
�@�����ł͓s�s�͐�̂������ʂ��l�������͂���܂���B
�����܂ł��q�[�g�E�A�C�����h���ۂɑ�����Ƃ��āA���̑��ʂɂ��Ă������c�_������̂ł��B�ƁA�����Ă��ɂ߂ĒP���ł��B
�͐���^���̑��ʂ����ōl����A���i�͂قƂ�ǐ������ꂸ�A�^�����ɂ͂��������C�ɗ������߂���̂����z�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���̂��߂ɂ́A�ł��邾������������āA���⟺�Ƃ��������̂��Ȃ��A���R�ŏ�Q���̖����A�܂��A����ɂ��ʐ���j�Q����\���̂�����̂���Ȃ����̂Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B
�ЂƂ���O�܂ł̔ނ�̗��z���ȒP�ɐ�������ƉJ�����킯�ł��B
�����A�s��̉͐�͂��̂悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���̂ł��B
���̂��߉\�Ȍ��蒼��������A��h���ӂł͖���|�����i��������ƌ���̌����ɂȂ�Ƃ����̂ł��j���ƂɂȂ�܂��B
���ۂɂ͐삪�����������Ɨ����������A���̂��Ƃɂ���Ă������Ē�h�͔j��₷���Ȃ�̂ł����A�����₤���̂Ƃ��ăR���N���[�g�Ȃǂɂ���ĕ⋭���i�߂���̂ł��B���̓_����l����Ɠy�؋Ǝ҂̗��z�Ƃ��d�Ȃ��Ă���̂ł��B |
 |
| �{�茧���ѐ쌹���� |
| �@ |
�@����R���N���[�g�ň͂ނ��Ƃ͓��H�̕����g�傷��v������n�܂������̂ł����A�����ɐ��̏��U�𑣐i������̂ł��邱�Ƃ͌����܂ł�����܂���B
�܂��A�n���͐�A�������͂����������̏����ɂ��M�z�ɑS����^���Ă��܂���B
�ƁA���������唼�̐���n���ɗ������ނ��Ƃ��A�q�[�g�E�A�C�����h�̍ő�̌����Ȃ̂ł��B
�@�ΏǗÖ@�I�ł͂���܂����A�n���͐�i�n�������r�^�̂��͉̂^�p�ɂ���āA�^�����ߌ�Ƀ|���v�E�A�b�v�ł����R�����ł��ɗ͉͐�Ɋҗ������A�s�s�͐�̈ێ����Ƃ��ׂ��ł��傤�B
�܂��A�X���b�g��̉���݂��A�܂��A�͐�ɐ��[�̈Ⴂ��݂��A�ɗ͒����A�����A�����������߂�ׂ��ł��傤�B
�������A�쏰�ɕω���t���A�������ł������c��悤�ɂ���̂ł��B
�@����A�}�t�̏��͐��s�X�n�̑��a�Ƃ��������̂��A�قځA���S�ɃR���N���[�g������Ă��邽�߂ɁA�J���𗬂��o���Ƃ���������̖����͎����Ă��܂����A�J����߂����̃J���J���̍a�ɂȂ�A�͂��Ȑ������ۂ��Ƃ��ł��܂���B
���̃R���N���[�g���a�Ƃ���������Ȃ����̂́A���͂̒n�ʂ��班�����������W�߂Ĉ��肵���������X�ɉ����ɑ���o���Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ���A�����������Ɏ��炪�ۂ������͂̒n�ʂɖ߂����Ƃ��ł��܂���B
�������z�ƍl���鑤�a�Ƃ́A�R���N���[�g�̕ǖʂł͂Ȃ��A�����������ɂ͎����ɐ�����₢�A�����Ȏ��͗]���Ȑ������z�����~���邱�Ƃ��ł���y�ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��B
�܂�A���͂̒n�ʂƐ����̃L���b�`�E�{�E�����s����悤�Ȑ��H�ł��葤�a�ł����A�K������������̂ł͂Ȃ��A���E���R���N���[�g�A�l�b�g��̑��a�A�ɒ[�Ȍ�����������Ί��݂̐��H�Ɉ��̍E���J���Ă��ǂ��̂ł��B
�܂��A���a�̌`����A�[���̈Ⴄ�ł��ڂ��̂�����̂ɕς��Ă��ǂ��̂ł��B
�@��������A�͂��Ȃ��������ۂ����ł��܂����A���a�ɐX���b�g��̉����`���t���Ă��ǂ��̂ł��B
�|�������ɂ����ƌ����̂Ȃ�A�X���[�v��̉��ɂ��Ă��ǂ��̂ł��B
�D�����܂�ƌ����̂Ȃ�Ζ]�ނƂ���ł��傤�B�Ȃ��Ȃ�A���ꂱ���������Ԑ�����ۂX�|���W�ɂȂ�̂ł�����B |
 |
| �ǂ��ɂł�����s�s�^�͐� |
| �@ |
| �b�x��@�@�g�g�p�ςݎ����ނ̉ԍ炩�W�W�C�h |
| �@ |
���[���H�̐�ɂ���n�ʂ̎����l���܂��傤�B
�`����"�ł���������A�R���N���[�g�������������I"�Ƃ��܂����̂Ő����ŏ����܂��B
�������������Ւn�̍r�n�Ɏ��R�ɑ��������Ă���̂�҂��Ă��鎖�͗��z�ł����A�{���Ɋ������Ă���ΖʂȂǂɂ͂Ȃ��Ȃ��L���ȗ͖߂��Ă͂��Ȃ����̂ł��B
���̂悤�Ȕj�ꂽ���ł̕��тɂ́A�g�p�ςݎ����ނ��A���M�⊄�蔢�����M���Ō������ؓB�Ȃǂœ˂��h���A�y��킹�Ăǂ�̎�ł���T���Ă����A���Ȃ葁�����������Ă�����̂ł��B
�R���N���[�g���������������r�n�ł́A������ł͂Ȃ��h�{���s�����Ă���̂ł��B
�����͉͐��h�ł��L���ł�����A�Q�����I�ɕ��щ^�����������͐_���{�[��
�̔��Ɏg�p�ςݎ����ނ�~���l�߁A�ォ��D��킹�ǂ�ƌ��킸�A�D�݂̖�̎�Ȃǂ���荞�݁A�Ԃ̃g�����N�ɐςݍ���ōr�n�ɂ����ƒu���Ă��邾���ł�����X�R�b�v�Ō����@��悤�ȋ�J�����Ȃ��Ă��ǂ��̂ł��B
���̂悤�ɊȒP�ɗ����Ԃ��^�����ł���̂ł�����A���Ɋ��j��̌����Ƃ��Đl���𑗂��Ă����y����Ђ̎В���n���c���A�V���芯���̘V���"�ߖłڂ�"�A���ʑO�̉���̍s�r�ɂ͍œK���Ǝv���܂��B
���R�������ɒǂ����̂�����A������ƈ����̐ӔC������Ă��玀��ł����I |
| �@ |
| �H�j����Ȃ�q�[�g�E�A�C�����h�֒n�������H�͉��т� |
�@�n�������H�̊g�傪�q�[�g�E�A�C�����h�̌����ł��鎖�͘_���̗]�n�̂Ȃ������w�I�����ł��B
�������A�q�[�g�E�A�C�����h���s�s�ɂƂ��ďd��Ȋ�@�ł���̂Ȃ�A�Ȃɂ����Ă����Ă����Ƃ͑S�͂��グ�đ�����ׂ��͂��ł����A���ۂɂ͑S���t�̎����N�����Ă���̂ł��B
�n�������H���v���̈�ł����Ȃ��Ƃ��Ă��A���Ȃ��N���[��������킯�ł��Ȃ�����I�Ɋg��𑱂��Ă��܂��B���ł�����s���O�s�����H�����Ă݂܂��傤�B |
|
|
�q�[�g�E�A�C�����h�Ђɋꂵ�ލ�����K�ڂɁA���łŌւ炵���ɐ�`�����n�������H�@�@�@�@�@�@�@�@
�]�ː�͐쎖������HP����I |
| �@ |
�@��ʌ��̓����Ői�ށA���E�ő勉�̒n���͐�̌��v��ł��B
�@��s���O�s�����H�͍���16���̒n����50���Ɍ��݂���鉄��6.3�q�̒n�������H�ł��B�{�݂́A�e�͐삩��^����������闬���{�݁A�n���Œ���������A��������n�����H�A�����Ēn�����H����^����r�o����r���@�ꓙ�ō\������Ă��܂��B |
| �@ |
| ���y��ʏȊ֓��n�������Ǎ]�ː�͐쎖�����̃z�[���E�y�[�W"�������̎d��"���� |
�@"�������̎d��"�ƌւ炵���ɏ�����Ă��܂��̂ŁA�܂��A�����B����قǗǂ����Ƃ�����Ă���ƍl���Ă���̂ł��傤�B
�ނ�͍^�����߂̂��Ƃ������ɂȂ��̂ł��B�����o�ł��鎖�قNj��낵�����̂͂���܂���B�������A�c��ȗ\�Z��H���ׂ��̂ł�����A���͂⍑�Ƌ@�ւ͋@�\��~�Ɋׂ��Ă���Ƃ����l�����܂���B
�@���̎�̎��Ƃ́A��s���ɂƂǂ܂炸�ɒn���ɂ��g�U�𑱂��Ă��܂��B
�ŋ߁A�K�ꂽ���ꌧ�ł����̈�[��ڂɂ��܂����̂ŏЉ�Ă����܂��B
��Õ����H�́A��Îs�X�n�̖����I�ȍ^����Q���y�����邽�߂ɁA��Îs�암�𗬂��W�̏��͐�̍^���𒆗����ŃJ�b�g���A�����H��ʂ��āA���c��֗���������n���g���l�������H�ł��B���݁A�����ԁi���c��`���z��܂ł̖�2.4�q�j�̍H�����I���āA���ɒʐ����J�n���Ă��܂��B |
|
|
| �@ |
| ���y��ʏȋߋE�n�������ǔ��i�Ή͐쎖�����̃z�[���E�y�[�W"��Õ����H����"���� |
�@�����ł́A�n�������H���S���I�Ɋg��̗l����悵�Ă���Ƃ������Ƃ��Љ�Ă����܂��B
�ʓI�ɂ��̎��Ƃ��ǂ��]�����邩�ɂ��Ă͓��ݍ��݂܂���B���́A���̉^�p�ƁA�R�X�g�ł��B�@�@
�����A���ꂪ�q�[�g�E�A�C�����h������������̂ł��邱�Ƃ͗������Ă����ĖႢ�����Ǝv���܂��B�@�@
�܂��A���i�Ή��݂̑�Îs�ł͑�K�͂ȃq�[�g�E�A�C�����h�͖ڂ̑O�̑吅��ɂ���Ċɘa����Ă��܂�����A����̒��ԏ���A�X�t�@���g�Ōł߂��ׂɏ����Ă��܂�Ȃ����x�̘b�ł����āA���Ǝ����ł�������܂���B |
|
|
| �@ |
| �I�j�s�s�^���J�̕p���Ɠs�s�̐��s���ɂ��āi�����̋ߓ���������j |
�@�u�������l����v�ɂ͋ߓ��M���������� �T�DHP�Ǘ��҂��� �Ƃ������ɐ����̍����R�����i�H�j������܂����A���� No�D225���i2006/08/24�j�Ɂu�s��̍��J�Ɠ������̊������v�Ƃ��������ׂ��������f�ڂ���Ă��܂��B
�ڂ����͌�����ǂ�ł��������Ƃ��āA�ȗ������ď����A���ɁA�q�[�g�E�A�C�����h���_�I�ȌǓ��ɂƂǂ܂炸�A�ߔM�A�ŔM�x���g�Ƃł������ׂ����̂ɐ������Ă���A���̂��Ƃ����{�̉J�̍~����ɔ��ɑ傫�ȕω���^���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂ł��B
�@����͓s�s�^�̏W�����J�̌����ł��B�{���͒n�\�ɂ��܂˂��L����X�|���W�̂悤�ȓy����Â��ɐ�����������A���ꂪ�������邱�Ƃɂ���Ĉ���I�ɉJ���~�鉸�₩�ȋC�������̂��A�C�ɖʂ��ăx���g�������s�s�̃q�[�g�E�A�C�����h�тɂ���ċ����M�����Đ�����㏸�C���ɓ삩��̊C�̎�������C����C�Ɏ�荞�܂�C�ݕ��̓s�s�������ŊC���N���̑�K�͉������W�����J���������Ă���̂ł͂Ȃ����A�������A���݂̓s�s�������ō~���Ă��܂����߂ɁA�c��̊���������C���ď�̓앗�ɂ���ē������ɑ��荞�܂�A���ʂƂ��āA�������̊������A�җ��R�����z�����t�F�[�����ۂ̊g��Ƃ��������̂Ɍq�����Ă���̂ł͂Ȃ����ƥ���B
�@�J�[�e���Ɖ������q�[�g�E�A�C�����h�N���̊C�ݕ��̏㏸�C���̑т��ď�ɂ�����삩��̎�������C�̐N�����Ւf���A�������̓������܂Ő������������܂�Ȃ��Ȃ��Ă���\�����w�E���Ă���̂ł��B
�@�܂�A�C�ݕ��ō~��s�s�^�W�����J�͎M���Ȃ����߂ɂ��̑唼���C�ɖ߂���A�s�s�̐������ł�����җ��R���̏W����ł͑S���J���~��Ȃ��Ƃ����X�������i����Ă���̂ł͂Ȃ����ƥ���B�������A���̉������Ó��ł���Ȃ�A�q�[�g�E�A�C�����h�ɂ��s�s�^�W�����J�̑����ƁA��s�s�̐��s���A�劉���Ƃ������ۂ͗����̊W�Ői�s���Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł��B
���̉�������������A��s�̐��r�Ƃ��Ă̎R�ԕ��̋���_���́A�s�s�^���J�����ڂ��ɂ݂Ȃ���A�J���J���Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��B
�@���ɁA"�ł�������̑�Ԕ���"�ŏ������悤�ɁA���y��ʏȂ̉͐�̉J�A�핢���A�n�������H���A���������A����ɂ͔_���Ȃُ̂ꐮ���A�g�呢�тȂǂɂ���āA��s�s�A�n���s�s�A�_���A�R�т��킸�A�̑S�Ăɂ����ĕs�t�I�Ȋ��������N����A��������ď�̗[���̌����ɏے������悤�Ȍ��ۂ��N���钆�A�ĈȊO�ł��h�V���u���I�ȍ~����������Ă��܁B�q�[�g�E�A�C�����h�͂��͂�Ă����̖��ł͂Ȃ��̂ł��B |
| �@ |
| �������Ă͂Ȃ�Ȃ����� |
| �@ |
�@�ꉞ�A�ΏǗÖ@�I�Ȃ��̂��܂߂āA�q�[�g�E�A�C�����h�ւ̑�̂悤�Ȃ��̂��Ă��܂����B�������A���̂Ƃ���"�S���ƂȂ�"�Ƃ����v���@�ł��܂���B
�@����́A�n���s�s�ł͂��̑����肪���ʂ����̂�������܂��A��s�s�ł͂قƂ�ǎ肪�łĂȂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv������ł��B
����́A�n�\�ɐ������Ԃ��Ƃ��Ă�����ł͂��ꂾ���̗]�n�����Ȃ�����ł��B
�@�܂��A����鐅�����n���ӂŒ��B���A�܂��A��������Ƃ��Ă��A���̂��߂̋�ԁi�Ⴆ�����������j��A�Ҍ����邽�߂́u�����Ă���n�\�Ȃ����\�y�v�Ƃ��������̂̐�Ηʂ��s������̂ł��B
����́A��s�s�̕K�R�ł����Ȃ��̂ł���A���܂�ɂ��ߖ��ɂȂ����s�s����̂���Ƃ����x�N�g���A�܂�A�l���̕��U�����ǂ����Ă��K�v�ɂȂ��Ă���̂ł��B
�]���āA�����O��Ƃ��āu�H�ƓI�ȋZ�p�v�ɂ���ď��K�͂Ȑ��z�����鎖�͕����I�ɉ\�Ƃ��Ă��A���ǂ͗]�v�ȃG�l���M�[�𓊓����邱�Ƃɂ����Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�܂��A����Y�ƊE�̋����ȋZ�p�ҒB�͂��̕����ł����������l�����Ȃ��Љ�\���ɂȂ��Ă��邩��ł��B
�@���̖��Ɋւ��Ắu�H�ƓI�ȋZ�p�v�͌��ǂ̂Ƃ��돬���ł����Ȃ��A�ً}���I�Ȏ��P�̎�i�ł����Ȃ��̂ł����āA�{���I�ɂ͐l�U����������������̂ł��B
�ƁA����ƁA��s�@�\�̈ړ]�ƕ��U�̕����܂��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B
�@����ł́A�s�s�̕��U�͂��ꎩ�̂Ƃ��ĉ\�Ȃ̂ł��傤���H���ɂ͂��܂���҂ł���Ƃ͎v���܂���B
�@����́A���{�̕x��Ɛ肵�A����ɗ͂������Ă����s�s���̕s���Y���L�҂��A�n���̍����ɂ���Đ������Ă�����v�\���̔j��������炷�悤�Ȏ�s�̉�̂ɓ��ӂ���Ƃ͓���l�����Ȃ�����ł��i��s�ړ]�\�z�ւ̔����A�J��Ԃ��s�s���ƕs���Y���L�҂���N���鎖�͗ǂ��m���Ă��邱�Ƃł��j�B
�@�]���āA���̑�s�s���̋���y�n���{��苒���A���̂��Ƃɂ���ē��{�ɌN�Ղ�������Ɛ�I���Z���{��@���ׂ��Ȃ����肻�ꂪ�\�ɂȂ�Ƃ͎v���Ȃ��̂ł��B
�@�����A�����ŁA�B��̌����I�ȉ\�����w�E���Ă��������Ǝv���܂��B����́A���q���Ɩ��Y���ł��B
�@���݂ł��r���̗���ȂǂŐQ���肷��z�[���E���X�̏�ɂ͒N���Z�܂Ȃ������}���V����������������c���Ă��܂����A���q���Ɩ��Y���͂��̌X��������ɏ������鎖�ł��傤�B
�@�����ȕč��n�o�[�h�̃G�s�S�[�l���Œ|�������Ə������炵�����Y�K���̔j��A���w�K���̂���Ȃ鏊���ቺ�A�x�T�w�ɂ��x�̓Ɛ�́A���̏��q���A���Y��������ɑ�K�͂ɐ����i�߁A�ߏ萶�Y�̋ɒv�ɂ���s�s�s���Y�̉��l���������I�ɐ����i�߂镨���I��b������^���Ă���鎖�ɂȂ�ł��傤�B
�@�������A���̃q�[�g�E�A�C�����h���ւ̓����K�R�ł������̂ł͂Ȃ��̂��Ƃ����v���͏����܂��A������ɂ���A�~�܂�ʃq�[�g�E�A�C�����h���ւ̓��́A����Ɉ�w�A�s�s��l�ԂɂƂ��ďZ�݂Â炢���̂ɂ��邱�Ƃł��傤�B
�����āA��s�s�s���Y�����l�̒Ⴂ���̂ɕς��邱�Ƃł��傤�B�������邱�Ƃɂ���āA�n�߂ēs�s�̉�̂��\�ɂȂ�̂ł��B |
| �@ |
| ���y��ʏȂ����y�Đ��Ȃ� |
| �@ |
�@���̂��Ƃ͂Ȃ��A������"�Ŕ̑}���ւ�"����Ȃ����Ǝv���邩������܂��A���͔��ɏd�v�ȈӖ��������Ă���ƍl���Ă��܂��B
�@�Ƃ͌������̂́A����قǂ܂łɔj��A�Ȃ��A�Ƃǂ܂�Ƃ����m��Ȃ��s�s�̊������ւ̓������~�߁A"�s�s�̐��z���ǂ��Đ�����̂�"�Ƃ��������l����ƁA�C�̉����Ȃ�悤�Ȏv�������܂��B
�������A���ɖ߂��Ă��������Ȃ��̂ł��B�@ |
 |
| �摜�͍��y��ʏȂg�o |
| �@ |
�@�q�[�g�E�A�C�����h���������邽�߂̓�����▂�@�Ƃ��������̂������ł͂���܂���B
�@�Ȃ��Ȃ�A���ݐi�s���Ă��鎖�Ԃ͖��Ăȕ����I���ۂł����āA��������ɖ߂��ɂ͕����I�@���ɏ]���ȊO�ɕ��@�͂Ȃ�����ł��B
�����A�����A���\�N�|���Ĕj�����𐔏\�N�����Č��ɖ߂������̂��ƂȂ̂ł��B
�������A���ɐF�X�ȋZ�p�����܂�Ă����ł���A�{�C�Ŏn�߂�������Ό��ʂ͔�r�I
��������Ă��邱�Ƃł��傤�B
�@�������A�]�˗���ɓo�ꂷ��悤�ȓ��{�����߂����͂ł��Ȃ��ł����A�����ĕs�\�ł��Ȃ��̂ł��B
�@���݁A�s�K�v�ɂ܂�Ȃ��������Ƃ��������Ă��܂��B
���H���݈������Ă݂Ă��A���ɋ����ߏ�ł���A��x�g���������H�ɕ�����t���A���ɓ�Ԑ������A�����𗼕��t���A���̓I�ɁA���H�̏�ɂ܂œ��H���Ă���̂ł��i�ꗱ�ʼn��x�����������j�B
�s��Ȃ�����m�炸�A�n���s�s�ł����̂悤�Ȃ��Ƃ��J��Ԃ���A����ɓV���芯���Ƃ������A�����H���t���ė���Ȃ��̂ł��B
����A���ɔ����Ƃ����鉽�X�Z���^�[�≽�X�X�^�W�A���Ƃ��������̂Ɏ����ẮA���������S���s�K�v�ł���ɂ�������炸�A���������������������������͂��ŋ������I�Ƀs���͂˂��鎖������B��̖ړI�Ƃ��đ���ꑱ���Ă���̂ł��B
�@���̂��Ƃ��t�ɍl����A�s�K�v�Ȃ��̂葱������قǂɂ��̍��͂܂��L���ł������Ƃ������Ƃł���i�����������̂ɂ��s�\�ɂȂ��������m��܂��j�A���Ɏ��R���Đ��̂��߂ɐ���̑ǂ̐�ς����Ƃ��J�n����A���Ӗ��Ȏ��Ƃ��Ӗ��̂��鎖�Ƃɓ]���ł���Ƃ������Ƃł��B
�{���A���̂悤�Ȕn���������ɍ��ƓI�������₷���قNj����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��̂ł���A�����̕x�������ɓ��������z�����Ȃ�A�����̍K�������債�A�Ȋw�I�A�����I�������ێ������͂��Ȃ̂ł����A���y�̍r�p�������܂ł����ȏ�A�d�����Ȃ����ƂȂ̂ł��B
�@�������A��������{�ɓ����x�̗]�T������Ƃ����[���͂���͔��Ɋ낤���̂ł����i*�j]�A���̖��͔�r�I�ȒP�Ȃ̂ł��B
�@����������Ȃ��s�K�v�Ȍ������Ƃ��J��Ԃ���Ă��闝�R�́A�y���ƎҁA�c���A���������Ȋ����I�Ȍo�ϖԂ����肠���A������ێ����A���̒��ō��Ƃ̕x�𗩂ߎ�葱���Ă��邩��ɊO�Ȃ�܂���B
�]���āA�ނ�͂��̌o�ϖԂ��ێ��������邽�߂Ȃ�A�����Ȃ鎖�Ƃ����ł��͂��Ȃ̂ł����āA���Ƃ��ƃr�W�����ȂǂƂ������̂��������킹�Ă��Ȃ��ނ�́A�����B�̌o�ϖԂ��ێ��ł���Ȃ�ΐV���������ˑ勴���������H������Ȃ������͂��Ȃ̂ł��B
���̂��߁A�q�[�g�E�A�C�����h���ۂ��A�ނ炪����Ă���������ɐ������ЉЂł��邱�Ƃ����m�ɂȂ�A���̕ύX���K�v�ł��鎖�����������i�������A����������ȊO�A����������߂͂��Ȃ��ł��傤���j�A�L���ŏZ�݂₷���������Ԃ����߂̎��R�Đ��^"��������"�i**�j�����X�Ƃ��Ă��n�߁A�ނ玩�g���l���ɐ��������������A������Ӗ��𗝉�����͂��Ȃ̂ł��B
�������K�v�ŏ����̔�p�ł��̎��Ƃ͍s����̂ł���A�y�����̎В��ɂ����|���`���z�킹��K�v�͂�܂���i���̎��Ƃœ����l�Ԃ̋��^���ꗥ�Œ�ɂ��邾���ł���͉\�ɂȂ�܂��j�B����͑��債�����鐶���ی��Ǝ��R�Đ��^�������Ɣ�Ƃ�����ւ�邾���Ȃ̂ł��B
�@�������A���Ƃ̃x�N�g����ς������邽�߂ɂ́A�y�؊����Ɏ��炪�q�[�g�E�A�C�����h���̍ő�̌����҂ł���A�s�s�����̂������ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����ӎ��A���O��A�����ޕK�v������̂ł��B |
| �@ |
| �b�x��@�@�g�o�C�p�X�����͌�ʏa�������炷�h |
| �@ |
�@�o�C�p�X�̃o�C�p�X���̂܂��o�C�p�X�c�����葱�����Ă��܂����A����ɕ����Č����_�̐��͑��������čs���܂��B
�u�o�C�p�X�����͌�ʏa�������炷�v�́A���m�Ɍ����A�M���҂��̕Њ�ɂ���Ē������ʉߎ҂̗��ցA�ߋ����ړ��҂̐h���ň����}��Ƃ������̂ł�������܂���B
�����Ɍ����I�]�����s�����̂悤�ɂ����Ȃ�Ȃ��̂ł��B
������₷�����邽�߂Ɋȗ����������f���Ő������܂��傤�B
�\���H�Ƃ��̎��ӂ̓��H�ƌ������f��������Ă݂܂����B |
|
|
�����̌����_���͂P���P���P�A�S�̂�1�{�W���X�i��������R�{�̓��H�̂R�̓��j
�Ίp����Ɉړ�����ƒʉ߂ɗv��������_���́@�T�i�R�j |
|
|
�����̌����_���S���Q���Q�A�S�̂͂S�{�P�Q���P�U�i��������S�{�̓��H�̂S�̓��j
�Ίp����Ɉړ�����ƒʉ߂ɗv��������_���́@�V�i�T�j |
|
|
�����̌����_���͂X���R���R�A�S�̂͂X�{�P�U���Q�T�i��������T�{�̓��H�̂T�̓��j
�Ίp����Ɉړ�����ƒʉ߂ɗv��������_���́@�X�i�V�j |
| �@ |
�@���H��Α���قnj����_�̐��͓��䋉���I�i�P���S���X���P�U���Q�T���R�U�c�j�ɑ��������A�M���҂��ɂ�郍�X�ŋt�Ɍ�ʏ�Q�������Ă��܂��̂ł��B
�@�ȒP�Ɍ����A�����Ձi�X�e�j����Ղɕς��Ă���̂��A���̌�ʐ���ƌ�����ł��傤�B |
| �@ |
������ �F�c��10�{�̐��i 9�e�j�����ՂŁA�e�̐���81�A�}�X�ڂ̐���100
��@�� �F�c��19�{�̐��i18�e�j�����Ղ�19�H�Ղƌ����A��_�i�ځj�̐���361�A�}�X�ڂ̐���324 |
| �@ |
��Ղ̖ڂ̂悤�ȋ��s���a���₷�����R�͂���Ȃ̂ł����A�u�a���邩��c�v�ƃo�C�p�X��Α���قǁA�t�ɐM���҂����ԁi���ς͂R�O�b����ꕪ�̔����~�����_���ƂȂ�j�ɂ��A�����āA�ʉ߂ɗ]�v�Ȏ��Ԃ�����Ă��܂��̂ł��B
���̂��߂ɁA�ꂵ����ɗ��̌����𑝂₷���ƂɂȂ�̂ł����A���̌����𑝂₹�Ηǂ��̂��Ƃ����ƁA����ɂ��o��ƌ����_�̌������t���Z���̂ł��B
�������A���͔ނ�����̂��Ƃ͏\���ɕ������Ă��āi������[�̏���l�͕ʂł����j�A�V�������m�ۂ��邽�߂Ƀo�C�p�X�H�������}���Ă���̂ł��B
�����āA������o�ϓI�ɂ��A��ʍH�w�I�ɂ��j�Y���邱�ƂɂȂ�̂ł��B |
| �@ |
| ���ė��R�A���A���y��ʏȁI�I |
| �@ |
���{���ЂɈ����C�荞�֓��R�́A�����͂��Ƃ��A�܂₩���Ƃ͌����`���I�ɂ����݂����鍑�c��Ɠ��t����������A���ɂ͍��Ƃ�ۂݍ��݁A�S�y��j�łɊ������̂ł����A���̎��́A���E�ł��ł��������������y��j���������y��ʏȂ��A�����ƍ��Ƃɔj�Y�������ƂɂȂ�ł��傤�B
"��X�̔]���ɐV���Ȑ��E���\�z����邱�ƂȂ��A���݂̓]���͂��肦�Ȃ��B"�̂ł��B |
| �@ |
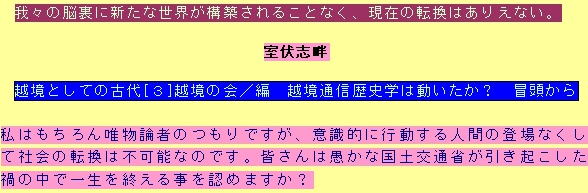 |
| �@ |
| * �@���͂���͔��Ɋ낤���̂ł����@�F�@����ɂ��Ă͊��ɏ\�������Ă��܂��̂ŁA��������Q�Ƃ��Ă���������K���ł��B�����ł́A���̈ꕔ���f�ڂ��܂��B |
| 86�D��������Ǝ���i�������Ƃ͎~�߂��Ȃ��I�������A�I���I�j |
| �@ |
����@�R���N���[�g�͉i�v�̂��̂ł͂Ȃ�
���̏��e��2005�N9��15���t�ŃA���r�G���e���́u�L���C�|���p���|�[�g�U�v�Ɍf�ڂ������̂ł��B
�@ |
�@�������Ƃ��I���I�Ƃ����ő�̗��R�́A����܂łɑ����Ă������̂��A���ɁA�\���傫���Ȃ�߂��Ă���A���͂��ɕ����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��邩��Ȃ̂ł��B
�@�Ⴆ�A�V�����⍂�����H�ɂ����Ă��A�������̂͌܁Z�N�ɋ߂Â����̂��o�n�߂Ă���A���Ȃ�̃R���N���[�g�̗i�S�̕��H���̑��j���ڂɕt���n�߂Ă���̂ł��B
�@���ɁA���s���̐V�����Ƀg���l������R���N���[�g�傫�����������ƍl���܂��傤�B���ɑz��ɂ���͂��ł���Ď��̐��͎���Ă���Ƃ��Ă��A���݂̂悤�ȉߖ��_�C���A�����^�]�̒��Ŏ��̂��h���Ȃ������ꍇ�A���̂��Ƃɂ��]���҂͍���̂i�q�����{�̎��̒��x�ł͎��܂�Ȃ����Ƃ͕����肢��������͂��ł��B
�@���炭�A���̌��݂̔w��ɂ��鑽���̏����i�C���A�V���u�E�R���A�o�c�̎��c�j���猾���āA�ォ�猚�݂��ꂽ�R�z�V�����̕�����قNJ�Ȃ��ƌ����Ă���悤�ł��B
�@���C���V�����̎���́A�썻�Ō��݂��i�߂��Ă����ɁA���E��̓S����Ƃ��������{���{��`�̋C�T������A�}���蔲���H���ȂǂƂ������͍̂l�����Ȃ������Ƃ���Ă��܂��B�S�H���Z�p�ҁA�S����g���l���̋Z�p�ҁA��Ƃ̃����������ɍ��������Ƃ����̂ł��i������ǂ��܂ŐM������̂��A���ǂ͕s���Ȃ̂ł����j�B
�@�������A�V�����H�̗������܂����A���̃��C���^�i���X�ɑ����̗\�Z�𒍂����܂Ȃ���Ȃ�Ȃ���ԂŁA�ڂ̑O�ɔ������������V�������ݎ��Ƃ��������Ƃ��Ă��A�ŏI�I�ȑI���͌����̉ғ����̐��H�ɓ�����U��������Ȃ��͖̂��炩�ł��邩��ł��B
�@�i�q�����{�̎��̂ɏے������悤�ɁA���S�����A�o�c��D�悵�Ď��̂��������邱�Ƃ͂���ł��傤�B�����A��ʍ����͐V�����ݍH�����̎��̂͋��e�ł����Ƃ��Ă��A���̂ɂ���Ď��炪�]���ɂȂ邩������Ȃ��ғ����̊����H���ɂ����闘�p�҂̎��̂����͐�ɋ��e���Ȃ��ƍl������̂ł��B���̂��Ƃ��A���������V�����������H����D�悹����Ȃ��Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ł��B
�@�c�O�Ȃ���A�����̋]�����������̎���ɂ���ĐV�K���~�܂�\��������̂ł��B���݁A�S���K�v���̂Ȃ�����V�����̌��݂��c�_����Ă��܂����A���Ă݂�ƁA�܂��A���Ƃɗ]�͂�����Ƃ�������̂ł��傤���B���ۂɂ͍��̎؋��͋��e���x���z���A�V���肵�����銯���Ɠy���Ǝ҂ƈ��������Ƃǂ��ɂ���āA�Ƃ����̐̂ɍ����̒��~��H���ׂ��Ă���̂ł����A"���Z���Ȃ��i�ł��Ȃ��j�o��"�̎����ł��傤�B
�@���āA�č��̓��[�K���������ɂ����đS���̍������H�ɒʍs�~�߂̋�Ԃ����o���܂����B������g���l���̃��C���^�i���X�ɒǂ��A�V�K�H���̌��݂͂��납�A�����̘H�����g���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł����B�w�i�ɂ������͖̂���}���狤�a�}�ւ̐����̈ڍs�ɔ����\�Z�z���̍팸�ł���A���̌�̃��[�K���R�g�͕��a�ȓy���Y�Ƃւ̓�����}���A�R���Y�Ƃւ̓����𑝂₵���̂ł����B�������A���܂�ɂ����݂���剻�������Ƃ̌��ʂł��������Ƃ͌����܂ł�����܂���B�ǂ����A���݂̓��{�̐��������l�̓������n�߂Ă���悤�ł����B
�@���{�̃��[�^���[�[�V�����̔g�̓A�����J�ɔ����I�߂��x��A�܁Z�N��㔼�Ɏn�܂����̂ł����A�A�����J�ō������H�̗i���ɋ�����g���l���j�����ɂȂ�̂����݂���܁Z�N�߂��o�߂������Z�N��ł��B���{�̍������H�����݂���܁Z�N�ɋ߂Â����̂��o�n�߂Ă���A���낻�듯����肪�n�܂�̂ł��B
�@�Q�l�̂��߂Ɂu���H�\�����̍���̊Ǘ��E�X�V�̂���������ψ���v�Ȃ鍑���Ȃ̊̂���c�̂̕����Ă݂܂��傤�B����́A�������H�����łȂ���ʂ̓��H���܂܂�Ă��܂��̂ŁA��@�͑S�̂ɍL�����Ă��邱�Ƃ��ǂ��킩��܂��B�@����@�ȉ��B
**�@���R�Đ��^"��������"�@�F�@����ɂ��Ă��ȉ����Q�Ƃ��ĉ������B |
| �@ |
| 119�D�@�����H�����푈���H�i��������R���ւ̐U��q���������j |
| ���̏��e��2006�N11��3���t�ŃA���r�G���e���́u�L���C�|���p���|�[�g�V�v�Ɍf�ڂ������̂ł��B |
| �@ |
�@���悢������_�c���{�i�����Ă��܂������A���ی�h���ɂ��쌛�h�̕�����������J����Ă��邩���m��܂���B���͂�����쌛�h�ł��������͈�x������܂���B
�@���̃u���W�������@�����ȋʏ��̂��Ƃ����q����Ȃǂ��肦�Ȃ����ŁA�S�͎����ĐÂ��ł��B���a���@�Ȃǂƌ����Ă͂��܂����A����������ɂ��Ă��A���{�Ƃ������Ƃ͗��ł͒����ɌR���͂�ςݏグ�Ă�����ɁA�j�Ɏ����Ă̓��C�V�����[�،���҂܂ł��Ȃ��A�̂���č��̊j����������ŗ��܂����B�͑D�ɐςݍ���ł̊�q�͏㗤�ł͂Ȃ��ȏ㎝���ł͂Ȃ��Ɨ������Ă����A�����J�̊��ٔF���A�ނ�̊�Ŏ�������ł��Ȃ��ƒʍ����Ă�������������ŐM�p���Ă����ӂ�����Ă����ɉ߂��Ȃ������̂ł��B
�@�܂�A�\�����͉��߉����ɂ���ĕ\�ʏ�͌��@������Ă���悤�ɑ����Ă��������̘b�ł����āA���ł͌��@�Ȃǎ���Ă������ȂǑS���Ȃ������Ƃ����̂����߂��鎯�҂̏펯�ł��傤�B
�@�]���āA�푈�ɂ������ȗ��A���ꂽ���ȂǂȂ���x���Ȃ����ɂ�����"���a���@�����I"�ƌ������Ƃ́A���o�ł��邩�A�t�Ɏ�点�Ă����Ǝv�����݂����������A��`���������������̎��ł����Ȃ��A�ނ���A����Ă����Ȃ����̂��A���I�ƌ������Ƃɂ���āA������J���҈�ʂ̌쌛�ւ̌��z���q�����߁A�����Ɋ�Ȉ��S���Ɩ�������^���閃��̂悤�Ȃ��̂ł����Ȃ������̂ł��B
�@���͂��̂悤�Ȃ�����Ȃ������I�^������v�z�ɂ͈�̋����������Ă��܂���B�܂�A��㖯���`���ō��̂��̂ł����邩�̂悤�ɗi�삵�A���̌�����ێ����鎖�ɗ��v�����o�����쌛���́i���̊���������������v�V�n�c������̑������g�������j���A���̐�㖯���`���Ō�I�ɂ���Ԃ�s�����āA�S�Ă̘J���ҁA�������H�Ǝ҂�����ԂɊׂ�����ׂ��Ă��܂����̂��A���̏I���ł��錻�݂ƌ����ׂ��ł��傤�B
�@�q�b�g���[�E�i�`�̑䓪���ł������`�I�ƌ���ꂽ���C�}�[�����a�������ݏo�������̂ł������悤�ɁA���̂����܂�������̏���|�s�����Y���̓o�ꂱ���A�A�����J�ɋ��v���ꋖ�e���ꂽ��㖯���`�̎Y���ł����Ȃ��̂ł��B
�@�]���āA��x�����ꂽ���ȂǂȂ��������@���쎝���鎖�ɂ����ς��鎖�ɂ��Ӗ��Ȃǂ��肦�Ȃ��̂ł��B
�@�܂��A���͎͂���̃u���W�������͂��ێ�����K�v�����鎞�ɂ͌��@�����낤���Ȃ��낤���A���������Ȃ鎞�ɂ��l���݂ɂ���A�J���ҁA��ʍ����ɏe�������A���@�Ȃǖ��W�ɖ\�͂�U�邤�͂��ł��B
�@����͂Ƃ������Ƃ��āA���ɂ͊�ȕʂ̈��S�����Y���Ă��܂��B����́@86�D��������Ǝ���i�������Ƃ͎~�߂��Ȃ��I�������A�I���j�ŏ������悤�ɁA��͌������Ƃ����ݏo�������̂��]��ɂ���剻���V�������n�߂����̌��ʂƂ��āA�V�K�����]�T�ȂǑS�������Ȃ��Ă���Ƃ������ƁB��́A�����I�ɂ͎�����̃N�[�f�^�[�Ƃ������ׂ�����̏O�c�@��̏����ɂ���āi�����܂Ō��ʂł��茻�ۂɉ߂��Ȃ��̂ł����j�A�c���p�h�ȗ��A���ƌ��͂������Ă����X�����A���H���A���ݑ��ȂǂƂ������쌛�I�i�e�����I�j�y�����P�C���Y��`�҂ǂ���������������r�����ꂽ���Ɓi�n���ł͂܂����̘A���������h�ł����j�ɂ���āA���a�Y�ƂƂ��Ă̓y���Ƃ̊������������Ă��鎖���\���ł��邩��ł��i��k�����`�������̂悤�ɐ₦������߂��͗L�蓾�܂����j�B
�@�������A�����������Ȃ��Ƃ������Q���̕����傫���������Ƃ͑����ł��傤���A�R���V�t�g�ɂ��R�����S�̌������Ƃ̔�d���オ�邱�Ƃɂ���āA���̒��S�͏��X�ɍ����\�~�T�C�����Y�A���{�b�g���퐶�Y�A�C�R�͂̑����Ƃ��������̂ɃV�t�g���Ă������ƂɂȂ�ł��傤�B
�@�P���ɂ͌����܂��A�A�����J�ł͖����̖���}�ƌR���̋��a�}�Ƃ����݂ɓ���ւ���Ă��܂����B�������A�č�����}�̒����͌����ł���A���̔w��ɂ͊C�O�Ƃ̋����ɕ������������Y�̗������݂�����̂ł��B�ő��A����Ȃ��A���邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�����J�̎p�����Ď��܂��B����A�q��@�ƕ��퐶�Y�ȊO�ɋ����͂̂���Y�Ƃ͂Ȃ��̂ł��B�����炱���A��ʎE�C�����̂Ƃ������C���N��N�����A�h���̗��t���A�]���ăA�����J���{��`�̒S�ۂƂ������ׂ��������Ζ����m�ۂ��ɍs�����̂ł��B�������Ă��邩�ǂ����Ƃ͊W������܂��B
�@���{�ɂ����ẮA��O�͑S�Ă̗\�Z���R���Ɛ푈�ɗ�������ł��܂������A�s��ɂ���Ė������Y�ȊO�͋�����Ȃ��Ȃ�܂��B�������A��㕜�����I���A�������Y�Ő��E��Ȋ����Ă��Ԃ��K�����ɂɓ���n�߂��A�������s���ł����邩�̔@�����ߑ��ɂ��y�؍H���ɋ���Ȗ��ʌ������n�߂�̂ł��i�c���A�|���A���ہA���{�A�쒆����j�B�����āA���̕t�����������݂̍����j�]�̊�b�ɂ���̂ł��B����ȘA����M�p���đI���œ��[�𑱂��鍑���ɂ���������܂����i���͈�x�����[������������܂���j�A�}�������̓��ŕ������l���Ă��Ȃ����̂悤�ł��B
�@���{��`�o�ςƂ͐l�Ԃ̗~�]�����ɉ�����������̂��̂ɉ߂��܂��A�����O��ɐ��x���������̂����{��`�Љ�ł��B���̎Љ�͐₦���鐶�Y�Ɛ₦����j����J��Ԃ��Ȃ���ΐ������Ȃ��̂ł��B�܂��ɐ푈�����͍œK�ł���i�����ł����Ɩ��̖����ɂ��₦���X�V���s����̂ł��j�A�y���Ƃł͕s�K�v�ȓ��H��_�������葱������̂ł��B
�@���͂��̌R���ւ̐U��q�������ɕ��a�Ȗ����Ő��Y�𑱂���B��̕��@�Ƃ���"��������"�i���R�Đ��^�j���Ă����̂ł����i�u�L���C�ٕρv�j�A�����ɂ͌��ݘJ���҂̒����̒ቺ�ɂ���ė\�Z�͍팸���ꂽ���̂́A���Ɨʂ͌��̂܂܂��A�ނ��둝�����Ă��܂��A����Œ肵�����̂悤�ł��B�@
�@�����A���Ɨ\�Z�̎�荇���̑��ʂƂ��ẮA�ǂ���瓹�H���̔s�k�ƂȂ����Ƃ������Ƃ���ł��傤�B
�R���Ɩ����̐U��q�͓����n�߂܂����B������A���̎����N���ɂȂ��Ă���ł��傤�B
�@�������_�҂́A�O���ɂ��[���Ȋ�@�ɒ��ʂ����e�Ղɕ��������_�҂ɕϖe���鎖�ł��傤�B |
|
|
| �@ |
�@���{���{��`���ĂыZ�p�͂����Ԃ��A��������ۋ����͂��ێ��������邽�߂ɂ́A�s�K�v�ȓ��H��_���葱������́A���{�b�g���Y��~�T�C�����Y�̕��������l�Ԃݏo���͂��ł���A���̈Ӗ��ł͓y�����̃{���N�����q���x���c�������́A�w�͂��闝�n�̐��n�Ȋw�����������Љ�̕����]�܂����Ǝv�����̂ł��B
�@����A�R���Ƃ����A�����M�[�����������l���o�Ă��鎖�͏��m���Ă��܂����A����͂���Ӗ��Ŏ��{��`�Љ�̕K�R�ł����āA�R�����Y�����ł���A�����ʂ̐��́i�Љ�̐��j�Ɋ�����ȊO�ɂ͕��@���Ȃ��̂ł��B
�������A"�R�����Y�ւ̃V�t�g�������ׂ��ł͂Ȃ��I"�ƁA����̂Ȃ�A����͎��{��`��œ|���鎖���l���Ē����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�ł��傤�B�Ȃ��Ȃ�A�X�N���b�v�E�A���h�E�r�����h���J��Ԃ����́A���{��`�̓����ł��邩��ł��B
�@�C�O�ł��������Ǝv���܂����A���{�ł͐퍑����i���ۂɂ͂�������͂邩�ȑO�̌Ñ�܂ők�邩���m��܂���B�������������H���͐푈�ɂ��z�ꁁ�؎��̋����J�����N���Ȃ̂ł�����j�̈�ʎG���͕����ɂ����Ă͏镁�����������Ă����킯�ŁA���̌�A������̍]�ˎ���ɂȂ�ƁA���̒����̋Z�p�҂̈ꕔ�͍��L�g�ƌĂ��p���H�◭�r�H���̓y�؋Z�p�҂ɂȂ�̂ł��B���̂悤�ɁA���͂͐펞�ɂ͐퓬�����Ă���̂ł���A�����ɂ͏镁����y�؍H�������Ă����̂ł��B���������A�G�W�v�g�̃s���~�b�h���V���������Ƃ̐푈�̌�̌������ƂƂ��Ē������đ��点���Ƃ�����������܂����ˁB���̂悤�ɁA�푈�ƌ����H���Ƃ͑o�q�̌Z��Ȃ̂ł���A����������ł��邱�Ƃł��傤�B
�@�]���āA"�푈���I"������O�̔���^���Ɓi�n�����Y�}�A���̑��̎Љ��`���}�A��{���A�ꉞ�A���݂̂悤�ȑ��i�H�j���\�ʉ�����O�̖q����O�Y��˓c�鐹��̑n���w��܂ł͏����Ă����܂����A����ȊO�̓��@�@�n���͗��悵�ĐN���̐땺�ɂȂ�A��y���n���瑂���T�A�ՍϑT���킸�c��͑S�ė��^������A��ŗ�ؑ�ق̂悤��"�@���҂͖{���͐푈�ɔ��������̂�"�ȂǂƂƂڂ��������������̂ł��j�ƌ��݂̊��ی�c�́i�����Ȃ�_���ȂȂǂɗ��p������Ɉ͂����܂�Ă��܂����m�o�n�@�l�Ȃǂ͂������ʂł����j�͓����Љ�I���i��Ӗ��������Ă��鎖���������Ă���̂ł��B�܂茠�͂�������Ȃ̂ł��B
�@�������A����A�R���V�t�g����w���܂��Ă���ƁA"���y�ƍ����̖��Ƃǂ��炪���"�Ƃ����������邱�ƂȂ���A���Ή^���̎Љ�I���i��ʒu�t�����ς���Ă���ł��傤�B�������A�L�ȍ��y�����Ƃ����^�����ꎩ�͍̂���Ƃ��s�ΓI�Ӗ���������������̂Ǝv���܂��B
�@�������A�Ō�I�ɂ́A"���Ȃ��͍��ƂƐ���Ă�����ׂ����Ƃ����܂����H����Ƃ����̕���s�������ł�����Ȃ����Ƃ��̂Ă܂����H"�Ƃ����I���𔗂���̂ł��B���͂��̂ǂ���Ƃ��قȂ�"���U"�ɖ��͂������Ă��܂��B���̕s�����Ŋ�]�����ĂȂ����Ƃ�����̂Ă�̂ł͂Ȃ��������܂�Ȃ��Ȃ��č��Ƃ���ǂ����Ă���̂ł��傤�B
���{��ꍏ���������łы���I�łтȂ����čĐ��Ȃ��I |
| �@ |
| 64�D��21�����s�S����c, ��8��L���C��s�m�ΊC�t�H�[����in �v���āE���� �����W�}���_���u�����������錾�v���� |
| ���ی�^���̌��E�Ƃ��ꂩ��̉ۑ�i�������Ƃ̒�āj |
| �}��쐅��茤�������i�����j �Ð� ���v |
| �@ |
| ���j��̂͂��܂� |
| ���̏��e��2005�N4��16���t�ŃA���r�G���e���́u�L���C�|���p���|�[�g�U�v�Ɍf�ڂ������̂ł��B |
| �@ |
�@����܂ŁA�S���̊��ی�c�̂⑽���̔��Ή^���͈���������Ɋ�@��������Ȃ��牡�\�Ȋ�Ƃ�j��I�Ȍ������Ƃɑ��鏟���ڂ̂Ȃ������𑱂��Ă��܂����B
�@�Â��͖����̓c�������ɂ�鑫�����R�̍z�łƂ̓����A��⣃_�����ݔ��Ή^���A�l���s�����A���i�̉����A�����Đ����a�i�ׁc�c�ȂǑ����̓����̑O�j�����݂��܂��B�n�߂͐����l���̕ω��ɂ�鐅���̈�����A������ɂ��ꂽ��Ƃ��r�o���鉘���������A���ځA��C��͐��C�Ȃǂ��������̂����������̂ł����A���ꂪ���̍����炩�ς�͂��߂܂��B�V�����������A�������J�ߑ����鑽���̃_�����݁A�S���t��A�X�L�[��Ȃǂ̑�K�̓��]�[�g�J���A�u�i�̐X��j��ѓ����݁A���C����A���ǐ�͌������A���Ή^�����Ȃ���Δ������X��ʂ�j���Ί_�����ۂ̋�`���݁A�����g���̑�\�����݁A��Ӑ�_�����݁A�M���`�����|���p���Ɓc�c�ȂǁA���Ԋ�Ƃɂ����̂��獑�ȂǍs������݂̖�肪���|�I�ɑ����Ȃ�A���S���������Ƃɂ����j��Ɉڂ��Ă��Ă��܂��B
����́A�ŏI�i�K�ł̂�����Y�Ɣp�������ˑR�Ƃ��đ傫�Ȗ��ł��邱�Ƃɂ͕ς肪�Ȃ��̂ł����A�H�Ɣr���━���Ƃ��������Y�i�K�Ő��ݏo����鉘�����Y�Ƃ̋�������A������x���܂�����ۂ�^���Ă��邩��ł��傤�B
�@�܂��A���ی�^���Ƃ͓ǂ��ʂ̂Ƃ���A�ǂ��Ċ����������x�̂���Ӗ��ŕێ�I�ȉ^���ł��B�������A���ꂷ����قƂ�ǒB���ł��Ă��Ȃ��̂������Ȃ̂ł��B���Ԋ�Ƃ̏ꍇ�̓S���t��J���̂悤�Ɍo�ϓI�ɐ��藧���Ȃ��Ȃ�Ύ�������̂ł����A���Ɗە����̌������Ƃ̏ꍇ�͌o�ό��������čs���邽�߂ɍی����Ȃ��������Ă���̂ł��B�������Ƃ����܂��Ɏ~�܂鐨���ɂȂ��̂́A�s�����̂��̂������S������ł��Ă��Ȃ����ƂɌ��������߂�ׂ��ł��傤�B
�@�����̊��ی�^���́A���Ԋ�Ƃ����Y�����ɂ���Ē��ځA���C���Ȃǂ����������Ƃɑ��Đ��Y�̐����⑀�Ƃ̒��~��i�����̕⏞����Ƃ�s���ɋ��߂���̂ł����B���������Ƃ���ƁA���Ɍ����̂͊����̕ʂȂ���K�͂ɍ��y��j�������K�̓��]�[�g�J���A�_�����݁A���Ƃ��~�߂�^���ł����B�������A���̑������B������Ă��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł����A�����܂ł������ƌ����邩������܂���B |
| �@ |
| �����͉��� |
| �@ |
�@�����ŁA�|���p���Ƃ��l���Ă݂܂��傤�B�C�T�J���͌��݁A�H�������S�Ɏ~�܂��Ă��܂��B�������A����͈ꎞ�I�ŏu�ԓI�ȏ����ɉ߂����A���ɂȂт����ك��x���ł͂����ǂ���ɕ������̂�������܂���B�������A����قǂ̑�K�͌������Ƃł����~�܂�i�K�ɓ��B�����̂ł��B���̏u�ԓI�ȍ��݂ɗ����Ċ��ی�^���̏�����W�]���鎞�A�K�R�I��"�~�߂���ɂǂ�����̂�"�Ƃ������ɓ˂�������܂��B
�@���ꂪ�u�~�߂鎞��͏I������v�Ǝ��B�������Ă���Ӗ��Ȃ̂ł��B�������A"�܂Ƃ��ȕ⏞����邱�Ƃ��A�~�߂邱�Ƃ��܂܂Ȃ�Ȃ����łȂɂ��o�J��"�ƌ����邩������܂���B�������A���̖�肪�����ł��Ȃ���ΈˑR�Ƃ��Ė����͂���ė��Ȃ��̂ł��B�t�ɁA���������˔j�ł���A�V���Ȕj���H���~�߁A����ꂽ���R�����Ԃ����Ƃ����ł͂Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��̂ł��B
�@����A���܂Ȃ��A�j��͑����Ă���̂ł����A���ɎY�Ɗ����ɂ���Ĉ�����������������ƂȂǍs���ɂ���Ĕj�ꂽ�܂܂ɂ���Ă���������u����Ă��܂��B
�@���ꂪ�����̃e�[�}"��������"��K�v�Ƃ��闝�R�Ȃ̂ł��B
�C�T�J���̂悤��"���ɗ����Ȃ��ǂ��납�S���Q�����������炳�Ȃ��������ʂȌ������Ƃɑ��āA��ׂ�ɂȂ鎑�����܂�����������̂�"�Ƃ����{��͏\���ɗ����ł��܂����A����͐����ȋc�_�ł��傤�B�ł́A�C�T�J���̑��h��y�����͐ς𑱂���_���⍻�h�_���A���������~�߂����Ƃ̒��C�����h�A���������ꉟ���������Ƃ����l���Ă��Ȃ������ȎO�ʒ��萅�H��͐�����̂܂܂ɂ��Ă����̂ł��傤���B
�@�t�̌�����������A���̔j�ꂽ�������̂܂܂ɂ��Ă����Ă�����Ă͍���̂ł��B���l�ɒǑK�̂悤�ł����A��͂�A�I�����͂��ꂵ���Ȃ��̂ł��B�������A����܂ł̂悤�ȊÂ��`���z�킹��K�v�͈����܂���B���y�̕����ƐV���Ȏ��R�̍Đ��ɕK�v�ŏ����̓����ŁA�����I�������Č��ɖ߂���Ƃ��n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B���ꂪ�A���������l���Ă����O���̊��ی�^���ł��B
�@�������A����"��������"�ɏ��o�����Ƃ��ł���A���邱�Ƃ��ړI�ƂȂ��Ă���������Ƃ̕�����ς������邱�Ƃ��\�ɂȂ�̂ł��B�Ȃ��Ȃ�A�ނ�̓_���⓹�H���{���ɕK�v�����瑢���Ă���̂ł͂Ȃ��A�H�����̂��̂��~�����Č������Ƃ𑱂��悤�Ƃ��Ă��邩��ł��B���̂���"��������"���n�߂���A���ʂȐV�K��}�����邱�Ƃ��ł��邤���ɁA���X�g���ŊX���ɕ���o���ꂽ��ʂ̎��Ǝ҂̌ٗp�ݏo���A�A�Ƃ̋@���D���l���̃X�^�[�g���C���ɗ��ĂȂ������t���[�^�[�Ƃ��j�[�g�Ƃ��Ă�鎖����̎��Ǝ҂ɐV���ȐE�ƌP�����s�����Ƃ��ł���̂ł��B
����ɁA��ʂ̌ٗp��n�o���邱�Ƃ͐V���Ȍi�C�z�肾���A�o�ςɊ��͂�^���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃɂ��Ȃ�̂ł��B�]���^�̌������Ƃ𑱂��Ă��Ă������̑唼���ꕔ�̗����W�c�ƈꈬ��̓y���Ǝ҂̉������������B�����ꑱ���邾���ŁA�����̓����ɂ͑S���U�������Ȃ��̂ł��B����ɑ��āA�Ꮚ���҂̏A�Ƃ��g��ł���A�ނ�ɂ͒��~�̗]�T���Ȃ����߂ɁA�l�����������͑S�ď���ɉ��ƂɂȂ�V���Ȍi�C�z��n��o���̂ł��B
�@���̂悤�ȁA�o�ς̍ďz�Ƃ������Y���̕t�������̍Đ��A�����ւ̓���j��ł�����̂����A���Ƃ̐������ɂ����܂ŌŎ����銯���@�\�Ȃ̂ł��B
�@���ђn�̍L�t���]���A�������e�g���E�|�b�h�̓P���A�����������Ƃ����l���Ă��Ȃ������ȎO�ʒ��萅�H�̒n���Z���^�e�����H�ւ̓]���A�����o�����X���������x���z���Č��݂��ꂽ��ʂ̃S���t��̕��сA�A�X�t�@���g�Ōł߂�ꂽ���ԏ�̐Z���^�ւ̓]���A�_���̓P���A���z��j����������}���������������ɓ]������c�c�ȂǁA�܂��A�����̔j�ꂽ�������u���ꂽ�܂܂ł͖L���Ȋ������߂����ƂȂǑS���ł��Ȃ��̂ł��B���ɔj�ꂽ�Ƃ���ł͕����̂��߂̍�Ƃ��ɂł��J�n���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B���R�Ȃ���ނ�ɐӔC����点�邽�߂ɁA�v��i�K����Z�����Q�����Č������ƂƂ����`�ŕK�v�ŏ����̌o��ōĐ����Ƃ��n�߂����悤�ł͂���܂��B |
| �@ |
| ���Y�s �� ���v |